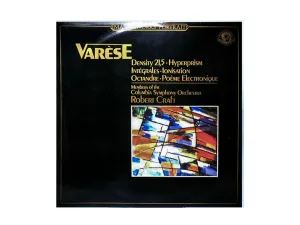エキスポ・クラシックス——この言葉をご記憶の方は、もう相当なご年齢だろう。これは、1970年の大阪万博で、その参加公演として開催されたクラシック音楽の数多い演奏会のことである。あの時は、大阪の旧フェスティバルホールを会場に、カラヤンとベルリン・フィル、セルとクリーヴランド管、バーンスタインとニューヨーク・フィルなどをはじめ、ベルリン・ドイツオペラ、ボリショイ劇場といった「超大物」が綺羅星の如く集うという、豪華絢爛たる布陣だった。いずれも、大阪で公演した後に、東京公演を行なっている。
特にボリショイ劇場は、それが日本初登場だった。チャイコフスキーの「エウゲニ・オネーギン」と「スペードの女王」、ムソルグスキーの「ボリス・ゴドゥノフ」、ボロディンの「イーゴリ公」という4つの「定番」を引っ提げての日本公演である。オーケストラや裏方を含めて総勢395人の大部隊の来日、モスクワから持って来た大道具も12トントラック50台分、というのは、当時としては画期的な規模だったはずだ。その費用の4分の1を日本の万国博覧会協会が持ち、4分の3をソ連政府が負担したそうである(「音楽の友」1970年10月号、福原信夫プロデューサー談)。
東京公演(8月28日~9月6日)は新芸術家協会の扱いだったので、筆者は財布をはたいて4演目全てのチケットを買い、初めて本場の豪華絢爛たるロシア・オペラの世界を堪能したのだった。あの舞台の、目の眩むような豪壮さは、全盛期のボリショイ劇場の威力を物語っていただろう。「ボリス」と「イーゴリ公」で披露されたロシアの歌劇場の合唱団の声の底力も、それはもう、なんとも形容し難いほどの凄さだった。
今でも忘れられないのが、初めて観た「スペードの女王」である。これは、演出がボリス・ポクロフスキーで——のちにボリショイ劇場やモスクワ室内歌劇場とともに何度も来日することになるあの名匠だ——ドラマとして非常に微細な演技を織り込んだ舞台をつくっていたため、強く印象づけられたのかもしれない。たとえば第2幕第1場の仮面舞踏会で、主人公の士官ゲルマンの背後から友人たちが「3枚のカルタ!」という運命的な言葉を彼に囁いてさっと身を隠してしまう場面だが、ポクロフスキーはこれを、背後に一列に並んでいる大勢の仮面客たちの中から数人を振り向かせて歌わせ、ゲルマンがぎょっとして後方を見返った時には、彼らは早くも仮面客たちの列の中に溶け込み、われわれ観客でさえも、客たちのだれがそれを言ったのかもはや判らなくなっている、という幻想的な舞台構図をつくり出していたのだった。
また、これも印象的な構図だったのは、最終幕で、必勝のカルタの秘密をつかんだゲルマンが賭博場へ飛び込んで来る場面だ。ポクロフスキーは、まず舞台奥にある大きな窓を通して、狂気の如く走って来る彼の姿を見せ、しかるのちに彼が舞台上手から息せき切って入って来る、という演出にして、圧倒的な緊迫感をつくり出していたのである。ここでは、一般に演出されるような、ゲルマンがゆっくりと賭博場に入って来るという設定では、とても彼の思い詰めた心理を表わすことはできないはずなのだ。筆者はこの舞台を観て以降、ポクロフスキーが大好きになった。それから25年も経って、初めて彼にインタビューする機会を得た際、巨匠にその話をして大いに彼を喜ばせた思い出もある。
もっとも、その日の上演には、奇怪な事故もあった。第2幕の幕切れ、ゲルマンの脅しにショック死してしまった老伯爵夫人が恐ろしい形相で椅子にのけぞっているという場面で、なんと幕が閉まらなくなってしまったのである。もう音楽も終わってしまい、会場内はしんとして、だれもが息を止めて呆然と舞台を見つめていた。ゲルマンもリーザも動けず立ち尽くし、伯爵夫人も恐ろしい形相を崩せぬまま動けない。あれじゃ辛いだろう、幕が閉められないのなら、せめて照明を落すとかすればいいのに、と筆者もやきもきしながら眺めているしかなかった。1分以上もそれは続いていたろうか。ようやく舞台袖にざわざわと声が起こり、なにごとか怒鳴り声も交りはじめて……。
その日、指揮をしたのは、若きゲンナジー・ロジェストヴェンスキーだった。彼の音楽の素晴らしかったことも、筆者がその上演を忘れられぬ一因になっているだろう。
(最終回)

とうじょう・ひろお
早稲田大学卒。1963年FM東海(のちのFM東京)に入社、「TDKオリジナル・コンサート」「新日フィル・コンサート」など同社のクラシック番組の制作を手掛ける。1975年度文化庁芸術祭ラジオ音楽部門大賞受賞番組(武満徹作曲「カトレーン」)制作。現在はフリーの評論家として新聞・雑誌等に寄稿している。著書・共著に「朝比奈隆ベートーヴェンの交響曲を語る」(中公新書)、「伝説のクラシック・ライヴ」(TOKYO FM出版)他。ブログ「東条碩夫のコンサート日記」 公開中。