
8月7日にフェスタサマーミューザKAWASAKIで太田弦指揮九州交響楽団の演奏を聴いた。曲目は、ビゼーの歌劇「カルメン」抜粋、ショスタコーヴィチの交響曲第5番ほか、というものであった。一見、「カルメン」とショスタコーヴィチの第5番という名曲の並んだプログラムであるが、太田によると、これはショスタコーヴィチの第5番が「カルメン」の旋律を引用しているというつながりでの選曲であった。
ショスタコーヴィチの第5番が「カルメン」の何を引用しているかというと、「ハバネラ」の一節である。第1楽章でのフルートの息の長い旋律は、「ハバネラ」の「ラームール、ラームール(恋、恋)」の部分から採られているといわれているし、第4楽章の最後で長調に転調したところでの「ラ・レ・ミ・ファ♯」の主題は、「ハバネラ」で合唱が「気をつけなさい!」と合いの手を入れる「ラ・レ・ミ・ファ♯」の音型の引用だといわれている。ただし、作曲者本人はそれについて言及していないので、後世の人々の推測でしかない。最後の勝利の「ラ・レ・ミ・ファ♯」の主題が「ハバネラ」から来ているとすると、先に長調の「ラ・レ・ミ・ファ♯」の主題が作られて、第4楽章冒頭の「ラ・レ・ミ・ファ」という威圧的な主題は「ハバネラ」の音型を短調にすることによって後から導き出されたということになるのだろうか。謎は深まるばかりである。
8月23、24日には、ユライ・ヴァルチュハ指揮読売日本交響楽団がR・シュトラウスの「メタモルフォーゼン」とベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」というプログラムを演奏した。シュトラウスの「メタモルフォーゼン」は、1945年に、第二次世界大戦によって破壊された祖国ドイツへの悲しみを込めて書かれた。そこで引用されているのが、ベートーヴェンの交響曲第3番「英雄」の第2楽章「葬送行進曲」である。つまり、「メタモルフォーゼン」には戦争の犠牲者への追悼の意味が込められている。「メタモルフォーゼン」では、「英雄」の第2楽章の葬送行進曲から派生した主題が奏でられていくが、楽曲の最後に葬送行進曲の主題が初めて完全な形で引用される。
9月20、21日のカーチュン・ウォン指揮日本フィルハーモニー交響楽団の演奏会では、伊福部昭の「SF交響ファンタジー第1番」とラヴェルのピアノ協奏曲が並べて演奏された。これは明らかに、ラヴェルのピアノ協奏曲第3楽章の「ドシラ、ドシラ」という音型と伊福部の「ゴジラのテーマ」が似ているということでのプログラミングに違いない。伊福部はラヴェルの音楽を好んでいたが、「ゴジラのテーマ」がラヴェルのピアノ協奏曲から(ラヴェルへのオマージュとして)採られたのか、あるいは偶然の一致なのか、確かなことはわからない。
そういえば、かつて(2019年4月)、太田弦は神奈川フィルハーモニー管弦楽団の演奏会で、コルンゴルトの「嵐の青春」とJ・ウィリアムズの「スターウォーズ」のメインタイトルを並べて取り上げていた。このときはウィリアムズがコルンゴルト作品から影響を受けたことが実感できた。
「引用」をキーワードにすると、いろいろ興味深いプログラムが作れるに違いない。

やまだ・はるお
音楽評論家。1964年、京都市生まれ。87年、慶応義塾大学経済学部卒業。90年から音楽に関する執筆を行っている。著書に、小澤征爾の評伝である「音楽の旅人」「トスカニーニ」「いまどきのクラシック音楽の愉しみ方」、編著書に「オペラガイド130選」「戦後のオペラ」「バロック・オペラ」などがある。




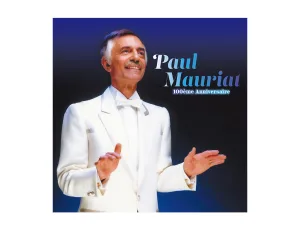





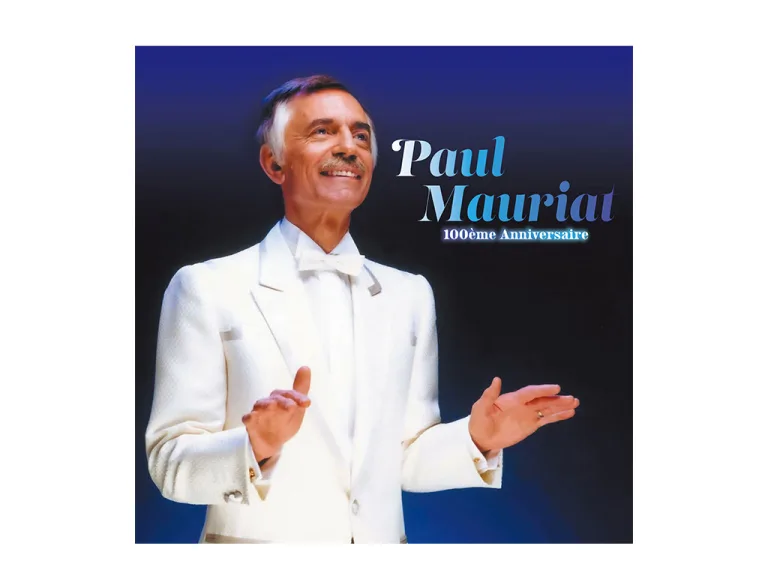










![第2幕 左から公証人(阿瀬見貴光)、トニオ(澤原行正)、マリー(砂田愛梨)、伍長(市川宥一郎)、ベルケンフィールド侯爵夫人(金澤桃子)、シュルピス(山田大智) 撮影:三枝近志 提供:公益財団法人ニッセイ文化振興財団[日生劇場]](https://classicnavi.jp/wp-content/uploads/2024/11/628d6f47cb18c632a2c3e57bb72dec12-300x200.webp)
