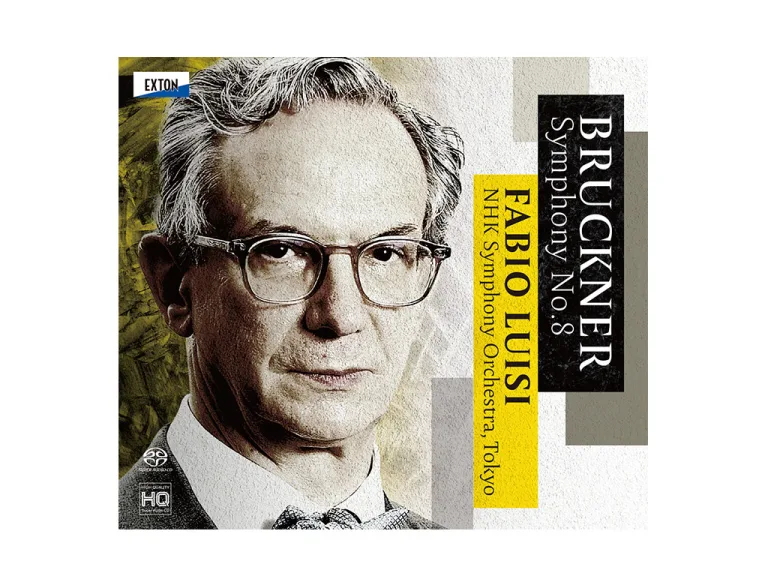2023年は、セルゲイ・ラフマニノフの生誕150周年にあたる。このアニバーサリー・イヤーに、たとえば、東京フィルは、5月と6月の定期演奏会でラフマニノフ・プログラムを組み、広島交響楽団は7月と12月の定期演奏会でオール・ラフマニノフ・プログラムを披露する。新日本フィルの2023/2024シーズンは、ラフマニノフのピアノ協奏曲第2番で開幕し、彼の交響曲第2番で締めくくられる。どれだけラフマニノフが愛されているのかと感心する。
現在では信じられないかもしれないが、今から半世紀前、作曲家としてのラフマニノフは、音楽学者や音楽評論家からほとんど評価されていなかった。ニューヨーク・タイムズの高名な音楽評論家、ハロルド・ショーンバーグは、1970年に著した「大作曲家の生涯」のなかでラフマニノフについてこう書いている。
「彼は19世紀のモデルを臆面もなく利用した作曲家であり、その結果、学者、歴史家、プロ、人気作り屋のいずれからも、ほとんど無視されてきた」(亀井旭・玉木裕訳)
ラフマニノフが20世紀半ばの学者や評論家に評価されなかったのは、彼が時代遅れな作品ばかり書いて、音楽の進歩になんら貢献していないと考えられていたからだ。
「ラフマニノフは1901年に『ピアノ協奏曲ハ短調』(第2番)を書き、この類型から外れることなく、本質的には同種類の音楽を作り続けた。大衆は彼の作品を愛したが、全世界の多くのプロ音楽家にとって、彼はチャイコフスキーの足元でロシアの涙を流すだけの、創造面では無に等しい存在だった」(同上)
20世紀半ばの進歩主義的な音楽史観において、ラフマニノフは価値のない作曲家とされた。そして、前衛的な現代音楽が趨勢(すうせい)の時代の音楽学者や音楽評論家は彼を敢えて無視しようとした。
しかし、ラフマニノフの作品がコンサートのプログラムから消えないで演奏され続けてきたのは、聴衆の支持があったからにほかならない。かつてはラフマニノフ=大ピアニストというイメージが強く、オーケストラの演奏会で取り上げられる作品もピアノ協奏曲中心であったが、近年は、交響曲などのオーケストラ作品にも人気がある。
たとえば、2017年にラトル&ベルリン・フィルがこのコンビでの最後の来日公演で交響曲第3番を演奏するなど、ロシアの指揮者やロシアのオーケストラでなくても、彼の管弦楽作品を積極的に取り上げるようになり、それらは、オーケストラの非常に重要なレパートリーとなっている。2023年は、日本のオーケストラでも、幻想曲「岩」、交響詩「死の島」、交響曲第1番など、演奏機会の少ない作品が取り上げられる。
ラフマニノフの作品の魅力はもちろんその哀愁を帯びた旋律の美しさにあるが、彼の素晴らしさは、無調性音楽や十二音技法が主流となりつつあった20世紀前半において、恥じらうことなく自信をもってその旋律美を活かした作品を残し続けたことにあるといえるのではないだろうか。音楽における進歩主義史観の嵐が去った現在、ラフマニノフが正当に評価され、生誕150周年が祝われるのは、喜ばしいことである。

やまだ・はるお
音楽評論家。1964年、京都市生まれ。87年、慶応義塾大学経済学部卒業。90年から音楽に関する執筆を行っている。著書に、小澤征爾の評伝である「音楽の旅人」「トスカニーニ」「いまどきのクラシック音楽の愉しみ方」、編著書に「オペラガイド130選」「戦後のオペラ」「バロック・オペラ」などがある。