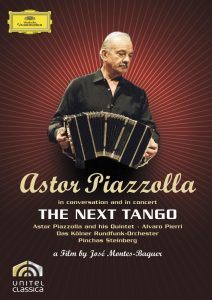常に予想の一歩先を行くジョナサン・ノット&東響によるベートーヴェン
在京オーケストラによるベートーヴェン演奏の中で、今、最も聴衆に刺激を与えてくれるのはジョナサン・ノット指揮、東京交響楽団のコンビと言っても過言ではないだろう。11日夜のオール・ベートーヴェン・プロでも事前の予想を良い意味で裏切る演奏が披露され、そんな思いを一層強くした。

1曲目はゲルハルト・オピッツをソリストに迎えてのピアノ協奏曲第2番。オピッツは、あたかもフォルテ・ピアノを意識したかのように、ダイナミックレンジをあまり広く取らずに柔らかめの音色で、端正に弾き進めていく。ノットと東響はいつものシャープな表現を抑え気味にして穏やかにソロを支えていた。
驚きはメインの「田園交響曲」であった。これまで聴いた第9などこのコンビによるベートーヴェンとはかなり印象を異にするアプローチであったからだ。彼らのベートーヴェンといえばピリオド(時代)奏法に寄せたスタイルを基調に、ベーレンライター版の校訂に加えてノット独自の解釈も織り交ぜながら、すさまじいまでの推進力を伴って音楽が組み立てられていく、というものであった。ところがこの日の「田園」はピリオドのスタイルに則ったものであったが、全体に丸みを帯びたふくよかな表現が際立っているように感じた。

例えば第1楽章終盤、第1主題を再現する弦楽合奏の箇所(422小節目から)、通常は音を切って演奏されることが多いが(ベーレンライター版でスタカッティシモとスラーが交互に記されている)、ノットは全体にスラーをかけて滑らかに弾かせていた。こうしたアーティキュレーション(音のつなげ方)の見直しが随所に行われ、さらに和音を構成する各パートの音量バランスにもかなり手が加えられていた。その結果、聴き慣れた「田園」とはひと味違った斬新な雰囲気を持った響きとなり、ノットが「田園」をロマン派への扉を開けるきっかけとなった作品と位置付けていることが伝わってきた。終演後はオケが退場しても拍手が鳴りやまず、ノットのソロ・カーテンコールとなった。
(宮嶋 極)
公演データ
東京交響楽団 第716回定期演奏会
11月11日(土)18:00 サントリーホール
指揮:ジョナサン・ノット
ピアノ:ゲルハルト・オピッツ
ベートーヴェン:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調Op.19
ベートーヴェン:交響曲第6番ヘ長調Op.68「田園」
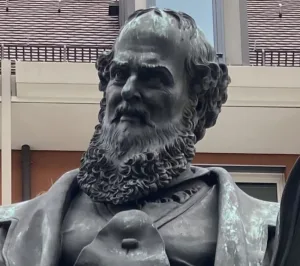
みやじま・きわみ
放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。