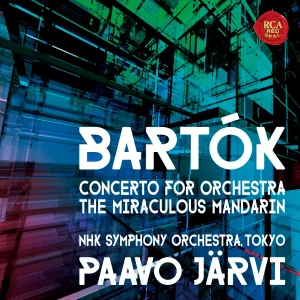不気味な「死の島」と戦慄の交響曲「バービイ・ヤール」をモダンなオーケストラ音楽として表出
「ショスタコーヴィチ没後50年記念」と銘打った都響スペシャル(前日のA定期も同プロ)。桂冠指揮者エリアフ・インバルの指揮で、ラフマニノフの交響詩「死の島」とショスタコーヴィチの交響曲第13番「バービイ・ヤール」が披露された。

不気味な絵画を音化した「死の島」と、ユダヤ人の大量虐殺をメインテーマにした「バービイ・ヤール」のプロとなれば、肺腑(はいふ)を抉(えぐ)るような表現も想像されるが、インバルは(おそらく)あえてそうせずに、適距離から俯瞰するようなアプローチで、モダンなオーケストラ音楽として表出し、結果的に両曲の特質をナチュラルに浮き彫りにした。
「死の島」は特に不気味さを強調せず、書かれた音をストレートに表現。絵全体の描写ではなく、絵の世界を少しずつ明らかにしていくかのような、ドラマティックな音楽が展開された。

「バービイ・ヤール」も、交響曲第10番あるいは第11番の延長線上に位置する大スケールの〝シンフォニー〟。テンポは全体に速めで、全楽章のトーンも一貫している。しかしながら音楽は壮絶極まりなく、曲の持つ戦慄性が自然と耳に届く。それを成就させたのが都響の機能的・重層的なサウンドであるのは間違いない。一部挙げると、第5楽章冒頭のフルート二重奏の場面変化やフーガ部分の弦楽の応酬は絶品だった、
また本作では、エストニア国立男声合唱団とバスのグリゴリー・シュカルパが絶大な威力を発揮した。彼らは、昨年2月に井上道義と同曲で共演したオルフェイ・ドレンガー及びアレクセイ・ティホミーロフに比べるとソフトな声質ながらも、終始雄弁な歌唱で楽曲の深みの表出に寄与した。

ここ2回のインバル&都響を聴くと、かつての引き締まった響きが蘇った感がある。今後もこのコンビは聴き逃せない。
(柴田克彦)
公演データ
エリアフ・インバル指揮 東京都交響楽団 都響スペシャル
2月11日(火・祝)14:00東京文化会館
指揮:エリアフ・インバル
バス:グリゴリー・シュカルパ
男声合唱:エストニア国立男声合唱団
プログラム
ラフマニノフ:交響詩「死の島」Op.29
ショスタコーヴィチ:交響曲第13番 変ロ短調Op.113「バービイ・ヤール」

しばた・かつひこ
音楽マネジメント勤務を経て、フリーの音楽ライター、評論家、編集者となる。「ぶらあぼ」「ぴあクラシック」「音楽の友」「モーストリー・クラシック」等の雑誌、「毎日新聞クラシックナビ」等のWeb媒体、公演プログラム、CDブックレットへの寄稿、プログラムや冊子の編集、講演や講座など、クラシック音楽をフィールドに幅広く活動。アーティストへのインタビューも多数行っている。著書に「山本直純と小澤征爾」(朝日新書)。