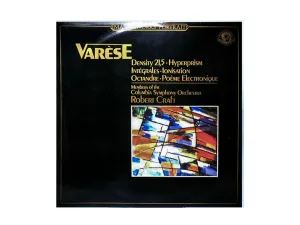「大分の県民オペラで、吉四六(きっちょむ)さんを主人公にしたオペラができてね。僕が歌うの。吉四六って、知らない? ほら、大分の民話に出て来る、あの頓智の吉四六。観に来ませんか? 県民オペラというものを知るいい機会だと思いますよ」と立川清登さんに言われて、吉四六とは大分の人だったのか、などと初めて気がついたほど、のんきな私だった。もちろん、吉四六という名の焼酎があることなど、知る由もなかった。それはちょうど今から51年前、1973年のこと。
初演の10月1日、大分へ飛び、市内の大分文化会館に着くと、すぐに立川さんの楽屋に案内される。立川清登(旧名・立川澄人)さんといえば、二期会所属の人気抜群のオペラ歌手で、フィガロやパパゲーノなどの軽快な役柄を得意とし、ミュージカルにも出演、テレビやラジオにも引っ張りだこの存在だった人である。彼はちょうど吉四六役のメイクの最中だったが、「いらっしゃい」と振り向いたそのいでたちは、こちらがワッとのけぞるような素っ頓狂な、大きな目に赤いダンゴ鼻、頬かむりに野良着。なるほどこれは民話オペラだけあるわ、と感心させられるような、素晴らしい扮装だった。
創作オペラ「吉四六昇天」の制作は、「大分県民オペラ」である。ストーリーの原作は宮本清氏と大分合同新聞、台本は阪田寛夫氏、作曲は清水脩氏。加藤公康氏の指揮する40人編成の大分交響楽団がピットに入り、県民オペラ合唱団と児童合唱団、地元の歌手たちが出演していた。立川清登さんも、言うまでもなく、大分県出身の名歌手である。
プロローグで、立川さん扮する吉四六が重い薪の束を背負った馬を曳いて登場すると、それだけで満員の客席から笑いと拍手と歓声が起こる。舞台と客席との、この親しい雰囲気。くたびれた馬の背から薪を下ろしてやり、自分で背負ってやった吉四六さん、ヤレ楽になったと安心する馬に向かい「おい待て待て、楽になった分だけ、ワシが乗ってもよかろうが」とそのまま馬の背へ——。ここで客席からはまた爆笑と拍手が起こる。
ラストシーンでは、あらぬ疑いをかけられたため天高くハシゴを昇って逃れた吉四六が、しかしついに力尽きてハシゴから手を離してしまったとき——「吉四六さんはトンビになってどこかへ飛んで行ったんだ、吉四六さんは死んではいない!」と子供たちの合唱が歌うと、客席からは大きな共感の拍手が起こる。吉四六という人物に寄せる大分の人たちの深い愛。そして、郷土出身の大スター歌手、立川清登に対する強い信頼感。立川さんの歌と演技は、それはもうあたたかく、人間味にあふれて、見事なものだった。「吉四六昇天」のこの初演における大成功には、彼・立川さんの存在こそが、大きな役割を果たしていたのである。
キリシタンの娘が歌う「キリエ・エレイソン」に、吉四六の唱える「なんまんだぶ」が見事に重なる、などという音楽のシャレも面白く、清水脩氏は民話オペラとしての性格を巧みに音楽の中に生かしていたと言えるだろう。おなじみの郷土の民謡(「けんなん節」など)のフシが現れると、身体でリズムを取り、時には手拍子までやりはじめるお年寄りたち。会場には、子供たちまでの広い年齢層にわたって、オペラを心から楽しんでいるという雰囲気が満ちていた。これが民衆に愛されるオペラというものだ。当時、小長久子氏が総監督として率いていた大分の「県民オペラ」は、まさしくその「愛されるオペラ」を掲げて、市民オペラ運動の先頭に立っていたのだった。

とうじょう・ひろお
早稲田大学卒。1963年FM東海(のちのFM東京)に入社、「TDKオリジナル・コンサート」「新日フィル・コンサート」など同社のクラシック番組の制作を手掛ける。1975年度文化庁芸術祭ラジオ音楽部門大賞受賞番組(武満徹作曲「カトレーン」)制作。現在はフリーの評論家として新聞・雑誌等に寄稿している。著書・共著に「朝比奈隆ベートーヴェンの交響曲を語る」(中公新書)、「伝説のクラシック・ライヴ」(TOKYO FM出版)他。ブログ「東条碩夫のコンサート日記」 公開中。