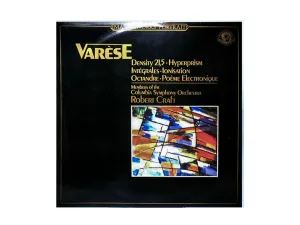「音楽とはかくも美しく楽しきものか(中略)ミュンヒンガーの両手の動きにつれて、十五の弦楽器によって醸し出されるアンサンブルの美しさ。それは聴く者の胸に、春の潮のようにやわらかくゆたかに通って、陶酔境に誘うのであった」。——これは1956年の3月10日、日比谷公会堂で行われたカール・ミュンヒンガー指揮シュトゥットガルト室内楽団(シュトゥットガルト室内管弦楽団)の演奏会について、雑誌「レコード芸術」(音楽之友社)5月号のグラビアに写真とともに掲載された一文である。
第2次大戦後、廃墟(はいきょ)から蘇(よみがえ)って復興を続ける日本で、初めて外国のオーケストラのナマ音を聴いた音楽愛好者たちがどんなに感動したか、今では想像もつかぬことだろう。私自身はそういう体験をした最初の世代ではないけれども、テレビやラジオ、新聞、雑誌などで、そのセンセーショナルな模様をおぼろげながら記憶している。
日本に来た最初の外国のオーケストラは、1955年5月のシンフォニー・オブ・ジ・エアで——その名称では分かりにくいので、招聘(しょうへい)元は「元トスカニーニNBC交響楽団」とか、そんな副題をつけていた——それはまさにその強大な音響の迫力で当時の日本の聴衆を震撼(しんかん)させ「日本オーケストラ界の黒船」とまで言われたようである。そしてその翌年3月に来日したのが、このカール・ミュンヒンガーの率いるシュトゥットガルト室内楽団であり、そのしっとりしたアンサンブルがみんなを酔わせたものだった。ちなみに、その直後の4月に来日したのが、パウル・ヒンデミットの指揮するウィーン・フィルハーモニー管弦楽団(抜粋メンバーによる中編成)で、これまた聴衆はその美しい気品のある音色に随喜の涙を流したものだった(と、伝えられる)。
その初来日したミュンヒンガーとシュトゥットガルト室内楽団は、3月10日の日比谷公会堂を皮切りに、4月1日の同ホールまで7回ほどの公演を行ない、バッハの「ブランデンブルク協奏曲第3番」や、モーツァルトの「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」などの名曲のほか、ヘンデルの「合奏協奏曲作品6の12」、バッハの「6声のリチェルカーレ」、ヴィヴァルディの「合奏協奏曲作品3の11」、パッヘルベルの「カノン」など、多彩なプログラムを演奏した、と記録にある。特に4月1日の公演では、オーボエとホルンにN響の団員を加えてハイドンの「告別交響曲」を演奏、「ローソクの灯を順に消してステージを去るという、さながらエステルハーツィ邸のいにしえを偲(しの)ばせる演出によって……」(レコード芸術5月号89ページ)とあり、これがまた感動を巻き起こしたらしい。ただ私の記憶では、同じ「告別交響曲」を旧NHKホールでも演奏し、それがテレビで生中継されたような気もするのだが……。一人、二人と順に退場して行く楽員たちの動きをテレビで眺めていた記憶が私にはある。ただ、その時のステージは明るいままだったので、あまり感動はしなかったという記憶もある。
前掲誌には、故・村田武雄氏(音楽評論家)が、レセプションでミュンヒンガーと立ち話をした記事が載っている。村田氏が「あなたのレコードではヴィヴァルディの『四季』が最も親しまれていますが、どうして演奏曲目に入れて下さらなかったのですか」と問うと、マエストロは「あれはチェンバロが必要ですから」と答えたという。村田氏「日本にもチェンバロがあることは新聞社からお知らせしたと思いますが」。M氏「ええ、出発間際に聞きましたので演奏者の手配ができませんでした」。どうやらミュンヒンガーは、日本にはチェンバロなどないと思っていたらしいのである。当時の欧米の音楽関係者の日本音楽界に対する認識の程度を窺(うかが)わせる話かもしれない。
村田氏は、その記事の最後にこう書いている。「シュトゥットガルトの合奏の純粋さを日本ではいつになったら得られるだろうか。この世界に達するにはまだ幾回か脱皮を重ねなければならないだろう」。
そのカール・ミュンヒンガーとシュトゥットガルト室内楽団は、それから16年後、1972年5月に再来日した。この時は、私はFM東京で当時担当していたライヴ番組「TDKオリジナル・コンサート」の無料公開録音演奏会に彼らを招聘し、当時東京の港区にあった郵便貯金ホールで、1600人の無料招待の聴衆を集めて、おなじみ「カノン」をはじめ、バッハやモーツァルトやグルックの作品を演奏してもらい、放送した。チェンバロには、小林道夫氏に客演をお願いした。実にしなやかで美しい演奏だったが、ミュンヒンガーが、半円形に配置された弦楽奏者たちの前で、右に左に忙しく動き回り、各奏者たちの目の前に接近しては、その都度細かい指示を与えるかのように、右手の指揮棒と左手を振りまわしていたのが印象的だった。すでにリハーサルを細かくやっていたはずなのに、なぜあんなに本番で細かく指示をだすのだろう、もしかしたらあれは単なるジェスチュアなのかな、と思ったりしたのだが——。

とうじょう・ひろお
早稲田大学卒。1963年FM東海(のちのFM東京)に入社、「TDKオリジナル・コンサート」「新日フィル・コンサート」など同社のクラシック番組の制作を手掛ける。1975年度文化庁芸術祭ラジオ音楽部門大賞受賞番組(武満徹作曲「カトレーン」)制作。現在はフリーの評論家として新聞・雑誌等に寄稿している。著書・共著に「朝比奈隆ベートーヴェンの交響曲を語る」(中公新書)、「伝説のクラシック・ライヴ」(TOKYO FM出版)他。ブログ「東条碩夫のコンサート日記」 公開中。