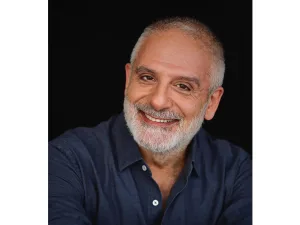アダルジーザを世界で一番勉強し
磨かれた歌唱にいっそうの輝きが
現在、欧州で一番活躍している若手日本人歌手は、脇園彩一択だろう。その十八番はロッシーニだというのが共通認識だと思う。ロッシーニ没後150年の2018年、作曲家の生地ペーザロの音楽祭で「セビリャの理髪師」のロジーナを歌い、2020年にも同じ役で呼ばれた。新国立劇場でも2020年2月にロジーナ、2021年10月に「チェネレントラ」のアンジェリーナで強い印象を残した。十八番であることは疑いようがない。
だが、脇園は別の方向でも飛躍を遂げている。2023年3月にボローニャ歌劇場で、前回この連載で紹介したフランチェスカ・ドットとともに「ノルマ」のアダルジーザを歌うのを聴いて驚いた。ベッリーニの長く優美な旋律を、美しく磨かれたレガートに揺れる心の色合いを添えながら歌い、精密に漸減するピアニッシモを加えた。このときアダルジーザはトリプルキャストだったが、脇園が群を抜いていた。
華麗なアジリタが要求されるロッシーニからの転向ではない。ロッシーニを歌う高度なテクニックはそのままにレガートを磨いたのである。
脇園は師匠のマリエッラ・デヴィーアから、将来なにを歌うか決めるように促され、いずれヴェルディを歌いたい気持をたしかめたという。そこで長く苦手意識を抱いていたレガートを、コロナ禍に徹底的に磨いた。とりわけアダルジーザは「2年間、世界で一番勉強したんじゃないか」と語る。
その成果が意外と早く確認された。2022年9月、スペインのア・コルーニャの劇場で歌う話が急きょ舞い込み、結果は「大成功で、一人勝ちしてしまいました」と脇園はいう。
いまの声が一番輝くレパートリー
その流れでボローニャかと思えば、その直前にも学びの機会があった。ジュネーブでドニゼッティ「マリア・ストゥアルダ」のカバーキャストを務めた際、ピアニストからイタリア語の二重子音や二重母音など、言葉さばきを徹底指導されている。「自分に欠けていた言葉の抑揚やニュアンスがすごく強化され、ア・コルーニャで歌ったときより1段階上がった感じがある」(脇園)という。
これまで脇園の軌跡を追い、要所で話を聞いてきたが、みずからの課題を的確に見極め、それを克服するべく合理的な努力を重ねる姿勢には感服するほかない。以前は声がいまほど飛ばず、いまより鼻にかかり、色彩やニュアンスもいまより乏しかった。しかし、そうした課題は聴くたびに着実に克服されている。かつてのフアン・ディエゴ・フローレスがそうだった。そんな脇園はいまアダルジーザに懸ける。
「『ノルマ』はいままで私が歌ってきた『セビリャの理髪師』などと色が違い、ロゼから赤ワインになったよう。まだ深いボルドーではないけれど、そこを目指す過程で、いまの私の声が一番輝くレパートリーだと思います」
自身がそう語るアダルジーザが、ボローニャ歌劇場の日本公演で聴けるとは、日本のファンは恵まれている。一方、「ロッシーニもまた、この先も私にとって大事な作曲家になっていくし、一つ大きなデビューを控えています」と語る。磨かれたレガートは、ロッシーニの役にもよい影響をおよぼすはずである。ますます脇園から目が離せない。

かはら・とし
音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。