ワーグナー作品上演の総本山ともいわれるドイツ・バイロイト音楽祭(祝祭)を4年ぶりに訪れた。取材したのは「ニーベルングの指環(リング)」(ピエタリ・インキネン指揮、ヴァレンティン・シュヴァルツ演出)の第2ツィクルス(8月5日~10日)と「タンホイザー」(ナタリー・シュトゥッマン指揮、トビアス・クラッツァー演出)の2回目(8月7日)の公演。開幕までにチケットが完売しないなどさまざまな議論を巻き起こした今年の同音楽祭について4回に分けて振り返る。初回は「リング」の演出について報告する。(宮嶋 極)

10年くらい前までは「世界一チケットが取りにくい音楽祭」と呼ばれていたバイロイト。実際、バイロイト友の会などに所属していない一般客はチケットを申し込んで購入の権利が回ってくるまで7、8年待たされることもあった。それだけ人気を誇っていたバイロイトのそれも「リング」のチケットが売れ残った。世界中のワグネリアンにとっても驚きの事態であった。バイロイト音楽祭は元々、ワーグナーが楽劇4作からなる大作「リング」を上演するために専用の劇場を建設し1876年に始めた祝祭(フェストシュピール)である。約150年間、「リング」はいつも一番の人気演目であったからだ。
ドイツ国内外のネット・メディアを検索してみると〝売れ残り〟の原因を作った元凶はシュヴァルツの演出だ、との論調が目についた。昨年、「神々の黄昏」のみNHK・BSプレミアムで放送されたが、その映像を見るとシュヴァルツら演出チームがカーテンコールに登場すると拍手がやみ、客席全体から大ブーイングが浴びせられた。ブーイングはバイロイトでは日常茶飯事ではあるものの、ここまで強烈なブーは珍しい。何より驚いたのは演出チームの何人かが短パンにサンダル履きでステージに登場したことだ。世界中のワグネリアンが聖地とも仰ぎ見る祝祭劇場の舞台にラフなスタイルで現れた演出陣の姿は、彼らの考え方の一端を表すものに映った。こうしたこともあり、長年バイロイトを支えてきた熱心なワグネリアンたちの多くが今年の音楽祭に行くことをやめたようだ。

現地で4作を通して見ると原作の設定を変更する読み替え演出ではあるが、思いつきのアイデアの羅列のような印象は拭いきれなかった。「ラインの黄金」の冒頭、この世の始原を表す音楽に合わせて双子の胎児の映像が投影される。シュヴァルツのプログラム・ノートによると、神々の長ヴォータンと地底に住むニーベルング族のアルベリヒは双子の兄弟であり、ヴォータンは富裕層、アルベリヒは貧困者。ヴォータンの邸宅に侵入したアルベリヒは庭のプールで遊ぶヴォータン家の幼児を3人のメイド(ラインの乙女)の隙を見て誘拐する、ということから物語が始まるという読み替えになっている。神々たちはモラルを失った現代の富裕層に置き換えられ、新装なった邸宅(ヴァルハル城)に設計士の兄弟ファーゾルトとファーフナーが代金を請求しにやってくる。当然、槍や剣、隠れ頭巾などのお馴染みのアイテムは登場しない。世界を支配する魔力を帯びた指環は男女の愛の結晶である子どもに置き換えられている。

ネットフリックスで配信されるような現代の人間模様を描きたいとシュヴァルツは登場人物の関係性も完全に改変していた。「ワルキューレ」ではジークリンデがジークムントと出会う前から既に妊娠していた。途中、それがヴォータンの子どもであることを暗示するような小芝居も。さらにジークフリートとハーゲンは兄弟だったと受け取れるような描写もあった。ブリュンヒルデの愛馬グラーネは彼女の愛人かボディガードのように描かれていた。そのグラーネ、「神々の黄昏」ではギービヒ家で惨殺されてしまう。ギービヒ家もまた退廃した現代の富豪の家。ロシアのオリガルヒに見えたりもする。「神々の黄昏」のフィナーレ、舞台はライン川河畔やギービヒ家ではなく、薄汚れた廃プールの底。ブリュンヒルデは惨殺されたグラーネの生首を抱えてジークフリートの遺体の横で息絶える。「救済の動機」に乗せて天上から首をつったヴォータンの遺体が汚物を垂れ流しながら降りてくる。これは22年のステージではなかったシーン、グロテスクであった。そして再び双子の胎児の映像が投影されて幕は閉じる。

読み替えのアイデアは一見陳腐だが、調べてみると原作の元ネタであるゲルマンや北欧の神話からヒントを得ている部分もいくつかあった。ただ、そうしたアイデアを集約して観客・聴衆に訴えかける演出のコンセプトが、まったく伝わってこなかったのも事実である。なお、今年は再演ということなのか、演出チームがカーテンコールに登場することはなかった。

バイロイトは読み替え演出の総本山でもある。100周年の1976年にプレミエされたピエール・ブーレーズ指揮、パトリス・シェロー演出によるプロダクションも当初は大変な批判を集めたが、今では名舞台としての評価が定まっている。実験工房(ヴェルクシュタット)ともいわれるバイロイトでは毎年、野心的な試みが行われる。当然、成功もあれば失敗もある。現在上演されているクラッツァー演出の「タンホイザー」は成功例であろう。2000年以降ではバリー・コスキー演出の「マイスタージンガー」、シュテファン・ヘアハイム演出の「パルジファル」、カタリーナ・ワーグナー演出の「マイスタージンガー」も大胆な読み替えが施されていたが、演出家の意図がしっかり伝わってきたという点では評価できるプロダクションだった。今回の「リング」の成否は果たしてどうであろうか。34歳の若手シュヴァルツの意欲は部分的には見るべきものはあったが、作品への深い理解とワーグナーの何にも代えがたい素晴らしい音楽へのリスペクトが大きく欠如していたように筆者は感じた。

☆公演データは下記からご覧ください。
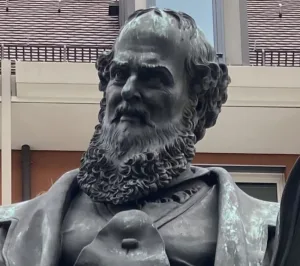
みやじま・きわみ
放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。






















