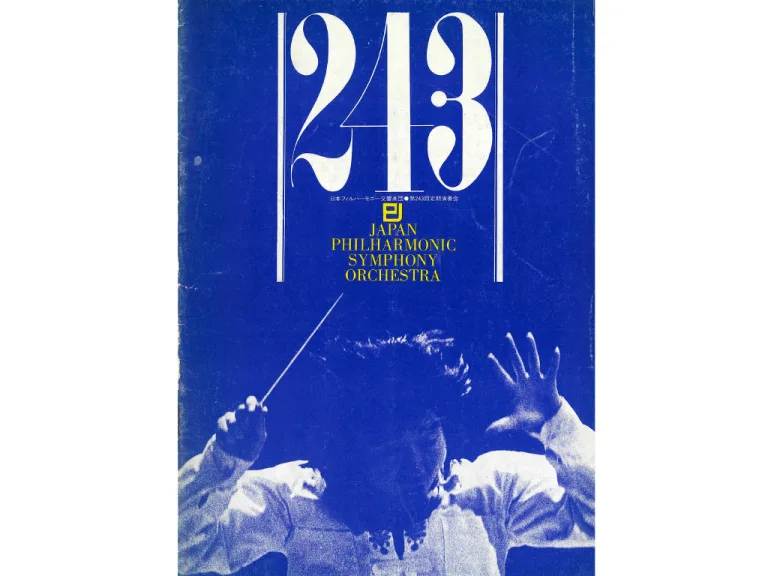激怒逆上した道化師カニオが妻とその不倫相手の男とを刺殺し、茫然と立ちつくし、「喜劇は終わりました」と告げる。だがそれは、原作のように劇中劇の観客に告げるのではなく、われわれオペラを観に来た観客に向かって告げるのだ。そしてみずからは降りてきた幕の前面に佇立(ちょりつ)して観客を見つめ、オーケストラが激しく劇的に終わったあとでもそれがしばらく場内沈黙の中に何秒か続く。その「間(ま)」のあと、おもむろに暗転する。そこで拍手が起きる。——これは、1月下旬にびわ湖ホールで上演された中村敬一演出によるレオンカヴァッロの「道化師」のラストシーンだ。
幕切れの瞬間にこの「間を採る」手法が、今日の演劇での演出では多いのだとか、そしてオペラでもそういう演出がだんだん流行りになってきたとか、だれかが教えてくれた。余韻を味わおう、考える瞬間をあたえよう、ということなのか?
セリフのみによる演劇の場合は、その「間」も、確かに効果的に違いない。が、音楽のあるオペラの場合、「オテロ」第4幕の幕切れのように、あるいは「トリスタンとイゾルデ」第3幕の大詰めのように最弱奏で終わるものはともかく、最強奏で音楽が終わっているにもかかわらず、そのまましばらく舞台が見える中で静寂が続くのは——まあ、ものにもよるけれど——何か「間が抜けた」ものに感じられてしまう。私のような「旧世代」の観客は、オーケストラが勢いよくダダダダンと終わると、ついそのテンポに乗って感覚と身体が反応し、同じテンポでの休止符(?)を挟んで拍手を始めたくなってしまうのである。音楽が勢いよく終われば、それにつられて勢いよく反応したくなるのが人情というものではなかろうか。たとえて言うなら、「オテロ」の第3幕の最後、「エレクトラ」の幕切れのような個所……。
それに関連して思い出すのは、「余韻をお楽しみいただくために、拍手やブラヴォーは指揮者のタクトが下りてからにお願いします」という、一部のオーケストラの演奏会で繰り返されるあのアナウンスだ。これがフライングの拍手やブラヴォーを防止するための策であることはもちろん承知しているのだが……。
指揮者によっては、もうそろそろいいんじゃないの、とこちらが待ちくたびれるくらい、指揮棒を高く上げたまま、なかなか下ろさない人もいる。みずから余韻に陶酔しているのか、それとも意図的に、まだ拍手をするなと指示しているのか。この「ま」が、すこぶるしらけるのである。
演奏家にとっては、演奏の終わった瞬間が完結の時なのだろうが、聴衆がそれを聴くという公開の演奏会においては、それを共有した聴衆の反応もまた音楽の演奏のうちなのである。とすれば、演奏された音楽のテンポをそのまま引き継いで称賛と感動と熱狂を表わす方がむしろ音楽的だと思われるのだが、どうなのだろう。もっとも、その「感動」は余韻を味わうことにあると主張し、どんなに「ま」が空こうと、その表現意志が減衰することはないのだ、という人たちもいるだろうが——。
まあ、いずれにせよ、その一部のオーケストラの演奏会における場内アナウンスのように、マナーについてあまりがみがみ言われると、そんなことはあまり強制されたくないな、とそろそろ思い始めたこのごろなのである。汚い声でのブラヴォーや絶叫や、音楽のテンポと合わないような慌ただしく騒々しい拍手を先んじて発するお客がいたら、その人は音楽的センスの皆無な御仁なのだと軽蔑し、改心せよ、と念じて済ませてしまおう、と思うようになってしまったのが最近の私の心境なのである。

とうじょう・ひろお
早稲田大学卒。1963年FM東海(のちのFM東京)に入社、「TDKオリジナル・コンサート」「新日フィル・コンサート」など同社のクラシック番組の制作を手掛ける。1975年度文化庁芸術祭ラジオ音楽部門大賞受賞番組(武満徹作曲「カトレーン」)制作。現在はフリーの評論家として新聞・雑誌等に寄稿している。著書・共著に「朝比奈隆ベートーヴェンの交響曲を語る」(中公新書)、「伝説のクラシック・ライヴ」(TOKYO FM出版)他。ブログ「東条碩夫のコンサート日記」 公開中。