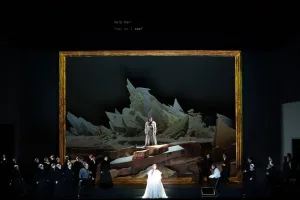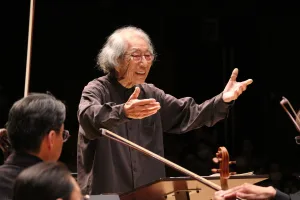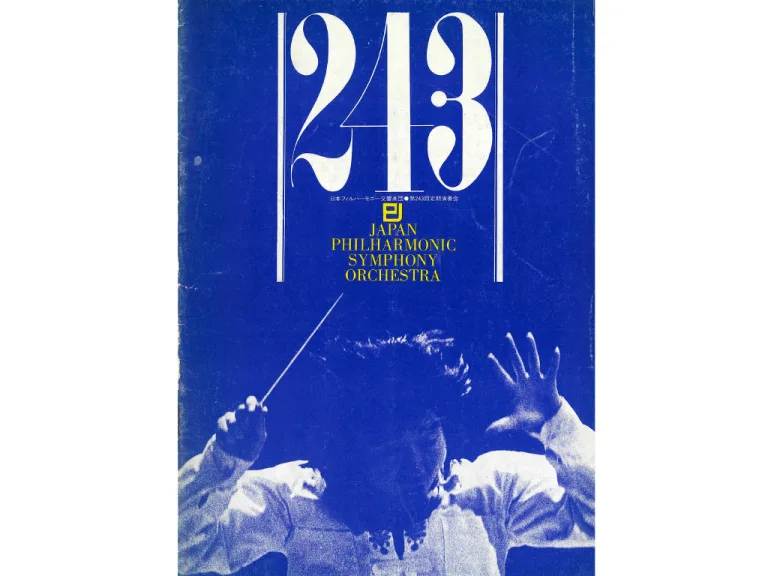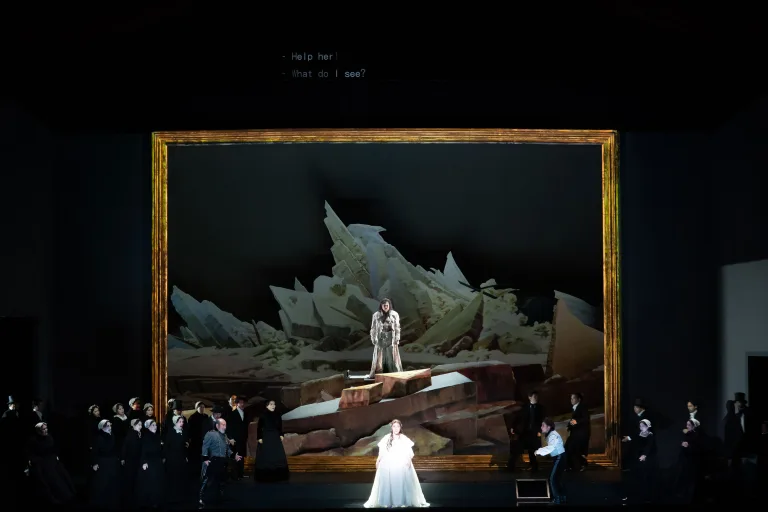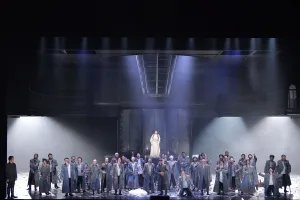オペラの上演に字幕が使われるようになってから、もうずいぶん時が経った。あれは本当に便利で、ありがたいものだ。字幕のおかげで、原語上演が気楽に見られるようになったし、不完全な邦訳使用の上演に出逢うこともなくなった。
いい字幕は、演奏や演出と同等の力を発揮するものだ。ここでいう「いい字幕」とは、言葉の使い方が適切で、原文のニュアンスをきっちりと生かし、音楽とドラマの進行とよく合い、演奏と演出のニュアンスをさらに強めて見せるものをさす。だがこれは、随分難しい作業には違いなく、つくる人は大変だろうといつも思う。
たとえば、モーツァルトの「フィガロの結婚」第2幕で、伯爵とフィガロが丁々発止の応酬をする場面がある。窓から飛び降りたのは誰だ、と伯爵が追及するくだりで、「ではお前が?」「さようで」「何故だ?」「怖かったので」「何が怖い?」「殿が怒って……」と続く短い言葉が、まるで普通の会話をするように速いテンポで飛び交うのだが、これはどう巧くやっても字幕では追いつかないだろうから、観る方もある程度は諦めなくてはならない。
でも、一部のDVDでの字幕にあるように「ニーベルングの指環」の野生児ジークフリートが、森の中で暴れまわっている時に「私」などという丁寧な(?)言葉づかいをするのは違和感がある。小人ミーメを相手に怒鳴りまくっているジークフリートには、やはり「おれ」の方がイメージも合うだろう。
たまにあるケースだが、だれがだれに向かって言っているのだか判らないような、曖昧な文章の字幕にもお目にかかる。また、作成者はそのオペラを実際に観たことが無いんじゃないか、と思わせるような、見当違いの表現の邦訳にぶつかることがある。あるいは「配慮」し過ぎて意味不明のものもある——ある劇場でヴェルディの「ナブッコ」が上演された際、バビロニアの王ナブッコが逆上して「イスラエル人どもを処刑せよ!」と怒号する原文の歌詞を、国際問題を考慮して不穏当な表現を避けるため「人びとを処刑せよ!」という字幕にしていたことがある。配慮は結構だが、言葉の選択がおかしい。「奴らを処刑せよ」ならともかく。
だが、巧い訳だなと感心させられる例も少なくない。ウィーン国立歌劇場の「ホヴァーンシチナ」がレーザーディスクで出た時に、一柳富美子さんがつけた字幕など、その好例であろう。あの中で、ニコライ・ギャウロフ演じる銃兵隊長官ホヴァンスキーや、パータ・ブルチュラーゼ演じる分離派教徒の長ドシフェイらが大口論をするシーンがある。ムソルグスキーの音楽も、アバドの指揮も凄い迫力だったが、それに乗って「貴公の銃兵隊はどうなのじゃ……家庭も顧みず、野獣と化しておる」「そうかもしれん。だがわしの責任ではないぞ。酒を飲み過ぎたせいじゃろう」「その間、貴公は何をしていたのだ。痴呆のように見とれていただけか」といった言葉がやり取りされるのだ。ふだんは使わぬような大時代がかった訳文だが、実際にその映像を観ると、歌手たちが並外れた威厳と風格を備えていて、実に物々しい大仰な場面であるだけに、この文体が実にピタリとはまっているのである。演奏と舞台に即した字幕とは、このようなものを謂(い)うのだろう。
一柳さんのロシアオペラの字幕は、これに限らず、雰囲気充分で面白い。かつてフェドセーエフの指揮で、チャイコフスキーの「イオランタ」が演奏会型式により上演されたことがあるが、その時の「おれは帰るぞ。じゃあな」という訳文など、机上で考えていればまず浮かばぬ言葉だが、音楽と演奏を聴いて、その場の人物の動きを見ていると、まさにその情景に合ったものだと感じられるのだ。
私が感心したのはもう一人、大橋マリさんの字幕だ。2019年に兵庫県立芸術文化センターでバーンスタインの「オン・ザ・タウン」が上演された際、猛烈なスピードで飛び交う英語のセリフにもかかわらず、客席の笑いが絶えなかったのは、ひとえに彼女の解り易い自然な言葉による字幕のおかげだろう。登場人物の女性たちがピトキン判事の冷酷さに呆れ、激怒して浴びせる罵声「a-ha!」に、「あ、そういうこと!」という捨てゼリフ的な訳を充てたあたり、秀逸なセンスであった。大橋さんはほかにも、モーツァルトの「イドメネオ」につけた字幕で、直訳すれば(虐げられた者たちの支えに)「この父より、今のお前自身より、価値ある支えになることから始めるのだ」(小瀬村幸子訳、キングレコードLP)となる原文を、「父をもおのれをも超えて行け」という表現でまとめていた。それが父イドメネオの、自分が犯した失敗を悔いつつ、涙を抑えて息子へ贈る告別の言葉だけに、実際の上演ではいっそうジンと心を打ったのである。

とうじょう・ひろお
早稲田大学卒。1963年FM東海(のちのFM東京)に入社、「TDKオリジナル・コンサート」「新日フィル・コンサート」など同社のクラシック番組の制作を手掛ける。1975年度文化庁芸術祭ラジオ音楽部門大賞受賞番組(武満徹作曲「カトレーン」)制作。現在はフリーの評論家として新聞・雑誌等に寄稿している。著書・共著に「朝比奈隆ベートーヴェンの交響曲を語る」(中公新書)、「伝説のクラシック・ライヴ」(TOKYO FM出版)他。ブログ「東条碩夫のコンサート日記」 公開中。