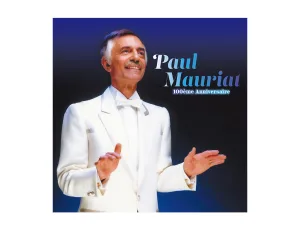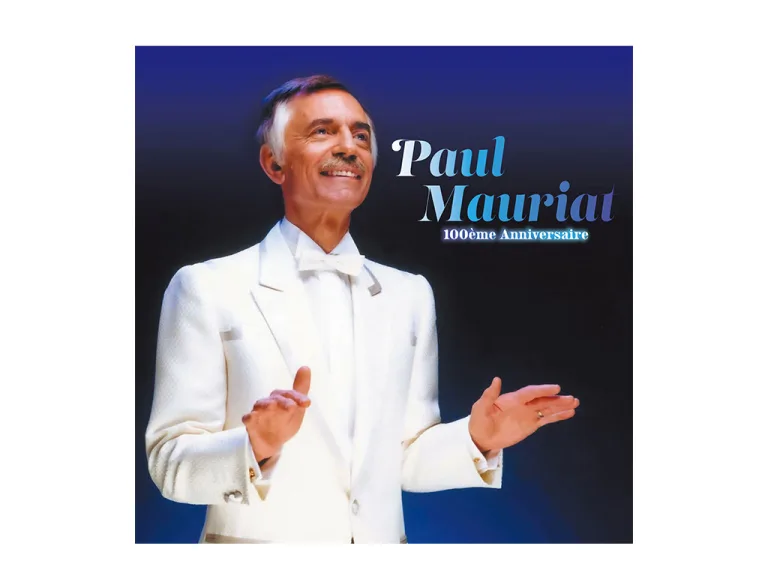この11月、ジョナサン・ノットが東京交響楽団の音楽監督としての最後の定期演奏会を指揮した。任期は来年3月までであるが、あと残すは、年末のベートーヴェンの「第九」とジルベスターコンサートのみである。ノットは、2014年4月から12シーズン、東京交響楽団の音楽監督を務めた。
この12シーズンでのこのコンビが取り上げた作品には、マーラーの交響曲全曲、ベートーヴェンの交響曲全曲、ブラームスの交響曲全曲、ブルックナーの交響曲第1、2、3、4、5、7、8、9番、ショスタコーヴィチの交響曲第4、5、10、15番、合唱を伴う作品として、バッハ「マタイ受難曲」、シェーンベルク「グレの歌」、エルガー「ゲロンティアスの夢」、ブリテン「戦争レクイエム」、リゲティの「レクイエム」、オペラとしては、モーツァルトの「フィガロの結婚」、「ドン・ジョヴァンニ」、「コジ・ファン・トゥッテ」、R・シュトラウスの「サロメ」、「エレクトラ」、「ばらの騎士」、ラヴェル「子どもと魔法」などがあげられる。このレパートリーを見るだけで、ノット&東響の充実ぶりと彼らがどんな時代を築いていたかが思い出される。
一方、この9月に東京都交響楽団の2026年度からの指揮者体制が発表され、大野和士が2026年3月の任期満了をもって都響の音楽監督を退任することが告げられた。来年度以降も、芸術顧問や桂冠指揮者としての関係は続くものの、2015年から続いた大野監督の時代も2026年3月で終了する。
大野&都響の11シーズンでまず思い出されるのは、2020年春のコロナ禍で音楽界の活動がすべて停止されていた状況のなかで、早くも2020年6月に大野のリーダーシップで「演奏会再開に備えた試演」が行われたことである。このときほど、大野が音楽監督を務めていることを心強く思ったことはない。

主な演奏曲目としては、マーラーの交響曲第1、2、3、4、5、7番、ブルックナーの交響曲第3、6、7、9番、ベルリオーズ「レクイエム」、劇的交響曲「ロメオとジュリエット」、ツェムリンスキー「人魚姫」、「抒情交響曲」、シェーンベルク「グレの歌」、ショスタコーヴィチの交響曲第5、10、15番などがあげられるが、東京フィルハーモニー交響楽団の常任指揮者時代のオペラコンチェルタンテ・シリーズでのチャレンジングな選曲を思えば、もっといろいろ手掛けてほしかった。聴き手の勝手な印象からすれば、やはり何かのチクルス(全曲演奏)をしないと、コンビとしての時代が記憶として残りにくい。
一方、オペラでは、大野&都響は、新国立劇場のピットで、西村朗「紫苑物語」、ワーグナー「ニュルンベルクのマイスタージンガー」、ムソルグスキー「ボリス・ゴドゥノフ」、ワーグナー「トリスタンとイゾルデ」、ベルク「ヴォツェック」など新制作を中心に同劇場の重要なレパートリーを手掛け、サントリーホールでベンジャミン「リトゥン・オン・スキン」を日本初演するなど、目覚ましい演奏を繰り広げた。
幸い、大野和士の新国立劇場のオペラ芸術監督としての任期は2030年まで延長されている。名作からレアな作品、日本人作曲家の新作まで、まだまだ大野の指揮で聴きたいオペラは数多くある。

やまだ・はるお
音楽評論家。1964年、京都市生まれ。87年、慶応義塾大学経済学部卒業。90年から音楽に関する執筆を行っている。著書に、小澤征爾の評伝である「音楽の旅人」「トスカニーニ」「いまどきのクラシック音楽の愉しみ方」、編著書に「オペラガイド130選」「戦後のオペラ」「バロック・オペラ」などがある。