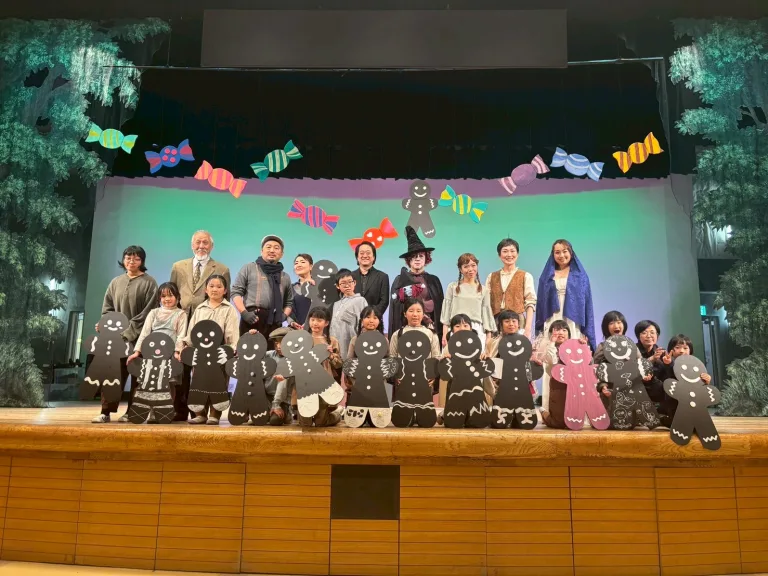20世紀音楽の諸相が耳を楽しませるコンサート
10月の新日本フィル定期は、人気作曲家・久石譲の指揮。フィリップ・グラスのヴァイオリン協奏曲第2番「アメリカン・フォー・シーズンズ」(独奏:ロバート・マクダフィー)とストラヴィンスキーの「火の鳥」組曲(1945年版)が披露された。
本公演は当初、後半にジョン・アダムズの「シティ・ノワール」が置かれた久石色全開のプログラムだった。従ってこの変更は実に残念。しかし「火の鳥」組曲が、主流の1919年版ではなく、より精妙な曲が多い1945年版である点で、作曲家の視点による清新な音楽への興味が増すことともなった。

「アメリカン・フォー・シーズンズ」のソリスト・マクダフィーは、同曲を委嘱&初演した上に、世界中で100回以上演奏している奏者。演奏にも「作品を手の内に入れた」自信が反映されており、楽章の合間に置かれた無伴奏部分をはじめ、グァルネリ・デル・ジェスの強靭な音色を生かした濃密なソロ(彼のアンコール2曲目の無伴奏曲は特にそう)を繰り広げた。ただし曲全体が「温和」ないし「穏和」な表現(1階11列下手寄りではそう聴こえた)で、楽章によるテイストの差異が少なく、どの楽章がどの季節なのかの解釈が聴き手に委ねられた曲の1つの妙味を実感し難かった印象も受けた。

「火の鳥」の1945年版は、1919年版の最初の3曲と「ロンド」の間に3つの「パントマイム」と「パ・ド・ドゥ」「スケルツォ」の2曲が挟まれている点、及び終曲最後の主題の繰り返しが短く切られている点が特徴。今回はこの特徴が〝特長〟に転化された。前者には特に力点が置かれ、1919年版にない部分の多様な音の綾が生き生きと伝えられたし、後者はテンポを通常より速めることで短い音の意味がナチュラルに明示された。曲全体は精緻で生彩に富んだ演奏。ホルンやオーボエなど各パートのソロも秀逸で、新日本フィルの機能性向上も顕著に示された。

アンコールのマルケス「ダンソン第2番」も、ありがちな「ノリだけ」の表現ではなく、多彩な状況変化を明確に表出した好演。同曲を含めて、20世紀音楽の諸相が耳を楽しませるコンサートとなった。
(柴田克彦)
公演データ
新日本フィルハーモニー交響楽団 第666回定期演奏会 サントリホール・シリーズ
10月13日(月・祝)14:00サントリーホール 大ホール
指揮:久石譲
ヴァイオリン:ロバート・マクダフィー
管弦楽:新日本フィルハーモニー交響楽団
コンサートマスター:西江辰郎
プログラム
フィリップ・グラス:ヴァイオリン協奏曲第2番「アメリカン・フォー・シーズンズ」
ストラヴィンスキー:バレエ音楽「火の鳥」組曲(1945年版)
ソリスト・アンコール
ヴィヴァルディ:「四季」より〝夏〟第3楽章
ジェイ・アンガー:アショカン・フェアウエル
アンコール
マルケス:ダンソン・ヌメロ・ドス(Danzón no.2)

しばた・かつひこ
音楽マネジメント勤務を経て、フリーの音楽ライター、評論家、編集者となる。「ぶらあぼ」「ぴあクラシック」「音楽の友」「モーストリー・クラシック」等の雑誌、「毎日新聞クラシックナビ」等のWeb媒体、公演プログラム、CDブックレットへの寄稿、プログラムや冊子の編集、講演や講座など、クラシック音楽をフィールドに幅広く活動。アーティストへのインタビューも多数行っている。著書に「山本直純と小澤征爾」(朝日新書)。