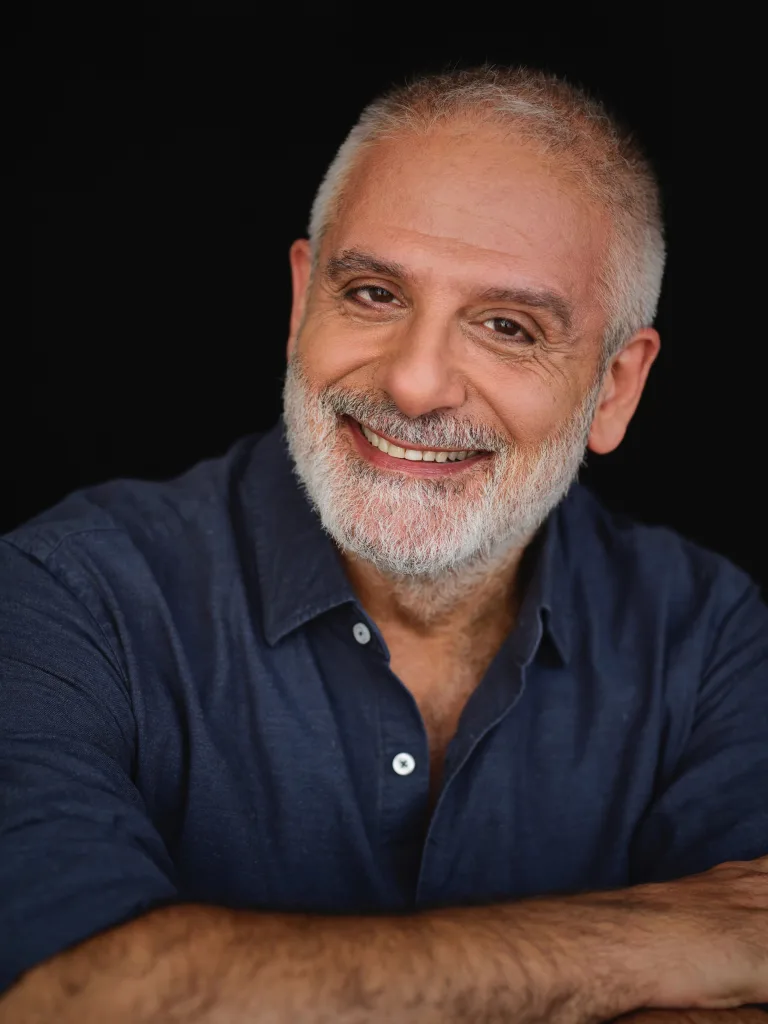
エレガントに響く美声を自然に駆使して
喜劇を圧倒的な高みに導く
プッチーニ「ジャンニ・スキッキ」は日本でもそれなりに上演されるが、終演後、満足感に浸って帰宅するのは難しい。題名役が低声をエレガントに響かせつつ、セリフを細やかに回す、という課題に応えられないからである。だが、稀に応える歌手を得ると、作品の奥義(おうぎ)に触れた気にさせられる。ピエトロ・スパニョーリが題名役を歌った2025年2月の新国立劇場の公演がそうだった。
朗々たる声を無理なく響かせ、会話のリズムそのもののような快活かつ精緻な歌唱をそこにつなぐ。母語であるイタリア語の美しさはいうまでもない。こういう歌唱はいくつもの才が重ならないと成り立たず、とりわけイタリア語のリズム感と対極にある日本語の話者には難しい。
とくにスパニョーリは、香り立つような美声で、お手本のような艶のあるレガートを表現できるから、それとの対比でセリフ回しがいっそう映える。自然な響きが生まれているからだろう、死んだブオーゾを真似た声色まで美しい。
喜劇的な役を得意とする低声をバッソ・ブッフォと呼ぶ。会話のテンポや抑揚を模倣したパルランド唱法を交え、種々の感情をコミカルに表すが、表現が大げさになると興醒めさせられる。安定した発声で自然に言葉を回し、感情の質や強弱は声に載せるニュアンスや色彩で描写してこそで、それができるスパニョーリはバリトンだが、この分野の第一人者になった。

フォードとファルスタッフの自然な歌い分け
2018年8月、ペーザロのロッシーニ・オペラ・フェスティバル(ROF)で「セビリャの理髪師」のドン・バルトロを歌い、巧みなパルランド唱法でドラマを牽引した。私はそれまで、バルトロという役はアクが強い声で歌われたほうが、滑稽な味わいが深くなると思い込んでいたが、スパニョーリが歌うのを聴いて考えを改めた。
このときはもう一人の低声、バッソ・プロフォンド(深いバス)の役であるドン・バジーリオをミケーレ・ペルトゥージが歌ったが、こうしてともに美声であるほうが音楽としてまとまると実感した。スパニョーリはベルカント・オペラならではの旋律美を表現でき、装飾歌唱も巧みで、そこに喜劇的な味わいを加えるからこそ映えるのだと。
それから6年を経た2024年8月、ROFで開催されたスパニョーリのリサイタルには驚かされた。冒頭のパイジェッロとベッリーニの歌曲から、旋律に載せられた言葉がぐいぐいと迫る。続いて「ラ・チェネレントラ」のドン・マニフィコや「イタリアのトルコ人」のドン・ジェローニオになると、水を得た魚のような圧倒的な表現力で、その役の人間性や味わいが深奥(しんおう)から湧き上がるのだが、そうした表現は美声で歌われるベッリーニの歌曲の延長上にあると気づかされた。特別なことはしていない。すべては美しい声を響かせる盤石のテクニックとともにあった。
このとき「ファルスタッフ」の題名役とフォードを歌い分けたのも象徴的だった。より真っ直ぐな性格のフォード役には流麗なレガートも求められ、実際、スパニョーリの表現は演劇的かつエレガントである。一方、題名役のほうが逐語的な表現が中心なうえに複雑な役だが、同じ発声にアクセントやニュアンスを加えると、見事にファルスタッフになる。本物のバッソ・ブッフォとはそういうものかと感じ入った。

かはら・とし
音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。






















