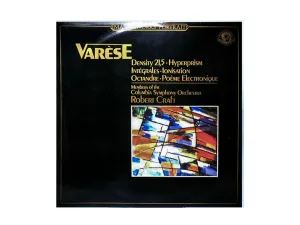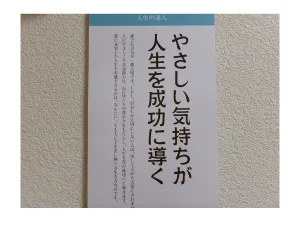小遣いをためて買ったチケットを大切に握りしめ、日比谷公会堂へ聴きに行った初めての東京交響楽団の演奏は、上田仁指揮でのチャイコフスキーの「悲愴交響曲」、ピアノ協奏曲第1番(ソリストは井口基成)、「胡桃割人形」組曲だった。その1955年1月4日の日記には、「練習不足なのだろうが、トランペットがしばしば突拍子もない音を出すのでヒヤヒヤした」と生意気な感想が書いてある。でもまあ、当時の日本のオケの生演奏は、大なり小なり、そういうことが日常茶飯事だった。それでも、当時は、みんな聴きに行ったのである。外来オケなどあり得なかった時代だ。日比谷公会堂の客席はぎっしり、両側通路さえ立ち見客で埋まっていたこともしばしばだった。みんな「熱かった」のだ。
東京交響楽団は、特に1950年代半ば頃、東京放送(ラジオ東京、現TBS)専属のオーケストラとして、日曜日の朝10時半からの30分番組にレギュラー出演していたので、私たちにもなじみの深い楽団だった(東宝映画「ゴジラ」のサントラの音楽を演奏していたのが、元東宝交響楽団の東京響だったことまでは知らなかったが)。その番組では、上田仁の指揮で、「新世界」や「運命」などを、なんと30分で演奏していた。どこかの楽章をカットするとかいうのではなく、ちゃんと初めから終わりまでやるのである。つまり、細部をあちこちカットして――ソナタ形式なら展開部をカットしてつなぐ、という手法だ。われわれファンには、しかし、とにかく貴重な時間だった。

特に1950年代末になってからは、東京響の定期は、われわれ若者連の間でも急激に人気を高めていた。アルヴィド・ヤンソンス(マリスの父君)が客演して目の覚めるような素晴らしい演奏を聴かせてくれたのがきっかけだったろう。「ヤンソンスは東響を鉛から金に変えた」という辛口の評論家・山根銀二の評も有名になったが、これは常任指揮者の上田仁にとっては随分侮辱的に感じられただろう。だが、とにかくそれは事実ではあった。
以降、東京響の快進撃は続く。1960年3月にオイゲン・ヨッフムが客演指揮したブラームスの交響曲第1番は、今なお記憶に残る感動的な演奏だった。また、ヴァーツラフ・スメターチェクが客演指揮したドヴォルザークの「第8交響曲」などもまさにエキサイティングな演奏で、2階席からはブラヴォーも飛び、「次の定期も期待するぞ!」などという絶叫も聞こえるなど、すごい盛り上がりを示した。オケの演奏水準も高かっただろうと思う。だれの指揮の時だったか、ブラームスの「第4交響曲」第4楽章の木下芳丸による長いフルート・ソロの素晴らしさが話題を集めたこともある。その他、パブロ・カザルスが客演指揮したのも東京響だった――その時は、私はTVで見ただけだったが、ベートーヴェンの「第4交響曲」で、それまで椅子に座って指揮していた彼が、第1楽章再現部直前の箇所でぱっと立ち上がり、それにつれて東京響がすさまじいクレッシェンドで再現部に突入したのを、震えるような感動とともに見つめ、聴いていたことを思い出す。
それほど素晴らしかった東京交響楽団が、1964年3月26日に突然解散を発表したことは、業界のみならず、われわれファンにとっても大きな衝撃であった。それは東京放送が専属契約を打ち切ったことで運営が成り立たなくなったためだが、ある雑誌は「個性を発揮し、若い聴衆に支持され……楽員の給料も他に比して最高と誇っていた東響が、何故このようにもろくも崩れ去ったのか」と嘆いた。3月31日、楽員たちが自主運営の楽団を結成して再発足し、危機を乗り越えたかと見えたが、4月9日には橋本楽団長が経営責任を感じて入水自殺するという悲劇も起こる。その苦難の中、再出発した東京響を獅子奮迅の勢いでけん引したのは、デビューして間もなかった弱冠23歳の指揮者・秋山和慶(のち1968年より音楽監督)だった。今日の東京交響楽団の隆盛への道は、こうして開かれていったのである。


とうじょう・ひろお
早稲田大学卒。1963年FM東海(のちのFM東京)に入社、「TDKオリジナル・コンサート」「新日フィル・コンサート」など同社のクラシック番組の制作を手掛ける。1975年度文化庁芸術祭ラジオ音楽部門大賞受賞番組(武満徹作曲「カトレーン」)制作。現在はフリーの評論家として新聞・雑誌等に寄稿している。著書・共著に「朝比奈隆ベートーヴェンの交響曲を語る」(中公新書)、「伝説のクラシック・ライヴ」(TOKYO FM出版)他。ブログ「東条碩夫のコンサート日記」 公開中。