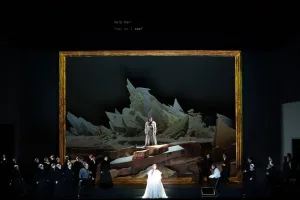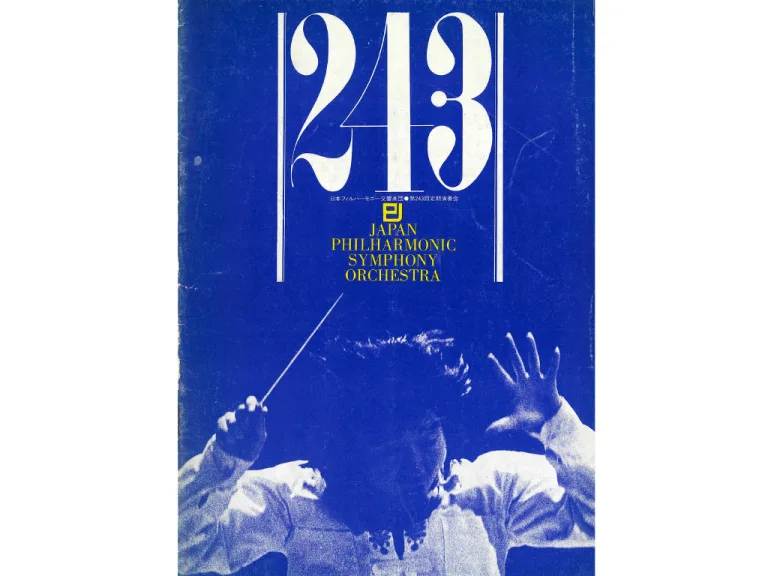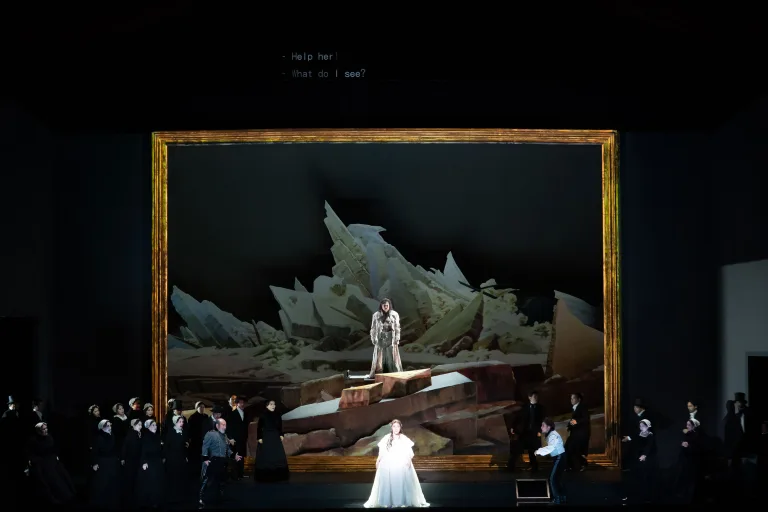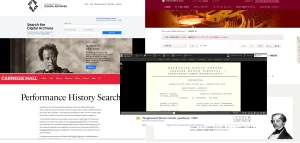「オーケストラをつくるのは難しいです……でも、それと比較にならんくらい難しいのは、それをずっと維持することです」
昔、何かの話のさなかに、朝比奈隆氏がそう語ってくれたことがある。この発言には、戦後、関西交響楽団を設立し、のちにそれを大阪フィルハーモニー交響楽団として存続させることに腐心した朝比奈氏ならではの重みがある。
事実、東京においても、私たちはオーケストラの苦難の歴史をいくつか見てきた——東京交響団は1964年、TBSから専属契約を打ち切られて財団法人が解散、楽団長が責任感から自ら命を絶つという大危機を体験した。また東京都交響楽団は1965年の結成直後、東京都議会選挙で第一党となった社会党と、同じく議席を伸ばした共産党とにより「無駄使いの対象」とされ、一時は小規模な「教育オーケストラ」に縮小させられたことがある。さらに1972年、日本フィルハーモニー交響楽団がフジテレビ・文化放送から専属契約を打ち切られて財団法人解散の憂き目に遭い、分裂したという歴史は、今でも折々、人々の口の端に上る出来事である。
音楽活動の盛んな首都東京においてさえこうだから、ましてやプロ・オーケストラの土壌など皆無だった東北の一都市、山形において、1972年1月に「東北初のオーケストラ」を旗揚げした村川千秋氏が、以降どれほどの苦難を体験したか、想像に余りある。本拠地山形での第1回定期演奏会(同年9月28日)は、音楽監督兼常任指揮者の彼の指揮でベートーヴェン・プロ(「エグモント」序曲、ピアノ協奏曲第3番、交響曲第5番「運命」)を演奏したが、この時の編成は40人、大半がエキストラだったという。「資金難、団員のなり手がない、というアキレス腱をかかえての船出」(山形交響楽協会編「無から有へ 山形交響楽団40年史」16頁)だった。
その後も「経営難、団員不足」という壁や、文化庁の求める「10型弦と2管、55人編成」を達成不可能ゆえに国の補助金の全額受給を断念せざるを得なかったという事態、あるいは宮城フィル(現・仙台フィル)への楽員の流出など、胸の痛むような出来事も絶え間なく続いたという。が、それらを乗り越えて山響の今日の隆盛への道を開いたこと、そして周辺に「山響の灯を消すな」という運動を巻き起こさせるその牽引力となったのは、ほかならぬ村川千秋氏のひたむきな姿勢だったのは明らかであろう。
1933年、山形県村山市に生れ、東京藝大や米国のインディアナ大学院に学び、帰国後に東京交響楽団で指揮デビューした村川氏の「故郷の街にプロ・オーケストラを」という理想——それは、その後黒岩英臣(現・名誉指揮者)、飯森範親(現・桂冠指揮者)、阪哲朗(現・常任指揮者)らの歴代シェフたちに引き継がれ、今やついに不動のものとなった。

村川千秋氏が6月25日に92歳で帰天したそのわずか1週間前、山響はオッコ・カムの指揮で、東京と大阪でシベリウスのヴァイオリン協奏曲と第2交響曲を演奏していた。またさらにその10日ほど前には、本拠地の山形市で、シベリウスの「レンミンカイネン」組曲を演奏していた。
特に「レンミンカイネン」は、山響がついにこのようなシベリウスを聴かせるオーケストラに成長したかと感銘を受けるほど、威厳に満ち、しかも神秘的な深さを持った超名演奏だった。シベリウスの作品は、村川氏がライフワークとして取り組み、しばしば山響と演奏したものでもある。氏がもしこの演奏を聴いたら、どんなに喜びに浸られたことであろう……。

とうじょう・ひろお
早稲田大学卒。1963年FM東海(のちのFM東京)に入社、「TDKオリジナル・コンサート」「新日フィル・コンサート」など同社のクラシック番組の制作を手掛ける。1975年度文化庁芸術祭ラジオ音楽部門大賞受賞番組(武満徹作曲「カトレーン」)制作。現在はフリーの評論家として新聞・雑誌等に寄稿している。著書・共著に「朝比奈隆ベートーヴェンの交響曲を語る」(中公新書)、「伝説のクラシック・ライヴ」(TOKYO FM出版)他。ブログ「東条碩夫のコンサート日記」 公開中。