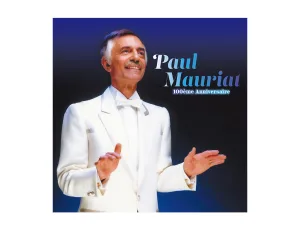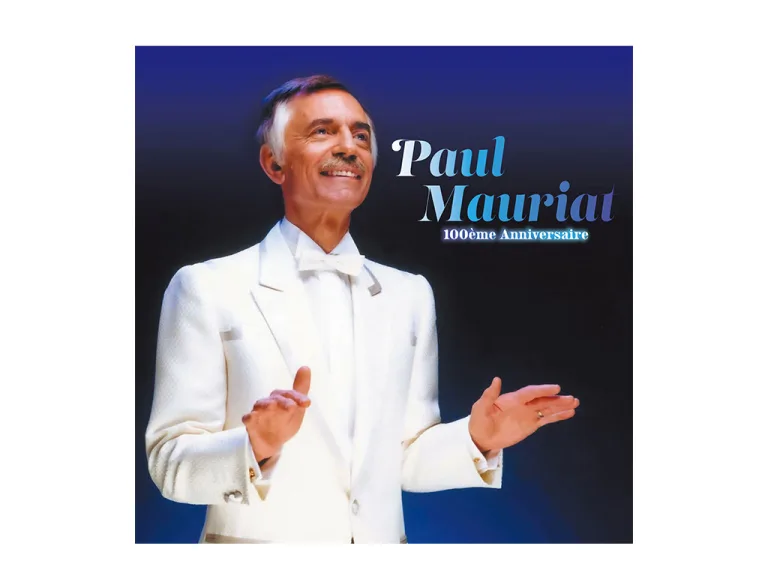オーケストラの世界で「バンダ」といえば、舞台上のオーケストラとは離れた場所(舞台裏や客席・通路)で演奏する別働隊のアンサンブルのことを指す。イタリア語の「バンダ」は、英語でいえば「バンド」つまり「楽隊」のことである。
もともとは、モーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」でのパーティのバンドやベートーヴェンの「フィデリオ」での到着ラッパ(複数人のバンドではなくソロだが)のような、ピットのオーケストラとは別に、オペラの舞台でリアルな音響効果を果たす役割として用いられた。その後、「ドン・ジョヴァンニ」の晩餐会での楽隊は、ヴェルディの「仮面舞踏会」での舞踏会の楽団やベルクの「ヴォツェック」での酒場のバンドに受け継がれていく。プッチーニの「ラ・ボエーム」第2幕最後の鼓笛隊の行進もとても印象的である。トランペットのファンファーレは、ヴェルディの「アイーダ」や「オテロ」、ワーグナーの「タンホイザー」などでも使われている。
また、ベートーヴェンが「フィデリオ」の到着ラッパを「レオノーレ」序曲第3番でも用い、管弦楽曲の世界でもバンダが使われるようになる。後に、マーラーは、交響曲第1番「巨人」の第1楽章で舞台裏のトランペットのファンファーレを用い、交響曲第3番第3楽章では場外でポストホルンを吹かせた。ベルリオーズは、「幻想交響曲」の第3楽章「野の風景」で、舞台裏のオーボエと舞台上のコールアングレを呼応させたが、舞台とバンダの応答では、後にマーラーの交響曲第2番「復活」第5楽章でより大規模なもの(舞台上のフルート、ピッコロと、舞台裏のホルン、4本トランペット、ティンパニ)がみられることになる。
そのほか、通常のオーケストラによりパワーを加えるために、別働の金管部隊が加わることもある。その代表的な例としては、マーラーの交響曲第8番、レスピーギの交響詩「ローマの松」及び「ローマの祭」、ショスタコーヴィチの「祝典序曲」などがあげられるだろう。ショスタコーヴィチの交響曲第7番「レニングラード」でも第2群のブラスが加わる。巨大なバンダでは、ヤナーチェクの「シンフォニエッタ」(トランペット9本、バス・トランペット2本、テナー・チューバ2本)やR・シュトラウスの「アルプス交響曲」(ホルン12本、トランペット2本、トロンボーン2本)があげられる。最大規模のバンダは、ベルリオーズのレクイエムではないだろうか。4組のバンダ(それぞれ8~12名の金管アンサンブル)が4方に配置されて咆哮し、それに舞台上の8対のティンパニ群が呼応し、10対のシンバルも加わる。
作曲家たちは、バンダを、単なる音量や遠近感の問題ではなく、音響空間をどう扱うかを意識して、用いたに違いない。だから、バンダの効果は、CDや音源よりも、コンサートホールや劇場で体験したい。指揮者にとって、バンダをどう扱うか(どの場所で演奏されるか)は、音響空間へのセンスが問われる課題といえる。

やまだ・はるお
音楽評論家。1964年、京都市生まれ。87年、慶応義塾大学経済学部卒業。90年から音楽に関する執筆を行っている。著書に、小澤征爾の評伝である「音楽の旅人」「トスカニーニ」「いまどきのクラシック音楽の愉しみ方」、編著書に「オペラガイド130選」「戦後のオペラ」「バロック・オペラ」などがある。