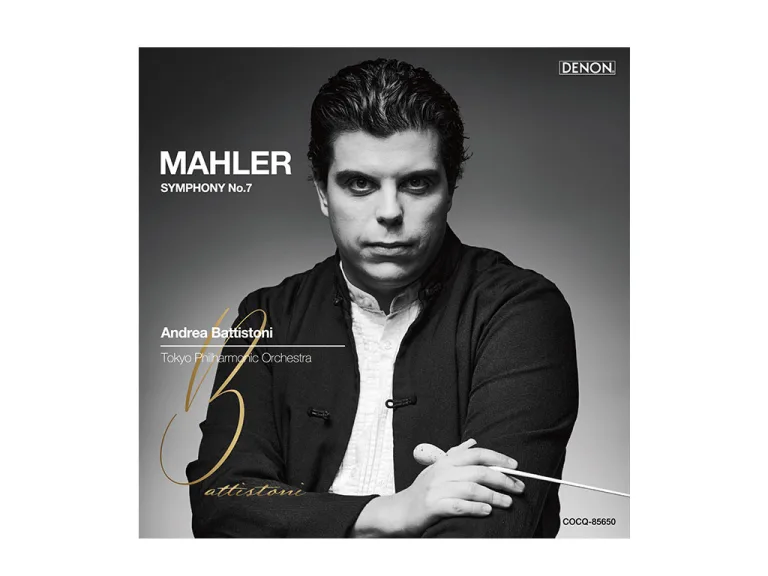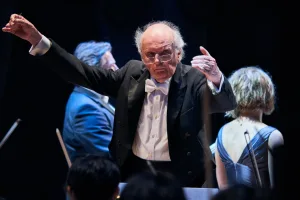〝声の演技者〟ナタリー・デセイの真髄を実感した一夜
ナタリー・デセイ(ソプラノ)&フィリップ・カサール(ピアノ)のリサイタル。今回がこの形における最後の日本公演だという。

それは、前半がモーツァルトの歌劇「フィガロの結婚」からのアリアとフランス歌曲=これまでの十八番、後半がミュージカルに通ずる英語の歌=現在〜今後の方向性を示すプログラムにも反映されている。
最初の「フィガロの結婚」は、バルバリーナ、スザンナ、ケルビーノ、伯爵夫人の女声4役の歌を1曲ずつ並べた大胆な構成。しかもデセイは、バルバリーナのカヴァティーナの出だしの旋律を歌わずに自身ピアノで奏でるという意表をつく(ある意味粋な)形でスタートした。その後は4曲を表情豊かに歌ったのだが、面白かったのは彼女のイメージから最も遠い伯爵夫人のアリア。同役の前身が「セビリャの理髪師」のロジーナであったことを想起させる可憐さが逆に新鮮だ。さらには、各曲の繋ぎや前奏にモーツァルトのピアノ作品を用いるなど、意味ありげな遊び心もあって、二人による「モーツァルト・ワールド」が耳を愉しませた。

おつぎは、ショーソン、ラヴェル、プーランクといったフランス歌曲。しかも全て「鳥」にまつわる楽曲だ。ここは透明感を湛えたモノトーンの世界。終始しっとりじっくりと歌われていく。(本日全体がそうだったが)特に感心したのは弱音の精妙なコントロール。中でもプーランク「モンテカルロの女」の最後の息を飲むようなロングトーンには心底感嘆させられた。

後半─メノッティ、バーバー、プレヴィンの作品─は、クリーミーな声によるさりげなくも格調高い歌が続き、〝声の演技者〟の面目躍如の趣。
アンコールは、アーン、メノッティ、そしてドリーブ「ラクメ」の1曲。本編同様のしっとりとした歌い回しで魅了し、最後まで一貫したトーンが維持された。
話(英語)も交えて進められたステージは、それ自体がハイセンスなエンターテインメントの如し。華麗で輝かしい歌声はもう聴けないが、〝声の演技者〟としては着実に円熟味を増している感がある。ワーグナーなどに挑戦して持ち味を失う歌手もままいる中、〝自身を知る〟デセイの行き方は賢明と言えるだろう。〝声を張り上げずして雄弁な〟歌手の真髄を実感した一夜。
(柴田 克彦)

公演データ
ナタリー・デセイ & フィリップ・カサール Farewell CONCERT
11月6日(木)19:00東京オペラシティ コンサートホール
ソプラノ:ナタリー・デセイ
ピアノ:フィリップ・カサール
プログラム
モーツァルト:歌劇「フィガロの結婚」より
〝無くしてしまったわ〟バルバリーナのカヴァティーナ
〝とうとうその瞬間が来た~さあ 早く来て〟スザンナのレチタティーヴォとアリア
〝自分で自分がわからない〟ケルビーノのアリア
〝スザンナは来ない!~ いずこぞ喜びの日〟伯爵夫人のレチタティーヴォとアリア
ショーソン:「ハチドリ」
ラヴェル:「天国の美しい3羽の鳥たち」
ベッツ:「傷ついた鳩」
プーランク:「かもめの女王」
ラヴェル:「悲しき鳥たち」(ピアノ・ソロ)
プーランク:「モンテカルロの女」
メノッティ:歌劇「霊媒」より〝モニカのワルツ〟
バーバー:「ノックスヴィル - 1915年の夏」
プレヴィン:歌劇「欲望という名の電車」より〝私が欲しいのは魔法〟ブランチのモノローグ
アンコール
アーン:リラの木のナイチンゲール
メノッティ:「泥棒とオールドミス」より〝私を盗んで、素敵な泥棒さん〟
ドリーブ:「ラクメ」より〝あなたは私に最も甘い夢を与えてくれた〟

しばた・かつひこ
音楽マネジメント勤務を経て、フリーの音楽ライター、評論家、編集者となる。「ぶらあぼ」「ぴあクラシック」「音楽の友」「モーストリー・クラシック」等の雑誌、「毎日新聞クラシックナビ」等のWeb媒体、公演プログラム、CDブックレットへの寄稿、プログラムや冊子の編集、講演や講座など、クラシック音楽をフィールドに幅広く活動。アーティストへのインタビューも多数行っている。著書に「山本直純と小澤征爾」(朝日新書)。