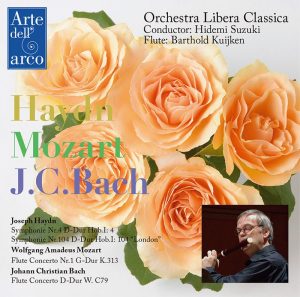明晰な快演、沼尻竜典と神奈川フィルのブルックナー8番
音楽監督に沼尻竜典を迎えて以降、神奈川フィルハーモニー管弦楽団は、その響きに骨太の度を格段に増して来ているように思われる。「みなとみらいシリーズ定期演奏会第408回で取り上げられたブルックナーの交響曲第8番ハ短調(ノヴァーク校訂による第2稿/1890)での演奏は、如実にその傾向を感じさせた。

石田泰尚をコンサートマスターとする「16型」の弦(第1ヴァイオリン16人に応じた弦編成)は厚みがあり、大編成の管楽器群と充分に呼応し、ブルックナー特有のトレモロをたっぷりと響かせた。ステージ後方下手寄りに並んだホルンおよびワーグナー・テューバ群も、それらに近接して配置されたコントラバステューバと一体化して、見事なハーモニーをつくり上げていた。ただ1カ所、第4楽章の終結部へ向かう直前の頂点で、トランペットとトロンボーンがフォルティッシモで吹く第1楽章第1主題の動機は、それが作品の構成上重要な意味を持っているだけに、もう少し明確に響いて欲しかったという気もするが。

沼尻竜典が手がけるブルックナーの交響曲は、そうしばしば聴ける機会はないけれども、予想通り明晰(めいせき)な音色と明確な輪郭を備えた、少しの曖昧さもない音楽構築によるものだった。テンポも速めで、全曲は正味77分~78分くらいだったろうか。第1楽章では凝った「矯(た)め」を避け、ストレートな力をもって、ひたすらぐいぐいと押して行く。特に印象的だったのは第3楽章の終結個所で、ホルンやワーグナー・テューバ群が静かに歌って行く主題は、その音色も表情も、あくまで明晰そのもので、ほとんど翳(かげ)りといったものを感じさせない。筆者ら旧世代(?)の聴き手たちが常にこのくだりに求めていたような、神秘的とか、彼岸的なものとか、未知の永遠への憧憬(しょうけい)とか諦念とか、そういったロマンティックな感情など、全く不要とばかりに一掃したような演奏だったというか。
もっとも、現代のブルックナー演奏には多かれ少なかれそのような傾向が聴かれることは承知しているし、マエストロ沼尻もまた現代の感性の中に生きる指揮者であることも承知している。ただし敢えて付け加えたいが、筆者と雖(いえど)も、そういうブルックナーもそれはそれで魅力的だ、と感じているのは事実なのである。

それにこの日の演奏、沼尻の演奏構築の設計も実に巧かった。第1楽章の終わり近く、弦やホルンの3連音に乗って幅広い音型がクレッシェンドを重ねて行くあたり見事な緊迫感だったし、第2楽章スケルツォでのモデラート(中庸を得た)のテンポによる主題動機の執拗(しつよう)な反復も安定した力感に満ちあふれていた。第4楽章最後の圧倒的な昂揚感は、これはもう、申し分ない。
充実した「ブル8」を聴いたという印象である。
(東条碩夫)
公演データ
神奈川フィルハーモニー管弦楽団 みなとみらいシリーズ定期演奏会第408回
10月18日(土)14:00横浜みなとみらいホール 大ホール
指揮:沼尻竜典
管弦楽:神奈川フィルハーモニー管弦楽団
コンサートマスター:石田泰尚
プログラム
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調WAB108(L.ノヴァーク版第2稿)

とうじょう・ひろお
早稲田大学卒。1963年FM東海(のちのFM東京)に入社、「TDKオリジナル・コンサート」「新日フィル・コンサート」など同社のクラシック番組の制作を手掛ける。1975年度文化庁芸術祭ラジオ音楽部門大賞受賞番組(武満徹作曲「カトレーン」)制作。現在はフリーの評論家として新聞・雑誌等に寄稿している。著書・共著に「朝比奈隆ベートーヴェンの交響曲を語る」(中公新書)、「伝説のクラシック・ライヴ」(TOKYO FM出版)他。ブログ「東条碩夫のコンサート日記」 公開中。