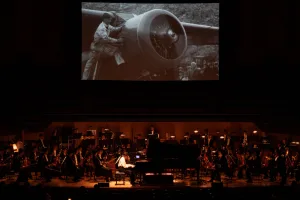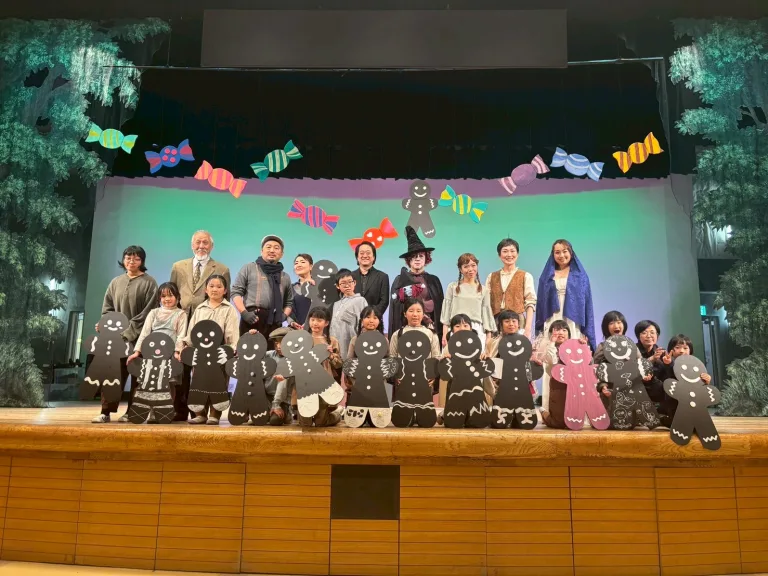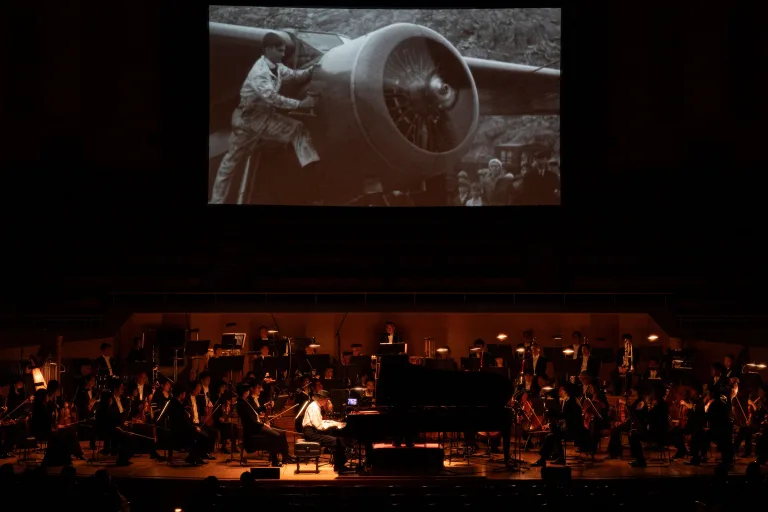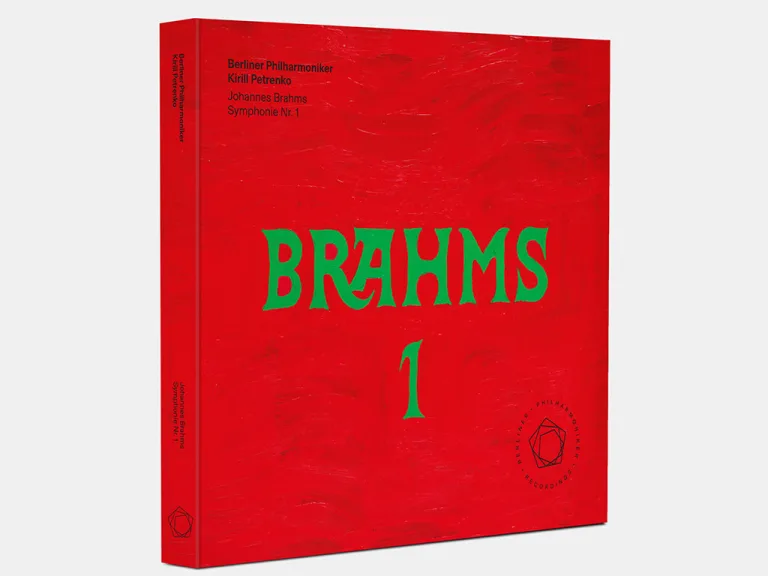ニールセンの神髄に迫る演奏
尾高体制での「大フィル」現在地を示す、充実した公演となった。
大阪フィルは、尾高忠明音楽監督のもとでベートーヴェン、ブラームス、ブルックナーなどの交響曲チクルスでレパートリーの中核を固めるとともに、様々な挑戦も行っている。
今回も「新しいレパートリーの紹介」としてデンマークの作曲家のニールセンの作品を一晩で演奏した。
ドイツでの評価が低いこともあって、日本でも演奏機会に恵まれなかったが、近年、東京を中心に演奏の機会も増え、その立役者と目されるデンマークの指揮者、トーマス・ダウスゴーが初登場に当たって、得意のニールセン作品を取り上げた。

プログラムは、作曲者がエーゲ海の日の出の感動を描いた序曲「ヘリオス」。最後の大規模作品となったクラリネット協奏曲(ウィーン・フィル首席で、大阪フィルのアーティスト・イン・レジデンスを務めるダニエル・オッテンザマーの独奏)、「不滅」の副題で比較的演奏機会の多い交響曲第4番の3曲。
ニールセンは、ヴァイオリンの楽士、軍楽隊のトランペット奏者を経験、コペンハーゲンの音楽院では、当時ドイツ音楽界の最前線で指揮者・作曲家として活躍した経験を持つゲーゼに学んだ。その後デンマーク王立劇場の楽団で、作曲家スヴェンセン指揮のもとヴァイオリン奏者を務め、その間、「ニーベルングの指環」など同時代のドイツ音楽に触れ、その後は王立管弦楽団の指揮者も務め、理論と様々な場での実践の両面を通じての経験を「心の声」として作品化した。
そのため、例えば「ヘリオス」の冒頭のホルン合奏にワーグナーやブルックナーを感じ、日の出後の躍動の場面ではエルガーなどの推進力、さらに大音量での長いユニゾンには同世代のシベリウスをなど北欧風な感情と相通じるもの、牧歌風の旋律にはブラームスやシューマンなど、過去の作品の痕跡がモティーフとして随所に感じられる。
しかし、ニールセンは取り入れたものを咀嚼(そしゃく)して、感情を込めて絶妙に組み合わされ、出てきたものは、表現の独自の境地に到達しているため譜面をなぞり、モティーフとなった作品の特徴を真の理解なくして「それらしく」演奏しても真価は引き出せない。これがニールセンの作品の決定的な演奏が出にくい原因だろう。

今回は、ブルックナーなどドイツ音楽を得意とするダウスゴーの指揮のもと、近年の大阪フィルが、従来のドイツ音楽に加えてシベリウス、エルガー、メンデルスゾーンなどのレパートリーを根付かせたこともプラスに働き、ニールセンの神髄に迫る演奏が実現した。(平末広)
公演データ
大阪フィルハーモニー交響楽団 第591回定期演奏会
9月26日 (金) 19:00フェスティバルホール(大阪)
指揮:トーマス・ダウスゴー
クラリネット:ダニエル・オッテンザマー
管弦楽:大阪フィルハーモニー交響楽団
コンサートマスター:崔 文洙
プログラム
ニールセン:序曲「ヘリオス」Op.17
ニールセン:クラリネット協奏曲 Op.57
ニールセン:交響曲 第4番「不滅」Op.29
他日公演
9月27日(土)15:00フェスティバルホール(大阪府)

ひらすえ・ひろし
音楽ジャーナリスト。神戸市生まれ。東芝EMIのクラシック担当、産経新聞社文化部記者、「モーストリー・クラシック」副編集長を経て、現在、滋賀県立びわ湖ホール・広報部。EMI、フジサンケイグループを通じて、サイモン=ラトルに関わる。キリル・ぺトレンコの日本の媒体での最初のインタビューをしたことが、ささやかな自慢。