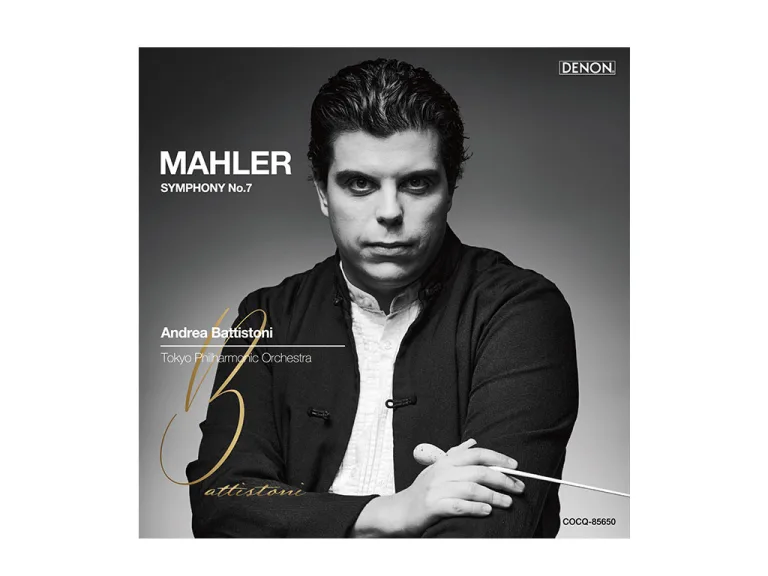若いパワーを誇示!ノセダ得意のラフマニノフで熱量の高いサウンドを築く
名門カーネギーホールが毎夏、若い世代を育成するプロジェクトがナショナル・ユースオーケストラUSA(NYO-USA)。この団体が同ホールとサントリーホール提携の一環で、初来日を果たした。指揮はワシントン・ナショナル響音楽監督やチューリッヒ歌劇場音楽総監督を務める名匠ジャナンドレア・ノセダ。
日本のパシフィック・ミュージック・フェスティバルのように、教育オーケストラ活動は世界各地で夏の恒例行事となった。2013年に始まったNYO-USAでは、全米からオーディションを経て集まった16~19歳のメンバーが、米〝ビッグ5〟などのプロから指導を受け、成果をカーネギーホールで披露する。各国の音楽祭などへの出演機会も増え、演奏水準が上がっているようだ。

プログラムはカルロス・サイモンの「祝典ファンファーレと序曲」、メンデルスゾーンのヴァイオリン協奏曲ホ短調、メーンにラフマニノフの交響曲第2番と、米国育ちの地力が発揮されそうな構成。メンバーは黒いジャケットに赤いスラックス、コンバースの白いスニーカーと、フレッシュな出で立ちで舞台に立った。

冒頭の序曲はアンドリス・ネルソンスのボストン響在任10年などを祝う5分ほどの機会音楽で、カーネギーホールも当ツアーを念頭に委嘱へ加わった。ショスタコーヴィチ「祝典序曲」へのオマージュ的な面がある華々しい作品で、まずは若いパワーを誇示した。
コントラバス奏者の弓使いはフランス式がドイツ式より多く、日本などの情勢と逆なのが興味深い。多様なメソッドや流儀を修めた奏者が集う様子を、端的に示した。この影響もあってか、響きの土台は終始、柔軟な感触を保っていた。
協奏曲の独奏は若手ヴァイオリニストのレイ・チェン。技巧派で鳴らすだけに、エッジの張った浸透力ある音色とキメの大きなヴィブラートを駆使して、身ぶりや構えが大きいソロを繰り広げた。これに対しノセダは、カンタービレが利いた弱音を時に効果的に使って、古典的な抑制美を表出した。

ラフマニノフはノセダが得意とする作曲家のひとりだけに、交響曲第2番は「おはこ」だろう。弦楽セクションが一体となって同じ方向へ身体をなびかせる強大なうねりを作りだし、熱量の高いサウンドを築いた。オケの音色は明るく、第3楽章アダージョは憂愁より、燃える情熱が勝った印象。終楽章はアレグロ・ヴィヴァーチェの指定通り、さっそうとした運びで、力感に満ちた頂点を形づくった。
(深瀬満)
公演データ
ジャナンドレア・ノセダ指揮 カーネギーホール ナショナル・ユースオーケストラUSA
7月26日(土) 17:00サントリーホール 大ホール
指揮:ジャナンドレア・ノセダ
ヴァイオリン:レイ・チェン
管弦楽:ナショナル・ユースオーケストラUSA
プログラム
カルロス・サイモン:祝典ファンファーレと序曲
メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調Op.64
ラフマニノフ:交響曲第2番 ホ短調 Op.27
ソリスト・アンコール
イザイ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第2番 イ短調 Op.27-2 より第1楽章
パガニーニ:24のカプリースOp.1より第21番
アンコール
マスカーニ:オペラ「カヴァレリア・ルスティカーナ」より間奏曲
チャイコフスキー:バレエ組曲「くるみ割り人形」Op.71aより第4曲〝ロシアの踊り(トレパーク)〟

ふかせ・みちる
音楽ジャーナリスト。早大卒。一般紙の音楽担当記者を経て、広く書き手として活動。音楽界やアーティストの動向を追いかける。専門誌やウェブ・メディア、CDのライナーノート等に寄稿。ディスク評やオーディオ評論も手がける。