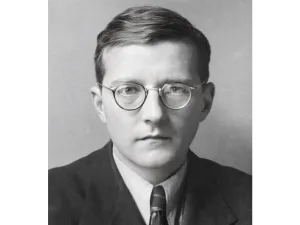マーラー・フェスの演目、交響曲第3番で壮麗かつ繊細な演奏を聴かせたルイージとN響
ファビオ・ルイージ指揮、NHK交響楽団の4月定期Aプロ、マーラーの交響曲第3番ニ短調。オランダで開催されるマーラー・フェスティバル(5月8日~18日)など、来月に予定されているヨーロッパ・ツアーで演奏する作品である。それだけにルイージはもとより、N響メンバーの気迫も並々ならぬものがあり、全曲にわたって高い集中力を維持し、指揮者の意図を反映した繊細さと壮麗さを兼備した演奏が披露された。終演後にはオケが退場しても盛大な喝采が止まず、ルイージが2度もステージに呼び戻されるほどの盛り上がりとなった。

ツアー仕様ということで長原幸太、郷古廉の両第1コンマス、フルートでは神田寛明首席が1番を、甲斐雅之首席がピッコロを担当するなど、ほとんどのパートで首席奏者が2人とも出演していたのも特別感を醸し出していた。
全曲にわたって勢いで押す場面は皆無で、細部にまでルイージの意図を具現化しようとのメンバー全員の集中力の高さは特筆すべきもの。第1楽章冒頭、ホルン8本による第1主題からアウフタクトを深い呼吸感をもって奏でて各旋律をたっぷりと歌わせていく。調の変わり目、特に弱音の場合は和声の移ろいが美しく表現されるデリケートさも際立った。マーラー・フェスにはロイヤル・コンセルトヘボウ管(指揮クラウス・マケラ)、ベルリン・フィル(同キリル・ペトレンコ、サカリ・オラモ)、シカゴ響(同ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン)などが出演するが、その中でこの日のような、ち密で繊細な演奏は他にはない持ち味となるはすだ。

最強音でもパート間のバランスが絶妙に調整された美しい響きが創出された。最たる例は第6楽章のコーダ。金管楽器を必要以上に突出させずに弦楽器の豊かな響きを土台にオルガンのようなハーモニーを構築し、深みを感じさせる締めくくりとなった。コーダ終盤、2人のティンパニ奏者(久保昌一、植松透両首席)によるD(レ)、A(ラ)の連弾も互いの間合いを合わせながら音程感が明快で重厚なサウンドによって音楽にどっしりとした推進力をもたらしていた。
後半、金管にミスが散見されたことが一部SNSで取り沙汰されていた。長い第1楽章ではほぼ無傷だったが、前半の弱音部で微細なニュアンスを表現するためなどで唇(アンブシュア)を長時間酷使したことが原因ではないかと予想される。2日目の公演、そしてツアーに向けてペース配分の改善を期待したい。
とはいえ、全体としては指揮者の作品解釈、それに応えるオケ・メンバーの集中力、演者全員の漲(みなぎ)る気迫によって聴衆の心に響く演奏であったことは盛大な喝采からも明らかである。
(宮嶋 極)

公演データ
NHK交響楽団 第2036回定期公演Aプログラム
4月26日(土)18:00 NHKホール
指揮:ファビオ・ルイージ
メゾ・ソプラノ:オレシア・ペトロヴァ
合唱:東京オペラシンガーズ、NHK東京児童合唱団
管弦楽:NHK交響楽団
コンサートマスター:長原 幸太
プログラム
マーラー:交響曲 第3番ニ短調
※他日公演 27日(日)14:00 NHKホール
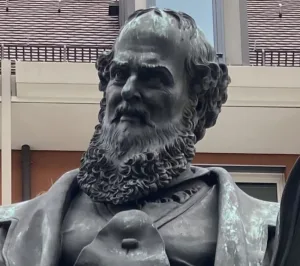
みやじま・きわみ
放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。