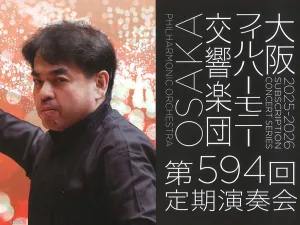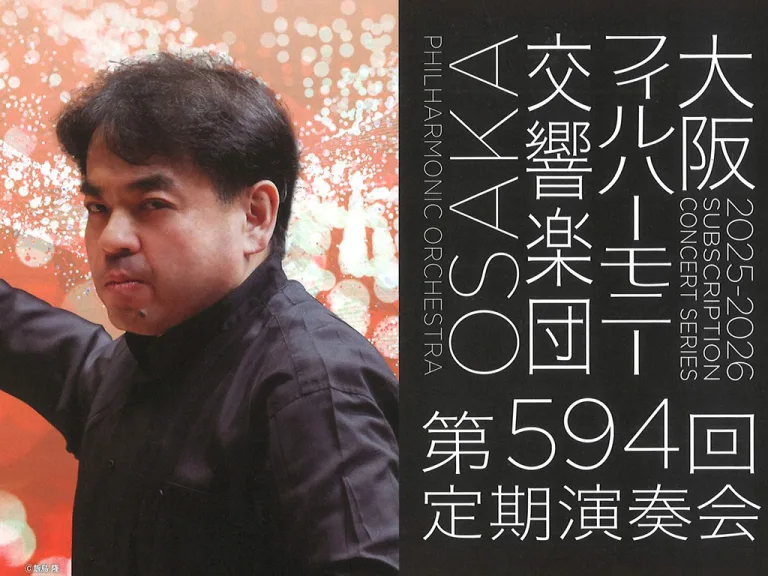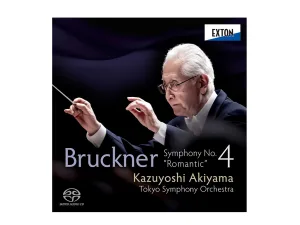これは大歌手による理想の歌唱の博覧会だ!
この晩は第一声から違った。超売れっ子でタイトなスケジュールをこなすためか、このところ疲れを感じることもあったが、芯がある強靭な中音域に支えられ、低音域も高音域も安定し、声が思いのまま駆け巡る。1曲目はモーツァルト「後宮からの逃走」のコンスタンツェのアリアで、コロラトゥーラは無理なく高音まで駆け上がって軽快に、しかも精密に回りながら音圧はたもたれる。弱音からさりげなく音を漸増させるのも、声が完璧に制御されている証だ。ベルカントのすぐれた歌唱技巧の博覧会のようだった。

東京フィルを指揮したコッラード・ロヴァーリスがまたいい。ロッシーニ「セミラーミデ」序曲は快活なクレッシェンドが心地よく、続けてオペラ全曲を聴きたくなったが、そんな指揮者を得てオロペサの歌はさらに躍動する。ベッリーニ「清教徒」の〝私は美しい乙女〟では舞曲のリズムで表現される装飾歌唱が安定し、安定しているがゆえにエルヴィーラの天真爛漫な感情がすべての音からにじむ。
一方、ロッシーニ「ギヨーム・テル」のロマンス「暗い森」では、レガートの旋律がたっぷりと味わえた。高、低、強、弱、すべての音が均質に安定し、質量は十分にあるのにやわらかい。しかも音色に高貴な艶が加わって、ハプスブルク家の皇女の役にふさわしい。

数年前、オロペサにインタビューした際、「私の声はカメレオンのようにどんな色にもなる」と語っていた。当時の彼女の声はいまほど安定せず、表現や音域ごとに声質自体を変えているところがあったが、いまは声質を常に一定にたもち、色彩を無限に変化させる。同じカメレオンでもいまは、王者の七変化をみせる。
後半はマイアベーア「悪魔のロベール」の、シチリアの王女イザベルのアリアから。芯がある張りつめた声に倍音を響かせ、深い感情を描く。オロペサは装飾歌唱も以前より精緻で鮮やかだが、レガートの旋律もますます磨きがかかり、深みを増している。支え、声を集め、響かせるという基礎が盤石だから、進化を続けることができるのだろう。
ヴェルディ「リゴレット」のジルダの〝慕わしい人の名は〟では、細かく精密なブレスコントロールを得て、どの音の響きにも揺れがない。安定をきわめた歌唱だからこそ、恋に目覚めた少女の心の高鳴りが聴こえる。グノー「ロメオとジュリエット」のワルツも、歌の器が安定しているからこそ、弾むような若さを自然に帯びる。
いずれもオペラ全曲を聴きたくなった。すべてが大歌手による理想の歌唱だった。
(香原斗志)

公演データ
旬の名歌手シリーズXⅢ リセット・オロペサ ソプラノ・コンサート
4月10日(木) 19:00サントリーホール 大ホール
指揮:コッラード・ロヴァーリス
ソプラノ:リセット・オロペサ
管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団
プログラム
モーツァルト:歌劇「後宮からの逃走」より〝どんな責め苦があろうとも〟
ロッシーニ:歌劇「セミラーミデ」より序曲 (オーケストラ)、歌劇「ギヨーム・テル」より〝ついに遠のいてしまった〟~〝暗い森〟
ベッリーニ:歌劇「清教徒」より〝私は美しい乙女〟
マイアベーア:歌劇「悪魔のロベール」より〝ロベール私の愛する人〟
ヴェルディ:歌劇「シチリア島の夕べの祈り」より序曲(オーケストラ) 、歌劇「リゴレット」より〝慕わしい人の名は〟
グノー:歌劇「ロメオとジュリエット」より〝私は夢に生きたい〟

かはら・とし
音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。