北の大地に育まれた独特のサウンドで首都圏の音楽ファンを魅了した札幌交響楽団の東京公演
札幌交響楽団の東京公演。今年は同団友情指揮者、広上淳一とともにサントリーホールにやってきた。
私事だが、筆者が初めてオーケストラの生演奏を聴いたのは札響であった。55年も前のこと。指揮は当時の常任ペーター・シュヴァルツ。中高生の頃には定期会員となり、毎月公演に通っただけでなく首席ティンパニ奏者に打楽器のレッスンを、団員関係者にピアノの手ほどきを受けたりもした。いわば自分にとっては音楽生活の原点のような懐かしさを覚えるオケである。とはいえ、今では札響を聴ける機会は少なく前回聴いてから10年以上は経過、その間にどんな変化を遂げたのか、興味津々で臨んだ。

開演に先立ち先月急逝した指揮者の秋山和慶を偲び、モーツァルトのディヴェルティメントK.136が献奏された。透明感がありつつも暖かさを感じさせる独特の札響サウンドは健在であった。
1曲目は武満徹が作曲した黒澤明監督晩年の大作「乱」の音楽を演奏会用に編曲した組曲。この映画のサントラを岩城宏之指揮、札響が担当したことは有名だが、これに先だつ1976年に当時、札響正指揮者だった岩城が定期でオール武満プロを組み、この時の演奏を武満が気に入り、「乱」の音楽へと結びついていったという、このオケにとってはお家芸のような作品である。前述の通り透明感のあるサウンドを駆使して、深く沈み込んでいくような空気間の創出は作品の世界観を見事に表現するものだった。

2曲目は外山啓介をソリストに迎えて伊福部昭のリトミカ・オスティナータ。リズムの執拗な反復が特徴で、後のミニマル音楽に繋がるような作品。同じリズム・パターンの繰り返しが単調に陥ることなく、また、多数の打楽器が必要以上の喧騒を作り出すこともなく音楽的な変化を明快に表出していた。
メインはシベリウスの交響曲第2番。北国フィンランドの作曲家シベリウスの作品は、似た気候風土で暮らす札幌の人々の共感を得やすいのかこのオケは昔から取り上げることが多かった。東京のオケのような緻密な組み立てとは少し異なる、おおらかで開放的な響きの構築が印象的で、そこから作品の別の表情が表れてくるのが興味深かった。第4楽章のコーダに向かって息の長い盛り上げ方も自然の雄大さを感じさせるもので、終演後は客席を大いに沸かせていた。久しぶりの札響は伝統的なキャラクターを継承しつつも、メンバーの若返りによって技術水準がかなり向上していたように感じた。
(宮嶋 極)

公演データ
札幌交響楽団 東京公演2025
2月3日(月)19:00 サントリーホール
指揮:広上 淳一
ピアノ:外山 啓介
管弦楽:札幌交響楽団
コンサートマスター:田島 高宏
プログラム
モーツァルト:ディヴェルティメントニ長調K.136から第2楽章(献奏)
武満徹:「乱」組曲(映画音楽の演奏会用編曲版)
伊福部昭:リトミカ・オスティナータ~ピアノとオーケストラのための
シベリウス:交響曲第2番ニ長調Op.43
アンコール
チェレプニン:10のバガテルより第4曲(ソリスト)
シベリウス:悲しきワルツOp.44-1(オーケストラ)
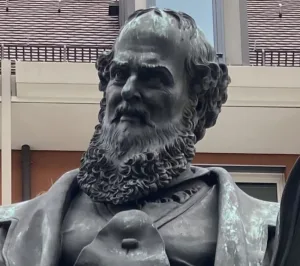
みやじま・きわみ
放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。


















