ブルックナー生誕200年記念イヤーにちなみ、交響曲第8番の初稿で充実の演奏を聴かせたルイージとN響
N響の新シーズン幕開けとなる定期Aプロで、首席指揮者ファビオ・ルイージはブルックナーの交響曲第8番、1887年完成の初稿を取り上げた。取材は2日目の公演。

ルイージは金管楽器を舞台上段下手からホルン&ワーグナーテューバ→テューバ→トロンボーン→トランペットと変則的な配置とするなどして、響きのバランスに細心の注意を払い、転調によるハーモニーの変化を明瞭に示すことで聴き慣れた第2稿(1890年)との違いを浮き彫りにするようなアプローチ。その上で各旋律を深い呼吸感をもって処理し、N響の美点を十分に引き出した重厚な演奏に仕上げた。

第1楽章は2稿に比べると対位法的な要素とティンパニの出番が少なく、構造面よりも和声に重きが置かれており、第7番の延長線上にあることが分かる。第2楽章はスケルツォの中間部がかなり異なっており、時折、長調の明るい響きが唐突に表れる。第3楽章はこの日の演奏でも29分を要する長大さ。シンバルが6回(第2稿は2回)鳴らされる頂点でハ長調(第2稿は変ホ長調)となるが、ルイージの巧みな響きの構築によってそのニュアンスの違いが伝わってきた。この盛り上がりが収束し、弦楽器とハープの静かな箇所はワーグナーの「ジークフリート」第3幕、ブリュンヒルデの目覚めの音楽の影響を受けているように感じた。さらに第4楽章のコーダ、第2稿ではオケが全開となり一気にフィナーレになだれ込むのに対し、初稿はいったん音量を落とし、再びブラスの強奏となるあたりに「ラインの黄金」の幕切れを想起させられた。初稿はワーグナーの影響を色濃く残し、第2稿はベートーヴェンを意識した改訂と考えられるのかもしれない。それは主調のハ短調に対して第2稿では終楽章コーダまでハ長調は控えられ、構造面を強化していたことからも分かる(ベートーヴェンの第5交響曲もハ短調が第4楽章にハ長調に転じる)。こうしたことが伝わってくるほど、この日の演奏は内容の濃いものであった。
(宮嶋 極)
※取材は9月15日の公演

公演データ
NHK交響楽団 第2016回定期公演Aプログラム
9月14日(土)18:00、15日(日)14:00 NHKホール
指揮:ファビオ・ルイージ
管弦楽:NHK交響楽団
コンサートマスター:郷古 廉
プログラム
ブルックナー:交響曲第8番ハ短調(1887年、初稿)
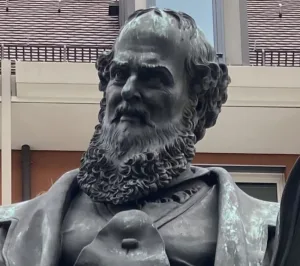
みやじま・きわみ
放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。

















