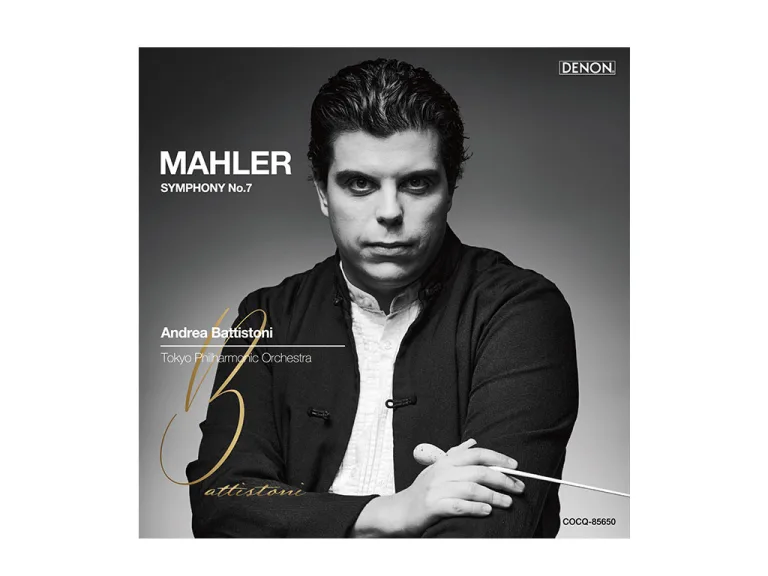中伊ペーザロにおけるロッシーニ・オペラ・フェスティバル(ROF)のリポート第2弾。今回はダニエラ・バルチェッローナ主演の「アルジェのイタリア女」と各種コンサートについて。
驚異的に保たれていたバルチェッローナの声
8月14日と18日、「アルジェのイタリア女」を鑑賞した。14日はロッシーニ劇場に着いたのが開演10分前で、劇場前でプレイベントが繰り広げられていたのを知らなかった。演出はそこから始まっていたのだ。18日に見たが、派手なワゴン車でドラァグクイーンたちがやってきて、大騒ぎしたのち劇場内に消えていった。

指揮はすぐれたテノールで、新国立劇場でも「ウェルテル」や「ホフマン物語」に主演したディミトリー・コルチャック。指揮をする歌手はなぜかテノールに多い。そのなかでは音楽性が高く、ロッシーニも熟知しており、この作曲家らしい抑揚や快活さが品よく表現されていた。精妙とまではいわないが、ほかの歌手による指揮とは、同じ次元で語れないものだったとはいえる。
ロゼッタ・クッキの演出には若干の読み替えがあった。イザベッラ、つまりイタリア女はドラァグクイーンとして描かれたのだ。「私が演じたのは女性に扮した男。アルジェの太守ムスタファはそれを女だと勘違いしているという設定です」とバルチェッローナが語る。

舞台上には黙役として本物のドラァグクイーンたちが出演。彼らが集団でムスタファを騙すのだが、イザベッラは派手に足を見せるドレスなどいろいろな服装で登場し、「5回も替えました」(同)。色彩豊かでハチャメチャだが、それが「アルジェのイタリア女」の音楽と構成、世界観とマッチした楽しい舞台だった。
それ以上に、バルチェッローナの歌唱に驚いた。1999年、私は同じ劇場で彼女が歌う「タンクレーディ」の題名役を聴いた。センセーションを巻き起こしたが、近年はヴェルディの重厚な役も歌い、いまさらロッシーニを柔軟に歌うには限界があると思い込んでいた。ところが、声はやわらかくフレージングはなめらかで装飾歌唱は鮮やか。非の打ちどころがなかった。本人に秘訣を尋ねると「息に乗せる発声を守り、声を締めつけないこと。幸い、ヴォーカルコーチでもある夫が常にチェックしてくれます。ジムで体を鍛えることも欠かせません」。
ムスタファ役のジョルジ・マノシュヴィリ、タッデーオ役のミーシャ・キリアら低声も健闘。リンドーロ役のテノール、ジョシュ・ロヴェルも逸材だが、声に芯があり、もう少し重い役で大成するのではないだろうか。

若手からベテランまで一級の歌手たちの歌
コンサートも充実していた。13日はヴァシリーサ・ベルジャンスカヤの管弦楽伴奏コンサート。メゾ・ソプラノと認識していたが、セミラーミデやアルミーダはともかく、アミーナにルチアとソプラノの曲ばかりだった。それでも声は充実し、安定していた。14日はマルコ・ミミチャ(バス)のピアノ伴奏のリサイタル。魅惑的で深い声をどの音域も均質かつ柔軟に響かせ、ベルカントのバスでは現在、最高峰だろう。ロッシーニやベッリーニは様式感にすぐれ、ドヴォルザークやムソルグスキーの世界観も絶品だった。

16日は、チェチーリア・モリナーリ(メゾ・ソプラノ)のピアノ伴奏リサイタルが秀逸だった。ロッシーニやソプラノのマリブランらによる、19世紀前半の室内歌曲に絞ったプログラムで、すみずみまで磨かれながら生命力あふれる歌唱に「機能性が高い最高峰の楽器による無欠の演奏」という言葉が浮かんできた。アンコールで歌った「今の歌声は」も技巧がこなれ、洗練を極めていた。17日はロッシーニのカンタータを並べたコンサート。2人の若き逸材、ジュリアーナ・ジャンファルドーニ(ソプラノ)の輝かしい声、ダーヴェ・モナコ(テノール)の柔軟で瑞々しい歌唱が強い印象を残した。

19日はミケーレ・ペルトゥージ(バス)の管弦楽伴奏コンサートに酔った。「カタログの歌」にはじまり、ロッシーニは「セミラーミデ」「ギヨーム・テル」、そして「夢遊病の女」「ドン・パスクワーレ」「シチリアの晩鐘」「ドン・カルロ」と時代が下る構成。いずれも考え抜かれた造形で、メッサ・ディ・ヴォーチェをはじめ盤石のテクニックで表情が細かくつけられ、まさに大歌手の歌。スタンディングオベーションで拍手が止まなかった。
テノールの河野大樹が歌った若者公演「ランスへの旅」だけは、次回に紹介する。


かはら・とし
音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。