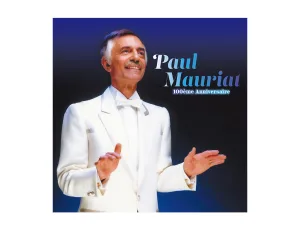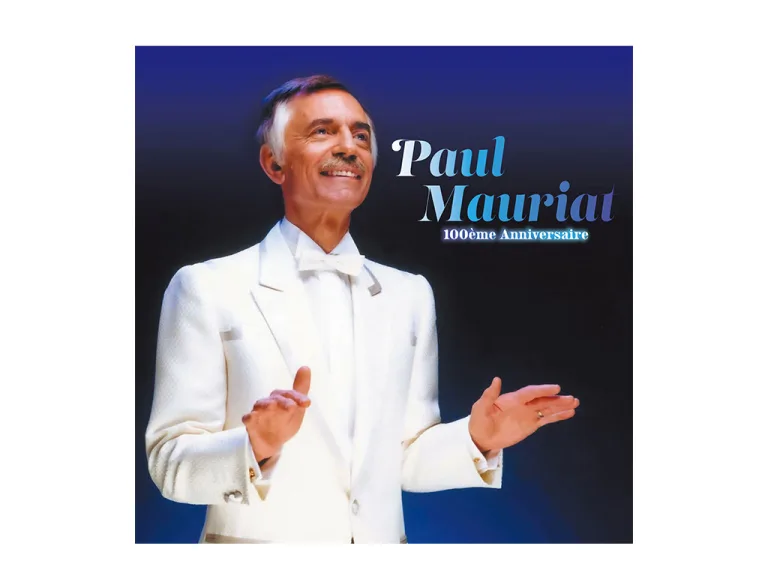2020年はベートーヴェンの生誕250年を祝するベートーヴェン関連の大きな企画がいくつも計画されていた。しかし、同年早春に始まったコロナ禍のため、そのほとんどが開催中止になった。いろいろ楽しみな演奏会が予定されていただけに本当に残念だった。それでも2027年がベートーヴェンの没後200年にあたるので、2020年に辛苦を味わった演奏家たちは、次のベートーヴェン・イヤーを目指して、リベンジを誓ったのであった。
2027年に先立って、いち早く、ベートーヴェン・ツィクルスを始めたのは、鈴木優人&関西フィルハーモニー管弦楽団。関西フィルの首席客演指揮者を務めている鈴木は、「ベートーヴェン・ヒストリー」というタイトルのもと、2025年6月から2027年まで、1年3回のペースで、交響曲全9曲を番号順に取り上げていく。合わせて、序曲や協奏曲も演奏され、とりわけピアノ協奏曲でフォルテピアノが使用されるのが注目される。
いうまでもなく、鈴木優人はバッハ・コレギウム・ジャパン(BCJ)で首席指揮者を務めるなど古楽に造詣が深い。鈴木はBCJでも、2026年1月から「ベートーヴェンへの道」というシリーズをスタートさせ、ベートーヴェンの交響曲に取り組む。BCJでは、ピリオド楽器でのベートーヴェンの交響曲全曲演奏が非常に楽しみである。また、ベートーヴェンと組み合わせる作品もC・P・E・バッハのシンフォニアやケルビーニのレクイエムなど、彼らならではである。
関西では、今年、久石譲が音楽監督に就任した日本センチュリー交響楽団もベートーヴェンの交響曲を続けて取り上げている。2025年度の定期演奏会は、ベートーヴェンの交響曲と1950年以降に作曲された作品とでプログラミングされている。久石らしいアイディアといえるだろう。久石はベートーヴェンと自作とを組み合わせる。
大阪フィルハーモニー交響楽団も音楽監督・尾高忠明との2度目のベートーヴェン・ツィクルスをこの9月に始めた。1回目のツィクルスが尾高の音楽監督就任直後の2018年であったが、7年振りの全曲演奏で、このコンビの深化を確かめたい。
東京では、矢部達哉率いる「トリトン晴れた海のオーケストラ」が2023年から2027年の完結を目指して、年2回のペースでベートーヴェンの交響曲全曲演奏に取り組んでいる。彼らも2度目のツィクルスで、前回は2018年から2021年までであった。指揮者なしで、コンサートマスター矢部のリードのもと緊密なアンサンブルが作り上げられる。
また、先日、NHK交響楽団が2026年の創立100周年記念事業を発表したが、そのなかに没後200年に先駆けるものとして、2026年9月から12月にかけてのベートーヴェン交響曲全曲演奏の開催も含まれている。ルイージ、エッシェンバッハ、ソヒエフ、デュトワ、ヤノフスキというN響と関わりの深い指揮者たちが登場して、ベートーヴェンの交響曲全曲を手掛ける。巨匠たちのスタイルの違いを聴くのもまた楽しい。
既に始まっている感じもするベートーヴェン・イヤー。2020年の失われたベートーヴェン・イヤーを取り戻すべく、よりバージョン・アップされた企画に期待したい。

やまだ・はるお
音楽評論家。1964年、京都市生まれ。87年、慶応義塾大学経済学部卒業。90年から音楽に関する執筆を行っている。著書に、小澤征爾の評伝である「音楽の旅人」「トスカニーニ」「いまどきのクラシック音楽の愉しみ方」、編著書に「オペラガイド130選」「戦後のオペラ」「バロック・オペラ」などがある。