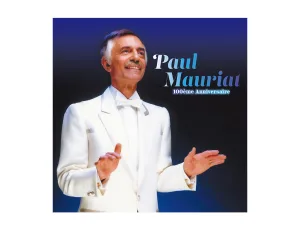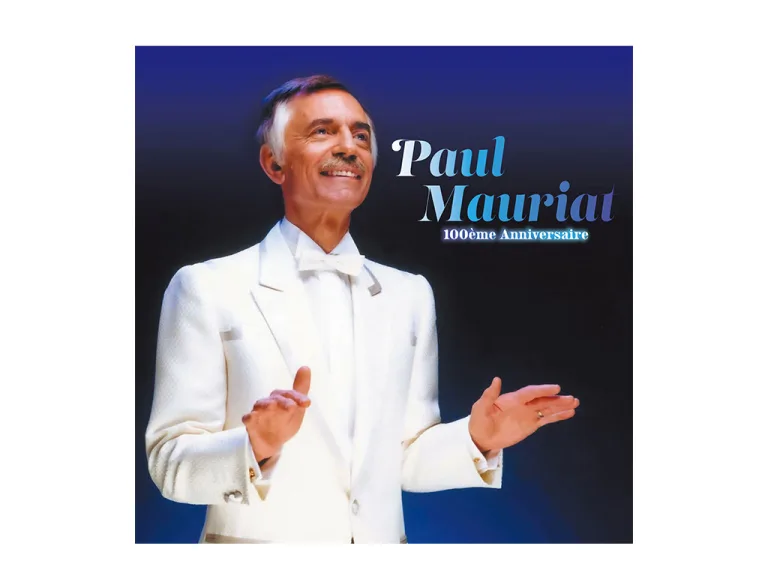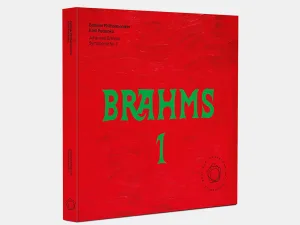毎日クラシックナビの「2024年開催公演ベスト10」座談会のとき、筆者は、2025年前半のオススメ公演としてクラウス・マケラ&パリ管弦楽団と山田和樹&バーミンガム市交響楽団をあげた。興味深いことに、そのどちらもがムソルグスキーの組曲「展覧会の絵」を取り上げ、パリ管がラヴェル編曲版を演奏するのに対して、バーミンガム市響はヘンリー・ウッド編曲版を使用する。
ムソルグスキーがピアノのための組曲「展覧会の絵」を作曲したのが1874年であったが、そのオーケストラ用編曲の最も早い試みは、1891年に初演されたミハイル・トゥシュマロフ版だといわれている。トゥシュマロフは、サンクトペテルブルク音楽院在学中に、師であるリムスキー=コルサコフのもとで、「展覧会の絵」の管弦楽化に挑んだ。なお、この編曲では、「グノーム」、「ビドロ」、「テュイルリーの庭」が省かれた。
ヘンリー・ウッド(1869~1944)は、ロンドンのプロムナード・コンサート(現在のBBCプロムス)を1895年のスタートから半世紀にわたって指揮した、イギリスを代表する指揮者。ウッドは、1915年に音楽評論家で女性解放活動家でもあったローザ・ニューマーチの勧めで、「展覧会の絵」を編曲したのであった。
ウッド版はラヴェルよりも早い時期の編曲であり、いうまでもなくラヴェル版の影響をまったく受けていない。冒頭のプロムナードは複数の金管楽器のユニゾンで始まり、「古城」では、舞台裏のユーフォニウムが旋律を吹く。妖婆が現れる「バーバ・ヤーガの小屋」では、ラヴェル版以上の魑魅魍魎(ちみもうりょう)感が描かれる。「バーバ・ヤーガの小屋」の最後の部分にはカットがあり、鐘の音に導かれて「キーウ(キエフ)の大門」が始まる。終結では、鐘が打ち鳴らされ、オルガンまで加わり、(ラヴェル以上に)壮大なクライマックスが築かれる。ところが、ウッドは、後にラヴェル版が普及すると、自らの編曲版を取り下げてしまうのであった。
「管弦楽の魔術師」と呼ばれたモーリス・ラヴェル(1875~1937)。その緻密なスコア(管弦楽総譜)により、ストラヴィンスキーは彼のことを「スイスの時計職人」と評した。そんなラヴェルであるが、彼はもともとパリ音楽院のピアノ科の学生だった(後に作曲科に入る)。ラヴェルの初期のオーケストラ作品は、自らのピアノ曲を管弦楽化したものが多い。「古風なメヌエット」「亡き王女のためのパヴァーヌ」「海原の小舟」「道化師の朝の歌」「高雅で感傷的なワルツ」「マ・メール・ロワ」などなど。しかし、彼は、1917年に「クープランの墓」を書き上げたあと、ピアノ独奏曲の創作を止めて、オーケストラを使った作品に一層傾倒していく。指揮者のセルゲイ・クーセヴィツキーがラヴェルに「展覧会の絵」の管弦楽化を依頼したのは1922年のことであった。まさに「ラ・ヴァルス」と「ボレロ」の間のラヴェルのオーケストレーションが円熟期を迎えていた頃の編曲である。
2つの「展覧会の絵」。フランス人が編曲したものをフランスのオーケストラが、イギリス人が編曲したものをイギリスのオーケストラが演奏する今回の〝競演〟に注目である。

やまだ・はるお
音楽評論家。1964年、京都市生まれ。87年、慶応義塾大学経済学部卒業。90年から音楽に関する執筆を行っている。著書に、小澤征爾の評伝である「音楽の旅人」「トスカニーニ」「いまどきのクラシック音楽の愉しみ方」、編著書に「オペラガイド130選」「戦後のオペラ」「バロック・オペラ」などがある。