今、最も信頼を寄せるティーレマンのタクトで美しいブルックナーを聴かせたウィーン・フィル
ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパンから東京公演初日を聴いた。指揮はクリスティアン・ティーレマン。演目はブルックナーの交響曲第5番。世界トップ・クラスの指揮者が入れ替わり立ち代わり指揮をするウィーン・フィル(WPH)のメンバーが今、最も信頼を寄せているのがティーレマンである。(WPHメンバーに聞くとかなりの割合でそう答える)それだけに彼が指揮台に立つと演奏に一層熱が入り、名演が生まれる。当夜もそうだった。

筆者はベルリン・ドイツ・オペラ時代の1990年代からティーレマンに注目し取材してきたが、最近、その音楽作りがかなり変貌してきたように感じる。極端な表情付け、例えばテンポを大きく揺らしたり、譜面に記されていない間(ま)をとったりというような作為的表現がすっかり影を潜めた。この日のブルックナーも大河の流れのごとく音楽の進行は自然で雄大。フレーズとフレーズ、旋律と旋律の自然な繋ぎ方に細心の注意を払っているように感じた。
第1楽章、弦楽器のピィツィカートによる導入からティーレマンは腰をかがめて弱音を維持しつつパート間の音量バランスを細密にコントロールしていく。これは全曲にわたって頻繁に行われ、この曲でよく使われる「大伽藍(だいがらん)のような響き」ではなく、全パートの隅々にまで神経を行き渡らせた美しいハーモニーの構築に腐心していることが分かる。全体に金管楽器を咆哮させることはせずにコーダのみテューバを除く金管楽器全パートとティンパニのアシスタントも加わり力強く締め括った。
第2楽章はWPH弦セクションの厚く美しい響きの魅力が全開となり(特に第2主題)聴衆をさらに引き込んでいく。第3楽章も意外と思えるほどレガート気味に流れを重視した音楽作りが維持されていた。
第4楽章は若干速めのテンポでコーダに向かってエネルギーを溜めてヤマ場を少しずつ築いていくような構え。フーガ的な対位法が特徴の楽章であるが、その構造をスケルトンのように示すというよりは、ここでもティーレマンは音量バランスに気を配り美しいハーモニーの創出に注力していた。WPHもその要求に応えてこのオケならではの美しい響きを紡ぎ出してみせた。コーダに入って初めてオケを全開にして鳴らし、輝かしい大団円を創出した。
終演後、ティーレマンは「決して強すぎない(うるさくない)豊かな響きを創り出すことができた」と演奏を振り返っていた。その言葉通りであろう。壮麗な響きが消え入り、しばしの静寂の後、盛大な喝采とブラボーが鳴り止まず、ティーレマンはオケ退場後、2度もステージに再登場し歓呼に応えていた。
なお、WPHの来日公演は今回で40回目、ティーレマンとは4回目となる。
(宮嶋 極)
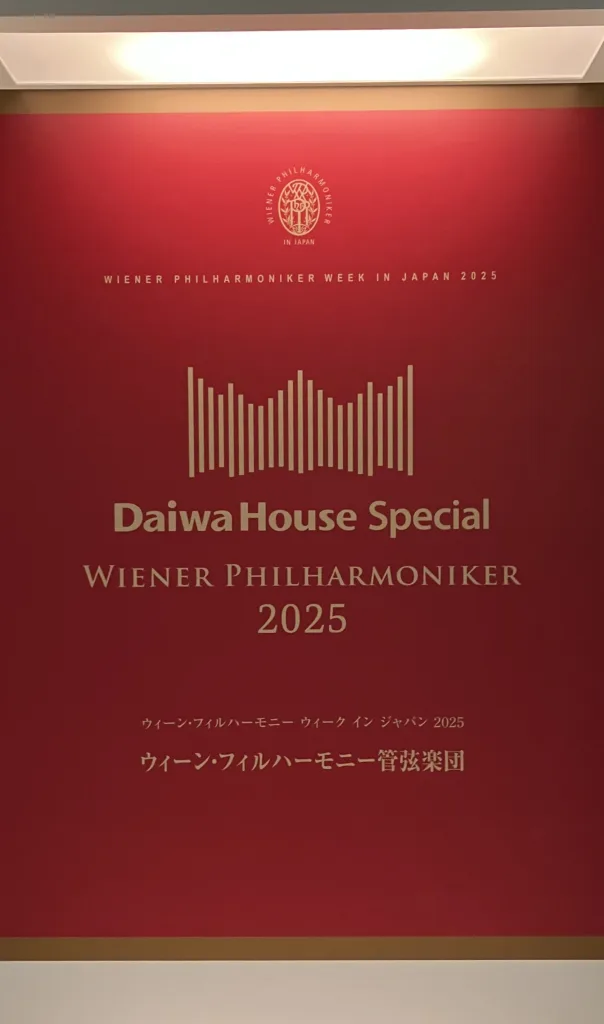
公演データ
クリスティアン・ティーレマン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン 2025 東京公演1日目
11月11日(火)19:00 サントリーホール 大ホール
指揮:クリスティアン・ティーレマン
管弦楽:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
コンサートマスター:ライナー・ホーネック
プログラム
ブルックナー:交響曲第5番 変ロ長調WAB.105(ノヴァーク版)
他日公演
11月12日(水)19:00、15日(土)16:00、16日(日)16:00、いずれもサントリーホール
※プログラム等の詳細はサントリーホールの公式サイトをご参照ください。
https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/feature/wphweek2025/
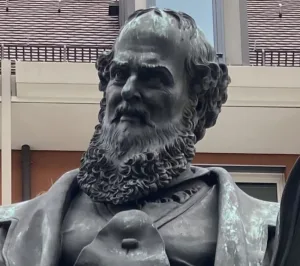
みやじま・きわみ
放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。
















