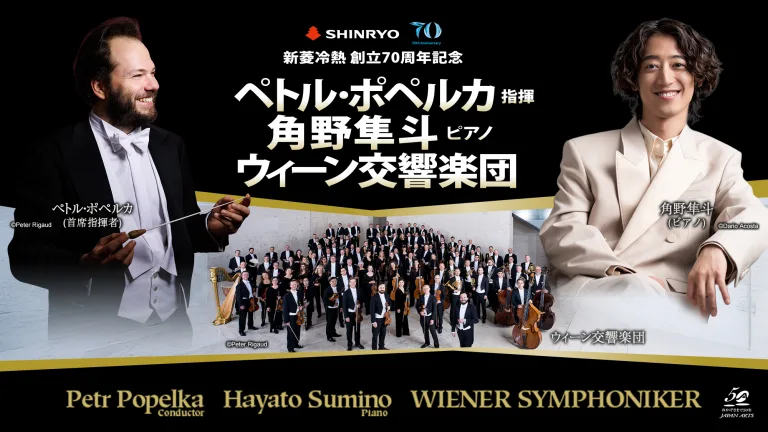指揮者とソリストが共有したロシア=ソヴィエト音楽への真摯な眼差し
ヴァイグレの読響常任指揮者7年目のシーズンは、ショスタコーヴィチの没後50周年と重なった。かねて「ロシア音楽はレパートリーの根幹の1つ」と語ってきたが、それは自身のバックグラウンドと一体のものだろう。生まれたのと同じ年、1961年に突如構築された「壁」は故郷ベルリンを東西に分断、ヴァイグレはソヴィエト社会主義共和国連邦(ソ連)の衛星国家、ドイツ民主共和国(東ドイツ)で育った。抑圧された社会で音楽の内実のみを真摯に究める姿勢を作曲家、指揮者が共有していることは確かだ。

冒頭のグリンカはロシア革命以前、1848年に書かれた小品。民謡の引用が「古き時代」を体現、木管ソロの彩りともども、ロシア気分を盛り上げる食前酒の役目を果たした。
2004年、「ベルリンの壁」崩壊の15年後に生まれた北村陽は現在、統一ドイツの首都となったベルリンの芸術大学(UDK)で学び、ヨーロッパ各地のコンクールを次々と制覇している。「チェロと管弦楽のためのコンチェルト・ラプソディ」は1963年、ハチャトゥリアンも弾圧の憂き目に遭った旧ソ連の独裁者スターリンの没後10年目に、満を持して作曲された。20世紀後半を代表するチェロのヴィルトゥオーゾ(名手)、ロストロポーヴィチの超絶技巧を前提とするだけに演奏の難易度は高いが、北村は易々とハードルを乗り越え、アルメニア人作曲家特有の民族的な旋律も、よりスマートでモダンな音楽として再現した。弱音であっても常に明瞭に発音され、急速な楽章のリズムも正確に刻む。ヴァイグレと読響は大編成でも柔軟性を失わず、ソリストを万全に支えた。

ショスタコーヴィチ「第15番」をヴァイグレが指揮するのは初めて。読響にとっても、手慣れたレパートリーとは言い難い。両者とも時に手探りの瞬間を見せながら、作曲家最晩年(1971年)の心象風景にどこまでも迫ろうとする真摯な演奏態度を高い次元で一致させた。第1楽章は打楽器の切れ味いい音に始まり、トランペット辻本憲一、フルート倉田優、ホルン松坂隼、コンサートマスター林悠介らのソロが名技を競いながら、パワフルな音響へと結実した。ロッシーニの引用が極めてシニカルに響いたのも印象的だ。第2楽章は遠藤真理の秀逸なチェロ、悲壮感を漂わせた林のソロや金管群の豊かな重奏に彩られながら、沈鬱な世界の中からロシア伝統の響きが聴こえてくる。第3楽章では再び木管群が大活躍した。ワーグナーの引用も「黄昏」や「愛の死」と暗く、陰々滅々が続きながら永遠の静寂に帰結する第4楽章は、当夜の白眉と言えた。ショスタコーヴィチは約20年後の旧ソ連崩壊を予感していた、と思わせるほどの説得力だった。
(池田卓夫)

公演データ
読売日本交響楽団 第652回定期演奏会
10月21日(火)19:00サントリーホール 大ホール
指揮:セバスティアン・ヴァイグレ
チェロ:北村陽
管弦楽:読売日本交響楽団
コンサートマスター:林悠介
プログラム
グリンカ:幻想曲「カマリンスカヤ」
ハチャトゥリアン:チェロと管弦楽のためのコンチェルト・ラプソディ
ショスタコーヴィチ:交響曲第15番 イ長調 Op.141
ソリスト・アンコール
J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲第6番より「サラバンド」

いけだ・たくお
2018年10月、37年6カ月の新聞社勤務を終え「いけたく本舗」の登録商標でフリーランスの音楽ジャーナリストに。1986年の「音楽の友」誌を皮切りに寄稿、解説執筆&MCなどを手がけ、近年はプロデュース、コンクール審査も行っている。