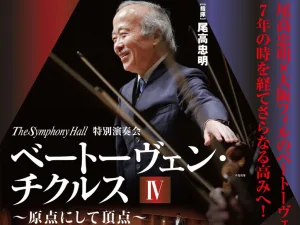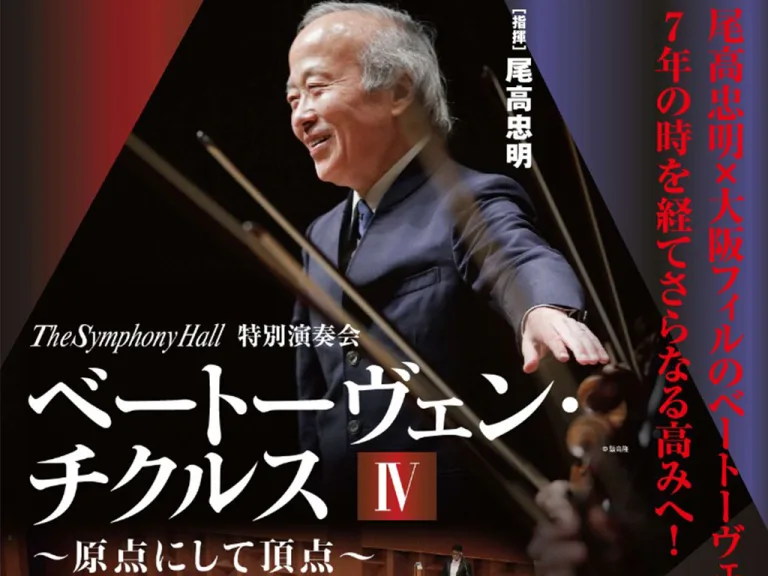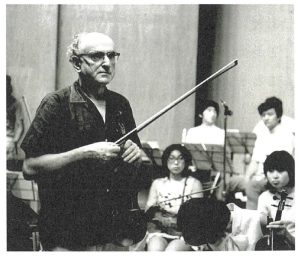全奏者渾身の壮絶な音楽! ショスタコーヴィチが見た景色を追体験
日本フィル首席指揮者就任以来、新鮮なアプローチで数々の名演を重ねてきたカーチュン・ウォン、今回は没後50年のショスタコーヴィチ、ピアノ協奏曲第1番と交響曲第11番「1905年」という作曲家の人生を辿(たど)るような選曲に挑んだ。

コンチェルトのソリストはピアノが小川典子、トランペットが同団ソロ・トランペット奏者のオッタビアーノ・クリストーフォリ、あとはヴァイオリン12型の弦楽器(コントラバスは5本)という室内楽的な編成だ。第1回ショパン・コンクールにソ連代表として参加した経験もあるショスタコーヴィチ、27歳の作品とあってピアノの見せ場も多いが、トランペットもオブリガードにとどまらず、2つの楽器の打打発止に魅了される。小川の硬質な打鍵による跳躍とクリストーフォリの超絶技巧を駆使するパッセージから若き作曲家のユーモアあふれる愉(たの)しさを味わえた。

交響曲第11番「1905年」は50代になったショスタコーヴィチがロシア革命の発端となった1905年1月22日の〝血の日曜日〟と言われる事件を描いており、それぞれの楽章につけられたタイトルから映像が浮かんでくる作品だ。ヴァイオリン16型、コントラバス10本という大編成で、クリストーフォリも引き続き後半の首席を務めた。
第1楽章「宮殿広場」の冷たく暗い冬の朝のアダージョや、ふんだんに引用される革命歌の明るさが冷徹なまでに美しい。第2楽章「1月9日」では宮殿に向かう民衆の強い決意がだんだんとその姿を現すように歌われるが、全楽器が鳴り響く中、スネアによる銃声の場面では、こちらの身体に痛みが走るような音のリアリティに驚愕(きょうがく)。直後の冒頭「宮殿広場」のアダージョを奏でるヴァイオリンの音も震えている。悲しみのトリルは折り重なった人々の息の音か。第3楽章「永遠の追憶」はコントラバスとチェロによるピッツィカートの重々しい響きから、ヴィオラが奏でる〝同志は倒れぬ〟の死を悼む旋律の美しさに息をのんだ。
第4楽章「警鐘」は、もはや一糸乱れぬ壮絶な合奏、ホルンやトランペットなどの最強軍団による激烈な音にスネア、ティンパニーも連打で応じ、クライマックスのあと再び「宮殿広場」のアダージョがまっすぐな音で蘇(よみがえ)る。歴史は繰り返すとでも言うように。

カーチュン・ウォンの狙いどおり2本立て映画のようなプログラム、それはショスタコーヴィチが見てきた景色を追体験するようだった。最後に鳴り響く鐘、その余韻が消えるまで、ウォンは左手を天に伸ばしたまま微動だにせず。全奏者渾身(こんしん)の壮絶な音楽は音が消えても耳の奥でまだ鳴り続けている。
(毬沙琳)
公演データ
日本フィルハーモニー交響楽団 第774回 東京定期演奏会
10月17日(金)19:00サントリーホール 大ホール
指揮:カーチュン・ウォン
ピアノ:小川典子
トランペット:オッタビアーノ・クリストーフォリ
管弦楽:日本フィルハーモニー交響楽団
コンサートマスター:扇谷泰朋
プログラム
ショスタコーヴィチ:ピアノ協奏曲第1番 ハ短調Op.35
ショスタコーヴィチ:交響曲第11番「1905年」ト短調Op.103
他日公演
10月18日 (土)14:00サントリーホール 大ホール

まるしゃ・りん
大手メディア企業勤務の傍ら、音楽ジャーナリストとしてクラシック音楽やオペラ公演などの取材活動を行う。近年はドイツ・バイロイト音楽祭を頻繁に訪れるなどし、ワーグナーを中心とした海外オペラ上演の最先端を取材。在京のオーケストラ事情にも精通している。