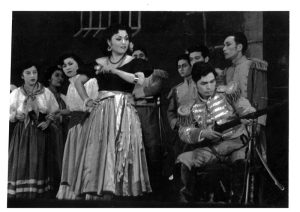シリーズを有終の美で飾る!オーケストラと〝以心伝心のコンチェルト〟を聴かせ、ベテランの貫禄を示す
小山実稚恵が弾くピアノ協奏曲によるシリーズ「Concerto~以心伝心」。その最終回は、デビュー40周年記念公演ということで、とっておきの2曲が並んだ。いずれも、小山が1982年のチャイコフスキー・コンクール本選で弾いた曲であり、今回、当時の指揮者、ウラディーミル・フェドセーエフと共演する予定であったが、事情により叶(かな)わず、氏の指名したドミトリー・ユロフスキが指揮台に立った。

前半、チャイコフスキーの第1番・冒頭楽章からして、実力派の面目躍如たるピアノであった。管弦楽は、14型の東京フィルをベースとし、弦5部の各部に1人ずつチャイコフスキー・シンフォニー・オーケストラ(旧モスクワ放送響)のプレーヤーを加えて、なかなかに強力だ。そんな相手と、芯のある、圧のある、しかし温かみを失わない響きで、対等にわたりあったのである。音の色あいや硬軟を自在に変え、また多層化してゆく技術は、まことに堂に入っており、同楽章の最終カデンツァなどを聴くと、それはもう「技術」とは思われない。動作や呼吸に作為がないのだ。

鍵盤楽器による「歌」は、一種のイリュージョンであるわけだが、第2楽章で彼女の紡ぎ出す歌は、ほんとうに歌声のよう。スケルツォふうの中間部では、打って変わって敏捷このうえない。けれども、そこへの移行も、またなんと自然であったことだろう。第3楽章では、途中、突如テンポを上げ、オーケストラを挑発。あるいは暴走だったか? だがオケも負けてはいない。それまでごく紳士的に見えたユロフスキが、属音上に築く変ロ長調の長いクレッシェンドを、ぐいぐいと増大させ、その天頂でティンパニに最強打を許す。すると小山のピアノが火を噴く――まさに、以心伝心のコンチェルトである。
対して、後半のラフマニノフ2番は、全体にオーケストラ主体と聞こえただろう。小山の側に、ピアノパートを含んだ交響的作品という(まっとうな)理解があったから、とみた。もちろん、ソロイスティックな高揚を聴かせた第2楽章・中盤のような例もあるが、それでも勝っているのは、管弦楽との協働の美である。同楽章終わりのアダージョ・ソステヌートの段などは、極上の室内楽。第3楽章・プレストのフーガ風の絡みもそう。前者は、センチメンタルになることなく、深いセンチメントを湛え、後者は、メカニックになることなく、正確を期していた。ベテランの貫禄と言うほかない。

アンコールとして、小山はまずソロでチャイコフスキーの「四季」より〝秋の歌〟を、次いでオーケストラとラフマニノフ「パガニーニの主題による狂詩曲」より第18変奏を披露。満場の熱い喝采を浴び、シリーズを有終の美で飾った。
(舩木篤也)
公演データ
小山実稚恵 サントリーホール・シリーズ「Concerto~以心伝心」2025
10月12日 (日)16:00 サントリーホール 大ホール
ピアノ:小山実稚恵
指揮:ドミトリー・ユロフスキ
管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団&フェドセーエフ・フレンズ
プログラム
チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番 変ロ短調 Op.23
ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 Op.18
アンコール
チャイコフスキー:「四季」Op.37bis より10月〝秋の歌〟
ラフマニノフ:「パガニーニの主題による狂詩曲」Op.43より第18変奏
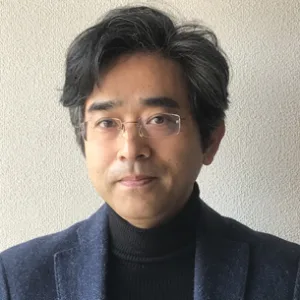
ふなき・あつや
1967年生まれ。広島大学、東京大学大学院、ブレーメン大学に学ぶ。19世紀ドイツを中心テーマに、「読売新聞」で演奏評、NHK-FMで音楽番組の解説を担当するほか、雑誌等でも執筆。東京藝術大学ほかではドイツ語講師を務める。著書に『三月一一日のシューベルト 音楽批評の試み』(音楽之友社)、共訳書に『アドルノ 音楽・メディア論』(平凡社)など。