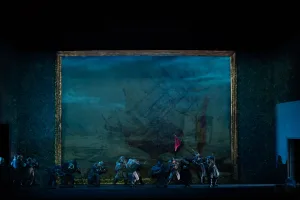音楽のみが立ち上がる「田園」、緻密かつ大胆な「春の祭典」――マルッキ&東響、四半世紀ぶりの再共演
アンサンブル・アンテルコンタンポランの音楽監督、ヘルシンキ・フィル首席指揮者(現在は名誉指揮者)、そしてロサンゼルス・フィル首席客演指揮者として国際的に活躍してきたスザンナ・マルッキが、東京交響楽団とおよそ四半世紀ぶりに再共演を果たした。

「田園」と「春の祭典」――自然という題材を共有しながら、時代と様式の対照が鮮やかな2作が並んだ。
ベートーヴェンの交響曲第6番「田園」は、音楽のみがみずみずしく立ち上がってくるようだった。ヴァイオリンはすっきりとして美しく、中低弦の厚みある響きが確かな基盤を築き、木管群のハーモニーが内声部に陰影と色彩を添える。それらの倍音がやわらかく全体に溶け込みながらも、響きの透明さと明晰(めいせき)さは終始保たれた。全体が自然で、湧き出る清水のように澄んだ流れが広がっていった。
第2楽章〝小川のほとりの情景〟は密やかで柔らかく、夢の中の光景のように展開した。第3楽章〝田舎の人たちの楽しい集い〟では、生き生きとしたリズムと自然なテンポの中で、木管やホルンのソロが快活に歌う。第4楽章〝雷雨、嵐〟では一気に激しさを増し、ティンパニと金管が力強く響きつつも、全体の均衡を失わない。終楽章〝牧人の歌、嵐の後の喜びと感謝の気持ち〟では清らかな流れが再び戻り、ホルンに導かれて温かく晴れやかに閉じられた。

ストラヴィンスキー「春の祭典」は、ベートーヴェンと同様に、細部まで明確に造形された演奏であった。そのうえで、この作品に潜む野性的な力と原始的な衝動が、緻密な構築の中で鮮やかに息づいていた。
第1部「大地礼賛」では〝序奏〟から〝春のきざし―乙女たちの踊り〟〝誘拐〟に至るまで、誇張を排した正確で丁寧な描写が貫かれた。その一方で、〝春の踊り〟の金管の咆哮(ほうこう)や銅鑼(どら)の強打、〝敵の都の人々の戯れ〟におけるティンパニと金管の応酬、〝長老の行列〟の大音響はいずれも強烈なインパクトを放つ。終曲〝大地の踊り〟は目も覚めるようなスピードと切れを備え、圧倒的な緊張のうちに締めくくられた。

第2部「いけにえ」の〝序奏〟では、木管・弦・金管のアンサンブルが緻密に組み上げられ、その正確さの中にマルッキの指揮の細やかさが発揮されていた。〝乙女たちの神秘的な集い〟のヴィオラ6重奏も繊細で、響きの層が美しく保たれていた。
2台のティンパニによる11連打で始まる〝選ばれしいけにえの賛美〟は変拍子が明確で、マルッキの指揮の冴(さ)えが際立つ。〝祖先の呼び出し〟を経て、〝祖先の儀式〟ではコーラングレ、アルトフルート、バストランペットのソロ、ベルアップするホルン群など、いずれも隙のない演奏であった。最後の〝いけにえの踊り〟のクライマックスでも、マルッキは正確なリズムとタイミングで東響を導き、そこには誇示も過度な演出も見られなかった。
ベートーヴェンでの深い音楽性、ストラヴィンスキーにおける緻密かつ大胆な構成力。 マルッキが作品の本質を捉える鋭い知性と柔軟な感性を併せ持つ名指揮者であることを、あらためて示した公演だった。
(長谷川京介)
公演データ
東京交響楽団 第735回定期演奏会
10月11日(土)18:00サントリーホール 大ホール
指揮:スザンナ・マルッキ
管弦楽:東京交響楽団
コンサートマスター:景山昌太郎
プログラム
ベートーヴェン:交響曲 第6番 ヘ長調 Op.68「田園」
ストラヴィンスキー:バレエ音楽「春の祭典」

はせがわ・きょうすけ
ソニー・ミュージックのプロデューサーとして、クラシックを中心に多ジャンルにわたるCDの企画・編成を担当。退職後は音楽評論家として、雑誌「音楽の友」「ぶらあぼ」などにコンサート評や記事を書くとともに、プログラムやCDの解説を執筆。ブログ「ベイのコンサート日記」でも知られる。