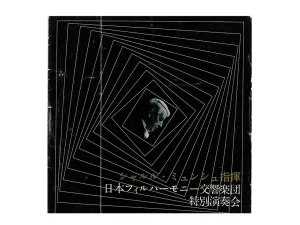辻井伸行、三浦文彰の日本の若手アーティストともに〝三刀流〟の妙技を披露したピンカス・ズーカーマン
ARKフィルハーモニックは、「サントリーホール ARKクラシックス」のレジデント・オーケストラとして2019年に「ARKシンフォニエッタ」の名称で発足し、編成の拡大に伴い、2024年に「ARKフィルハーモニック」に名称を変更した。三浦文彰がアーティスティック・ディレクターを、辻井伸行がレジデント・ピアニストを務めている。ソリストや国内オーケストラのコンサートマスター、首席奏者が多数参加。

「サントリーホール ARKクラシックス」の10月4日のARKフィルの公演は、「ピンカス・ズーカーマン」の芸術と題され、ズーカーマンが指揮を執った。
ヴァイオリンのレジェンド、ピンカス・ズーカーマンは、昔からヴィオラも弾く二刀流で知られている(指揮も加えると、三刀流である!)。この日のモーツァルトのヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲でも、ズーカーマンは、ヴィオラ独奏を披露し、指揮も務めた。ヴァイオリンの独奏は三浦文彰。三浦はズーカーマンのことを自らのメンターと言っている。ズーカーマンは、ヴィブラートをしっかりとかけて、温かみのあるヴィオラを聴かせてくれた。技巧も健在。三浦のヴァイオリンは艶があり、洗練されている。確かに二人の演奏スタイルは似ている。第2楽章では二人の寄り添うような対話が聴けた。

続いて、辻井伸行の独奏でモーツァルトのピアノ協奏曲第26番「戴冠式」。指揮はズーカーマン。辻井は、まろやかで純粋で清らかなモーツァルトの音を奏でる。まさに珠を転がすような美しさ。オーケストラは自発的で一体感もある。ソロ・アンコールのベートーヴェンのピアノ・ソナタ第8番「悲愴」の第2楽章もレガートで美しい演奏。
そして、最後にドヴォルザークの交響曲第8番。ズーカーマンは、音楽作りが自然で、流れが良い。オーケストラ(特に弦楽器)をよく歌わせる。ときに金管楽器を開放的に吹かせたりもする。第2楽章ではハッとするような弦楽器の弱音表現があり、第3楽章中間部でのヴァイオリンの表情豊かな歌に心動かされた。

カーテンコールが続くなか、ズーカーマンはオーケストラのメンバーのヴァイオリンを借りて、「シング・ウィズ・ミー」と言って、ブラームスの「子守歌」を弾き始めた。場内にその旋律を歌う(ハミングする)声が広がる。そして、ズーカーマンは「サヨナラ」と言って、演奏会を締めた。
(山田 治生)
公演データ
サントリーホール ARKクラシックス〔公演4〕
ARK PHILHARMONIC 1 「ピンカス・ズーカーマンの芸術」
ピアノ:辻井伸行
指揮&ヴィオラ:ピンカス・ズーカーマン
ヴァイオリン:三浦文彰
管弦楽:ARKフィルハーモニック
プログラム
モーツァルト:ヴァイオリンとヴィオラのための協奏交響曲変ホ長調 K. 364
モーツァルト:ピアノ協奏曲第26番ニ長調 K. 537「戴冠式」
ドヴォルザーク:交響曲第8番ト長調Op. 88
アンコール
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第8番Op. 88「悲愴」から第2楽章(辻井伸行)
ブラームス:「子守歌」(ピンカス・ズーカーマン)

やまだ・はるお
音楽評論家。1964年、京都市生まれ。87年、慶応義塾大学経済学部卒業。90年から音楽に関する執筆を行っている。著書に、小澤征爾の評伝である「音楽の旅人」「トスカニーニ」「いまどきのクラシック音楽の愉しみ方」、編著書に「オペラガイド130選」「戦後のオペラ」「バロック・オペラ」などがある。