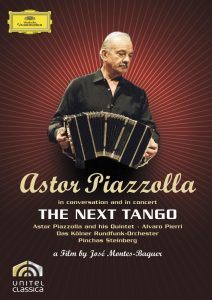N響との初共演でスケールの大きな演奏を聴かせ実力を示した米国出身の若手指揮者ライアン・バンクロフト
NHK交響楽団の9月定期からCプログラム2日目を聴いた。指揮は米国出身の新鋭、ライアン・バンクロフト。今年36歳、指揮者としては若手だが、既にロイヤル・ストックホルム・フィル首席指揮者、BBCウェールズ・ナショナル管首席指揮者の肩書を持ち、フィルハーモニア管、ロンドン・フィル、ベルリン・ドイツ響、ケルンWDR響、ボストン響など欧米の名門オケに客演を重ねる実力派。N響とは初共演。

この日の前半はバリトンのトーマス・ハンプソン(主催者表記=トマス)をソリストに迎えマーラーの歌曲集「こどもの不思議な角笛」から5曲を取り上げた。ハンプソンは現在70歳だが、あらゆる音域において声に伸びがあり、広いNHKホールをものともしない余裕のある歌いっぷりは年齢からの衰えをまったく感じさせない。過剰な表現は一切しないのだが、繊細なニュアンスに富んだ歌唱は作品の深層を掘り下げる味わい深いものであった。交響曲第4番の第4楽章に転用された〝天上の生活〟交響曲第2番第4楽章の原型となった〝原光〟は両交響曲完成後に歌曲集から外されているが、多くの聴衆にとってなじみ深い曲であり、演奏効果は抜群。盛大な喝采にハンプソンは「私にとって東京、とりわけこのNHKホールは最も好きな音楽空間のひとつです」との趣旨のメッセージを客席に投げかけ、同歌曲集から〝誰がこの歌を作ったか〟をオケとともにアンコールした。バンクロフトとN響はこの名歌手の歌唱を柔軟に、そしてデリケートなタッチで支えた。

後半は4部からなるシベリウスの交響詩「4つの伝説」。2曲目の〝トゥオネラの白鳥〟を除けば日本での演奏機会は多くはないが、全曲を通して聴くとこの作曲家の交響曲に勝るとも劣らない力作である。バンクロフトは現在、ストックホルム・フィルのシェフを務めているように彼のキャリアの中で北欧は重要な位置を占めており、シベリウスも得意としている。北欧の大自然を彷彿(ほうふつ)とさせるスケールの大きな音楽作りで、作品の世界観を分かりやすく示してくれた。実力のある指揮者が持ち合わせているオケを豊かに鳴らす力にも秀でており、この日のN響もよく鳴っていた。
コンサートマスター(川崎洋介)、チェロ首席(水野優也、ゲスト)、コールアングレ(和久井仁)には重要なソロが複数回出てくるのだが、いずれも表情豊かな妙技を披露。バンクロフトは終演後に楽団から贈呈された花束を和久井にプレゼントしてその健闘を讃えた。

今年のN響定期にはこの日のバンクロフトやペトル・ポペルカ(2月)、タルモ・ペルトコスキ(6月)といったライジング・スターともいうべき若手指揮者が初登場し、充実した演奏を聴かせているが、選曲も含めてとてもよい方向性だと、この日の熱演からも実感することができた。
(宮嶋 極)

公演データ
NHK交響楽団 第2044回定期公演 Cプログラム2日目
9月27日(土)14:00 NHKホール
指揮:ライアン・バンクロフト
バリトン:トーマス:ハンプソン(主催者表記=トマス)
管弦楽:NHK交響楽団
コンサートマスター:川崎 洋介
プログラム
マーラー:
「こどもの不思議な角笛」から
〝ラインの伝説〟〝トランペットが美しく鳴り響くところ〟〝浮世の生活〟
〝天上の生活〟〝原光〟
シベリウス:交響詩「4つの伝説」Op.22
アンコール
マーラー:「こどもの不思議な角笛」から〝誰がこの歌を作ったか〟(ソリスト&オーケストラ)
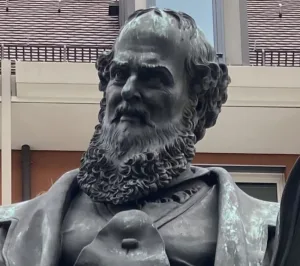
みやじま・きわみ
放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。