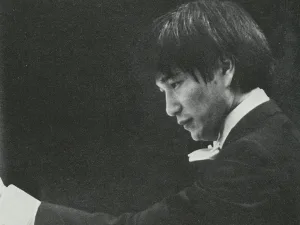寄せては返す波のような感情を高い透明度で再現
ヴァルチュハ(1976年スロヴァキア・ブラティスラヴァ生まれ)は2022年の初共演で「交響曲第9番」、2024年の首席客演指揮者就任記念で「第3番」を振り、今回も「大地の歌」なので、読響の「マーラー番」といえる存在だ。ヨーロッパではオペラ指揮の実績もあり、「トリスタンとイゾルデ」全曲はベルリン・ドイツ・オペラで経験済み。2022年からはヒューストン交響楽団の音楽監督を務め、今回のソリスト2人にも新進気鋭の米国人歌手を起用するなど、自身の多彩な側面を散りばめたプログラムとなった。

編成は16型(第1ヴァイオリン16人)で、配置は通常のアメリカ型。「トリスタン」が始まると、濃厚なロマンよりも揺れ動く感情の切なさが前面に出て、透明度の高い弦の響きが木管楽器のソロをくっきりと際立たせる。イングリッシュホルンの北村貴子、オーボエの荒木奏美、クラリネットの中舘壮志らの妙技が光る。ヴァルチュハは次第に音の振幅を拡大し、クライマックスにかけて息の長いアーチを築いた。「愛の死」では繊細さがさらに徹底、寄せては返す〝うねり〟の中に愛のドラマを美しく描いた。
「大地の歌」は「トリスタン」の約半世紀後に書かれた作品だが、「愛と死」あるいは「生と死」の対比を共有する。ヴァルチュハもアプローチの基本は変えず、室内楽のようにトランスパレント(明瞭)な音の線を丁寧に重ね、全体のバランスにも絶えず気を配りながら歌詞の内容に即した響きを読響から引き出していく。第3曲「青春について」のユーモラスなタッチの強調が象徴したように、全体に過度の重さを慎重に避けたアプローチだった。荒木や中舘に加え、フルートのフリスト・ドブリノヴ、ヴァルチュハがベルリン・コンツェルトハウス管弦楽団首席客演指揮者だった時代(2017〜23年)から旧知の間柄であるコンサートマスターの日下紗矢子らが傑出したソロを聴かせた。

独唱者の人選、歌い方については客席の意見が分かれた。ドイツ=オーストリア圏の有力歌劇場や世界的音楽祭で急速に地歩を固めつつあるヘルデン(英雄的)テノールのクレイ・ヒリーは輝かしい声と巨大な声量を駆使して、歌詞の明暗をくっきりと歌い分ける。半面、あまりにオペラ的なアプローチと仕草は、ドイツ・リート(ドイツ語歌曲)の解釈者として「いかがなものか?」と疑問視される隙を与えた。ヴァルチュハのつくる響きと透明度で一致するメゾ・ソプラノ、サーシャ・クックはやや古風な歌のドイツ語(ゲザングドイッチュ)で深く内面を掘り下げ、たっぷりとした余韻を残す。第6曲「告別」ではクリスタルな声が室内楽的な管弦楽ともども浄化の世界を極め、結びの言葉の「ewig(エーヴィヒ=永久に)」にも大袈裟ではない、しみじみとした思いをこめた。ただ、時折フレージングが短めになる点には改善の余地があるかもしれない。2人の人選も含め、ヴァルチュハが諦念の側面ばかり強調されがちな作品を現代のセンスで洗い直し、陰と陽を明確に対比させたアプローチは明快であり、成功を収めたといえる。
(池田卓夫)

公演データ
読売日本交響楽団 第685回名曲シリーズ
8月19日(火)19:00サントリーホール 大ホール
指揮:ユライ・ヴァルチュハ(首席客演指揮者)
メゾ・ソプラノ:サーシャ・クック
テノール:クレイ・ヒリー
管弦楽:読売日本交響楽団
コンサートマスター:日下紗矢子
プログラム
ワーグナー:楽劇「トリスタンとイゾルデ」から前奏曲と愛の死
マーラー:大地の歌

いけだ・たくお
2018年10月、37年6カ月の新聞社勤務を終え「いけたく本舗」の登録商標でフリーランスの音楽ジャーナリストに。1986年の「音楽の友」誌を皮切りに寄稿、解説執筆&MCなどを手がけ、近年はプロデュース、コンクール審査も行っている。