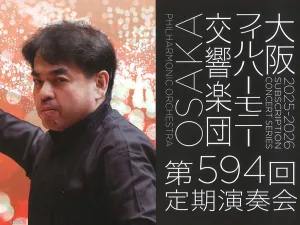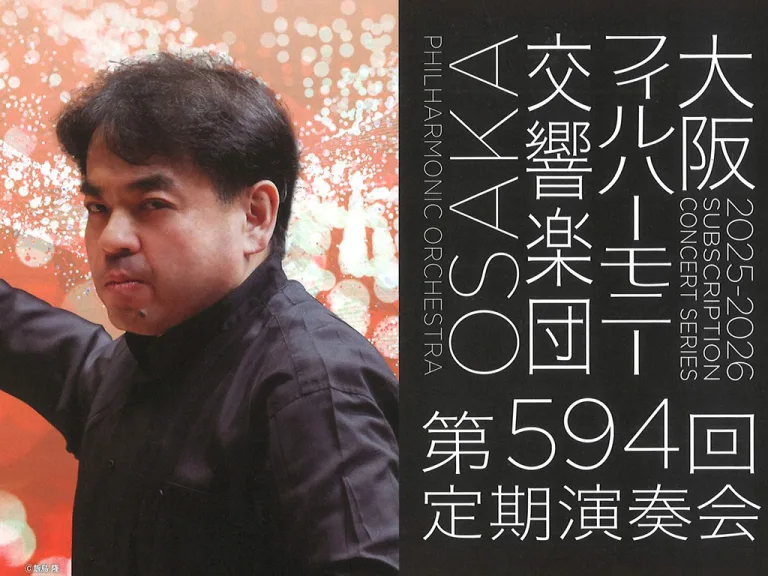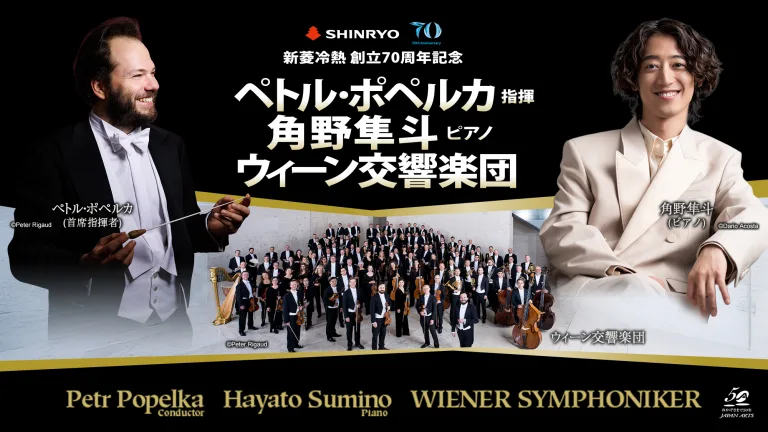知的なコントロールを徹底した、端正でクールな演奏
活況を呈する日本の若い室内楽グループをけん引する一員となったクァルテット・インテグラが、結成10周年を迎えた。2022年のARDミュンヘン国際音楽コンクールで2位に輝いた後、チェロ奏者が交代し、昨春にパク・イェウンを正式にメンバーへ迎えたばかり。活躍の場は広がる一方だ。定期的に登場するTOPPANホールでは今回、第一次世界大戦を起点とした東欧やウィーンに焦点を当てるハードなプログラムに挑んだ。

4人の微妙な均衡のうえに成り立つ弦楽四重奏団にとって、メンバー交代は重大な局面。新たな顔ぶれが固まったことで、第1ヴァイオリンの三澤響果を核に、第2ヴァイオリンの菊野凛太郎とヴィオラの山本一輝が内声をがっちり固める構図に対し、パク・イェウンは一段と存在感を高めて振る舞うようになり、合奏の熟成度が上がった。
冒頭に置かれたバルトークの弦楽四重奏曲第2番は第一次世界大戦中に書かれ、無調的な響きも醸す難物。同団はこの曲を含むライヴCDを出すなど、すっかり手の内に収めている。当夜も自然な呼吸あふれる精緻なアンサンブルで、モダンな曲想を丹念にあぶり出した。時折現れる民俗的なイディオムの扱いはむしろ淡泊で、急速な第2楽章でも余裕をもって滑らかに運動性を引きだした。

こうした特徴はヤナーチェクの傑作、弦楽四重奏曲第1番「クロイツェル」で、さらに明確になった。高い解像度で作品の構造を緊密に示し、知的なコントロールを徹底するので、端整でクールな印象が強まる。他方、この曲特有の渦巻く情念や土臭い民俗性は控えめで、バルトークからつながる現代性を強く意識させた。
その流れが後半のベルク「抒情組曲」へなだれ込んだ。12音音階を駆使した新ウィーン楽派の名品だ。生乾きの前衛性が過去の遺物となった21世紀ならば、演奏解釈は大きく変わりうる。同団は自然体で曲を自分たちに引き寄せ、生硬さを一切感じさせない流麗なアプローチでうならせた。
第1楽章〝快活なアレグレット〟から流動感の強いテクスチュアをたたえ、「古典の額縁」へ収めるのに成功。〝狂気のプレスト〟と称された第5楽章も整然と処理し、緊張感を保ちつつ息苦しさのない希有なスタイルを見せつけた。全体に官能性や濃やかな情動が増すと、次のフェーズが開けてくるだろう。

米国での研さんを終えた彼らは、さらに海外で腰を据えて活動する計画があるようだ。若手団体のホープとして、どう熟成を深めるのか楽しみだ。
(深瀬満)
公演データ
クァルテット・インテグラ II
8月5日(火)19:00 TOPPANホール
クァルテット・インテグラ
ヴァイオリン:三澤響果
ヴァイオリン:菊野凜太郎
ヴィオラ:山本一輝
チェロ:パク・イェウン
プログラム
バルトーク:弦楽四重奏曲第2番 Sz67(1915-17)
ヤナーチェク:弦楽四重奏曲第1番「クロイツェル・ソナタ」(1923)
ベルク:抒情組曲(1925-26)
アンコール
ハイドン:弦楽四重奏曲 ロ短調Op.33-1 Hob.Ⅲ-37より第4楽章 Finale (Presto)

ふかせ・みちる
音楽ジャーナリスト。早大卒。一般紙の音楽担当記者を経て、広く書き手として活動。音楽界やアーティストの動向を追いかける。専門誌やウェブ・メディア、CDのライナーノート等に寄稿。ディスク評やオーディオ評論も手がける。