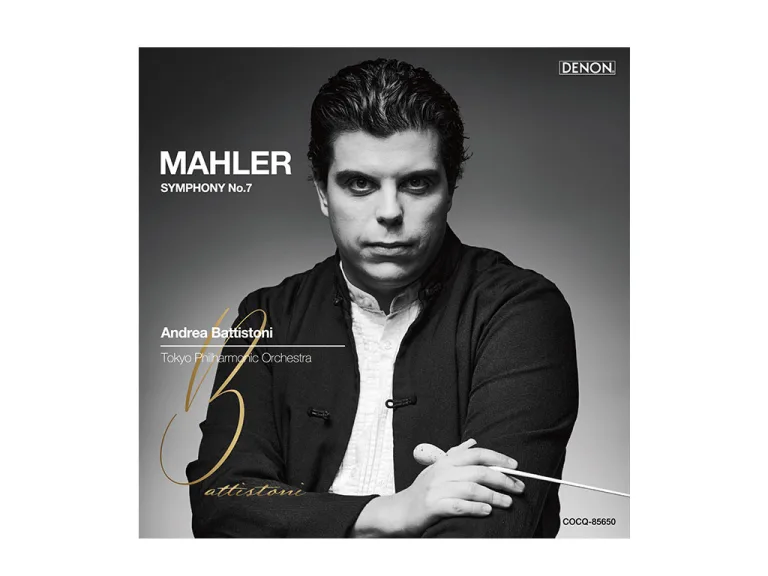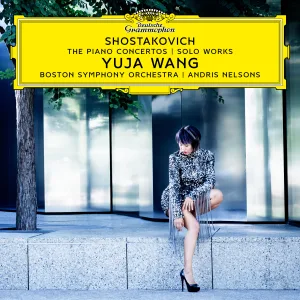フランスの「鏡」に映し出されたアメリカとスラヴ
旧大陸のヨーロッパと新大陸のアメリカ、ヨーロッパ内部の西と東。それぞれ長く対立概念で語られてきたが、交通や通信の手段が飛躍的に発達した20世紀を通じ、相互に緊密な影響を及ぼし合うようになった。アメリカの作曲家&指揮者レナード・バーンスタインはニューヨーク・フィルハーモニック音楽監督を辞任後、ヨーロッパでの活動を増やし、晩年はフランス国立管弦楽団への客演指揮でも人気があった。ガーシュウィンはストラヴィンスキーやラヴェルだけでなくベルクを深く研究、ジャズとクラシックの融合以上に独自の管弦楽を生んだ。カンブルランが指揮した「キャンディード」序曲は、日本のテレビ番組のテーマにも使われた主旋律の部分を洗練の極みでさらりと歌わせ、弦と管のバランスにも独自性をみせながら、軽やかなユーモアのセンスでも魅了した。

フランスの中堅ドゥ・ラ・サールのピアノは往年の名手モニック・アースを彷彿とさせる堅実なテクニック、確かな教養に裏打ちされた中庸の美徳を備える。指揮者ともども、ガーシュウィンが苦心の末に獲得した書法を克明に再現し、ピアノ協奏曲に古典の格調を与えた。ソロの出だしにはモーツァルトの協奏曲を思わせる潤いがあり、強打も絶対に無機的に響かせず、花びらが舞うような煌めきをみせる。第3楽章の激しい連打も鮮やかさで際立ち、暑苦しさの真逆のクールさで魅了した。アンコールは「今の世界に生きる人々の愛と平和のために」と前置きした後、メシアン初期の作品を静かに弾いた。

後半はハンガリーのバルトーク、ロシアのムソルグスキーと「東」の音楽。弦楽合奏による「ルーマニア民族舞曲」はカンブルランが常任指揮者だった時代から読響とともに培った音の個性、良く歌うが音色とアーティキュレーションが鮮明で決してもたれない弦の特性がフルに発揮された。この1曲が西から東へ進む〝橋〟の役割を果たし、さらに東方のロシア音楽へと進むが、カンブルランはラヴェル編曲の色彩感を的確に押さえ、フランスの「鏡」に映し出されたムソルグスキーの心象風景を描いた。ラヴェル版一般の演奏よりも角(かど)が取れ、レガート(滑らかさ)を基調に、要所要所を締める行き方。管楽器はもとより、コンサートマスター林悠介のソロも美しく浮かび上がった。
(池田卓夫)

公演データ
読売日本交響楽団 第684回名曲シリーズ
7月15日(火)19:00サントリーホール 大ホール
指揮:シルヴァン・カンブルラン
ピアノ:リーズ・ドゥ・ラ・サール
管弦楽:読売日本交響楽団
コンサートマスター:林悠介
プログラム
バーンスタイン:「キャンディード」序曲
ガーシュウィン:ピアノ協奏曲 へ調
バルトーク:ルーマニア民俗舞曲(弦楽合奏版)
ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲「展覧会の絵」
ソリスト・アンコール
メシアン:「おお、聖なる饗宴よ」O Sacrum Convivium

いけだ・たくお
2018年10月、37年6カ月の新聞社勤務を終え「いけたく本舗」の登録商標でフリーランスの音楽ジャーナリストに。1986年の「音楽の友」誌を皮切りに寄稿、解説執筆&MCなどを手がけ、近年はプロデュース、コンクール審査も行っている。