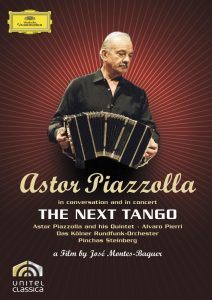フォルテピアノの名手とピリオド楽器オーケストラが織りなす、典雅で豊かな古典派音楽の世界
フライブルク・バロック・オーケストラがフォルテピアノのベザイデンホウトと来日。トッパンホールにおける2公演の初日を聴いた。

1曲目はモーツァルトのオペラ「偽の女庭師」から序曲。オーケストラがステージに登場すると音合わせをせず、いきなり弾き始める。まさにアレグロ・モルトの快速テンポで「fp」を際立たせ、ヴィオラと低弦の8分音符を推進力に疾走。中間部はゆったりとしたテンポで表情豊かに歌い、コンサートマスターのフォン・デア・ゴルツが即興的な短いパッセージを弾いて主部に戻ると、アンサンブルは一段と引き締まって強靭に。演奏が終わって拍手を待たずにハイドンの交響曲第74番の第1楽章。ここでも主要主題のフォルテとピアノが明快に示され、各セクションがぴたりと揃う。第2楽章は弦の柔らかな音色と人間味あふれるフレージングが快く、メヌエット楽章は質朴な味わい。トリオのファゴットとチェロの惚(とぼ)けた表情が面白い。終楽章は主題前半の惚けた表情と、全休止を挟んだ情熱的な後半部との対比や転調、強弱など、ハイドンの様々な仕掛けを印象深く示しつつ、猛烈な速さで突き進む。

ここでベザイデンホウトが登場。オーケストラの念入りなチューニングののちに協奏曲第17番。冒頭のアインザッツもそうだが、フォン・デア・ゴルツがオーケストラをリードして肌理濃(きめこま)やかに表情をつける。一方ソリストも要所で合図を送る。緩徐楽章の音量のバランスが絶妙。終楽章は椋鳥(ムクドリ)の囀(さえず)りを想起させて楽しい(とくに管楽器)。ベザイデンホウトのフォルテピアノの多彩な音色や繊細な表現は定評があるが、長年同団の首席客演芸術監督を務めているだけあって、オーケストラと一体となってスコアから引き出す情報量の多さに驚かされる。ソロは所々即興的なパッセージを鏤(ちりば)め、カデンツァはモーツァルト自身のオリジナルにベザイデンホウトが手を加えたものを弾いた(後半の第9番も同様)。

休憩後のJ.C.バッハのト短調の交響曲。冒頭、ガット弦がトゥッティで奏でるサウンドがすばらしい。硬めの子音で低音は深みがあり、暗いパッションが渦巻く。緩徐楽章は多様なアーティキュレーションや和声、強弱が表情豊かな語りを思わせ、終楽章の凄まじい緊迫感は、まさに同曲の疾風怒濤の精神そのもの。あっけない終わり方は何かの問いかけのようだ。
そして再びモーツァルトのピアノ協奏曲第9番「ジュノム(ジュナミ)」。第1楽章はフォルテピアノのレガートと歯切れのよい弦の刻みが立体的な響きの構造を浮かび上がらせ、緩徐楽章は両者の丁寧な弾き込みと繊細な表現が美しい哀愁と陰影をもたらす。終楽章はソロの流麗なパッセージとともにダイナミックに弾き進められ、中間部は静かな舞のよう。最後は両者一丸となって猛スピードで駆け抜けていく。アンコールはベザイデンホウトがモーツァルトの「アルマンド」を弾き、静謐(せいひつ)な余韻を残してコンサートを終えた。
(那須田務)
公演データ
フライブルク・バロック・オーケストラ withクリスティアン・ベザイデンホウト(フォルテピアノ) 第1夜
4月3日(木)19:00トッパンホール
フォルテピアノ:クリスティアン・ベザイデンホウト
管弦楽:フライブルク・バロック・オーケストラ
コンサートマスター・音楽監督:ゴットフリート・フォン・デア・ゴルツ
プログラム
モーツァルト:オペラ「偽の女庭師」K196より序曲
ハイドン:交響曲第74番 変ホ長調Hob.I-74
モーツァルト:ピアノ協奏曲第17番ト長調 K453
ヨハン・クリスティアン・バッハ:交響曲ト短調 Op.6-6
モーツァルト:ピアノ協奏曲第9番 変ホ長調 K271「ジュノム」
ソリスト・アンコール
モーツァルト:ピアノのための組曲ハ長調K399(385i)より「アルマンド」

なすだ・つとむ
音楽評論家。ドイツ・ケルン大学修士(M.A.)。89年から執筆活動を始める。現在『音楽の友』の演奏会批評を担当。ジャンルは古楽を始めとしてクラシック全般。近著に「古楽夜話」(音楽之友社)、「教会暦で楽しむバッハの教会カンタータ」(春秋社)等。ミュージック・ペンクラブ・ジャパン理事。