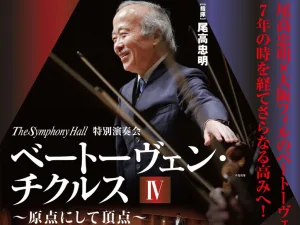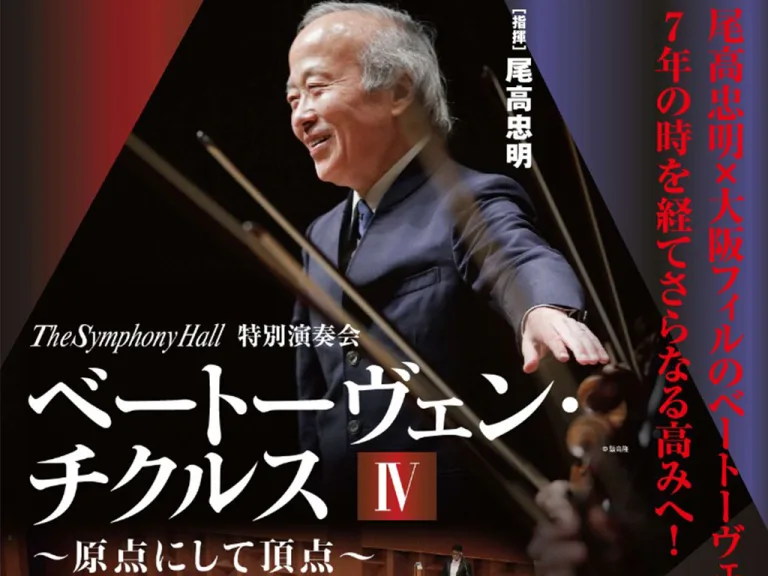伝統あるオーケストラによる折り目正しいアンサンブル
ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団は、その起源を1827年に遡る伝統あるオーケストラ。であると同時に、若い人材の登用にも積極的で、2月12日のコンサートでも、コンサートマスターの隣の席に弓新が座り、第2ヴァイオリンの首席奏者を大江馨が務めていた。

ギュルツェニヒ管はオペラハウスとコンサートホールとの両方で活躍するケルン市のオーケストラということで、この日は、まず、オペラの序曲として、ウェーバーの歌劇「オベロン」序曲が演奏された。フィンランド出身のサカリ・オラモが熱気のある明確な指揮。冒頭のホルンのソロから美しく、折り目正しいアンサンブルによる立派な演奏。2025/26年シーズンからギュルツェニヒ管弦楽団のアーティスティック・パートナーを務めるオラモと同楽団との相性の良さが示された。

続いて、諏訪内晶子の独奏で、ブルッフのヴァイオリン協奏曲第1番。諏訪内は、第1楽章からヴァイオリンをたっぷりと鳴らし、歌わせる。技巧的にも冴えている。第2楽章はスケールの大きなカンタービレ、第3楽章も鮮やかで、まさにロマン派協奏曲の王道を行く演奏を繰り広げた。諏訪内とオラモは2002年にシベリウスとウォルトンのヴァイオリン協奏曲の録音を行っている。お互い信頼感があるのだろう。オラモは伴奏に終わらないサポート。ソロ・アンコールでは、諏訪内が、J.S.バッハの無伴奏ヴァイオリン・ソナタ第3番のラルゴを、軽妙なボウイングで清らかに弾く。

後半は、ベートーヴェンの交響曲第7番。オラモは熱のこもった指揮で、推進力のある音楽を繰り広げる。弦楽器の内声部をしっかりと鳴らし、音に厚みがある。終楽章は、テンポの変化でメリハリをつけ、最後はボルテージをあげて全曲を締め括った。アンコールのベートーヴェンの「プロメテウスの創造物」序曲でもベートーヴェンに相応しい熱量と整然としたアンサンブルが披露された。
(山田治生)
公演データ
ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団 日本ツアー 東京公演2日目
2月12日(水) 19:00サントリーホール
指揮:サカリ・オラモ
ヴァイオリン:諏訪内晶子
管弦楽:ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団
プログラム
ウェーバー:歌劇「オベロン」序曲 J.306
ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲 第1番ト短調 Op.26
ベートーヴェン:交響曲 第7番イ長調Op.92
ソリスト・アンコール
J.S.バッハ:無伴奏ヴァイオリンのためのソナタ第3番 BWV1005よりNo.3ラルゴ
アンコール
ベートーヴェン:バレエ音楽「プロメテウスの創造物」Op.43より序曲
※来日ツアーのその他の公演日程、プログラム等の詳細については、下記ホームページをご参照ください。
サカリ・オラモ指揮 ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団 | クラシック音楽事務所ジャパン・アーツクラシック音楽事務所ジャパン・アーツ

やまだ・はるお
音楽評論家。1964年、京都市生まれ。87年、慶応義塾大学経済学部卒業。90年から音楽に関する執筆を行っている。著書に、小澤征爾の評伝である「音楽の旅人」「トスカニーニ」「いまどきのクラシック音楽の愉しみ方」、編著書に「オペラガイド130選」「戦後のオペラ」「バロック・オペラ」などがある。