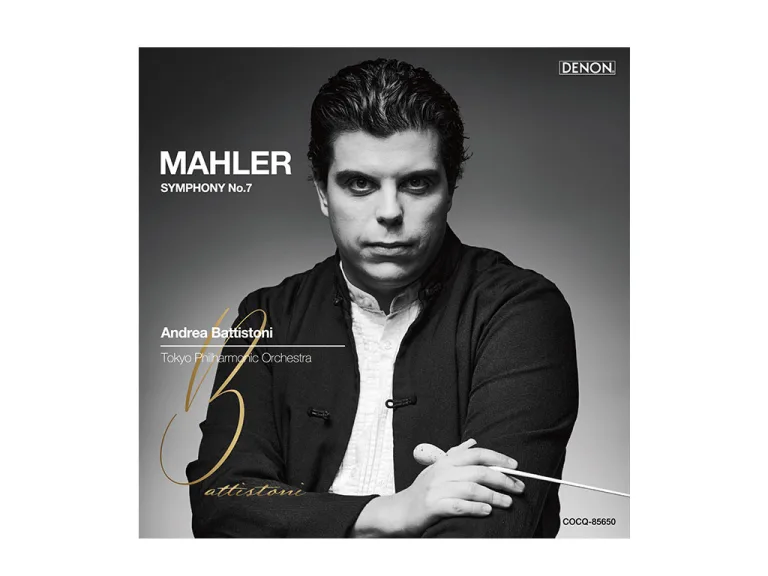加藤のぞみとシラグーザの驚異の歌唱
前回、6月13日にサルデーニャ島のカリアリで鑑賞したドニゼッティ「ラ・ファヴォリータ」について、途中まで報告した。騎士フェルナンドが惹かれ、王アルフォンソ11世から結婚を許された女性は、実は王の愛妾だったという話で、ファヴォリータとは愛妾を意味する。表題役のレオノーラ役を歌った加藤のぞみ(メゾソプラノ)が、力強くエレガントな歌唱で東洋人の癖もまったく感じさせず、フェルナンド役のアントニーノ・シラグーザ(テノール)と互角に渡り合ったことはすでに記した。

そのシラグーザも驚異的だった。声が明るく瑞々しく、61歳にして30代に聴こえる。昨年10月、新国立劇場の「夢遊病の女」では変わらない声に驚いたものの、超アクートでの音質の変化が気になった。だが、この日はそれもない。フェルナンドは初役だが、声に力強さが増して劇的な表現も充実し、それでいてレガートは伸びやかで優美だ。アリア「やさしい魂よ」もソットヴォーチェのやわらかい表現とフォルテの間を自在に往来し、輝かしいハイCを延々と輝かせた。
アルフォンソ役のダミアーノ・サレルノ(バリトン)の品位ある歌唱、修道院長バルダッサーレのラマズ・チクヴィラーゼ(バス)の深い響きなど、ほかの歌手陣も充実。舞台となる教会や修道院、宮殿等をリアルに見せ、歴史的な美しい衣装で飾り、演劇的にも充実したアレックス・アギレラの演出の下、バランスのよい声の競演が味わえた。
一方、ベアトリーチェ・ヴェネツィという若い女性の指揮は、ドニゼッティらしいエレガンスより劇性が強調され、1970年代までの録音でよく聴くタイプの演奏で、慣習的カットが多く施された。そもそもオリジナルの仏語版が全盛の中、伊語版での上演は珍しい。伊語版ではフェルナンドがバルダッサーレの息子になるなど、内容に矛盾が生じており、近年は避けられている。だが、作曲家の存命中から上演されてきた版なので、矛盾を体感するためにも上演する価値はあると思う。

ロッシーニ唯一の「純粋なブッファ」の潜在力が引き出された
前後するが、6月12日にローマ歌劇場でロッシーニ「アルジェのイタリア女」を鑑賞した。指揮はセスト・クァトリーニ。2月にナポリのサン・カルロ劇場で聴いたグノー「ロメオとジュリエット」も、シャープな音運びでリリシズムが強調され、よい印象が残っていた。この日も軽やかさの中に溌溂とした楽しさをからめる秀演だった。
イタリア女イザベッラ役はキアーラ・アマル(メゾソプラノ)。元来、すぐれたロッシーニ歌手で、相変わらずどの音域も安定し、技巧的にも申し分ない。強烈なインパクトはない分、上品で音楽的水準が高い。こうしたエレガンスはベルカント、とりわけロッシーニの歌唱に欠かせない。

アルジェの地方総督ムスタファ役のパオロ・ボルドーニャ(バスバリトン)は、新国立劇場の「セビリャの理髪師」(2020年)のバルトロなど、喜劇的な役を聴いてきたが、ムスタファは深い響きもほしい役。大きく深い響きをつくりつつ滑稽味も柔軟に加え、軽重のバランスが秀でていた。リンドーロのダーヴェ・モナコ(テノール)は、昨年10月にピアチェンツァで聴いたロッシーニ「エジプトのモーゼ」のオシリデ役が秀逸だったが、この日も瑞々しい歌唱で、アジリタの切れ味も冴えた。
ロッシーニのオペラで純ブッファなのは、「アルジェのイタリア女」だけだと思う。マウリツィオ・スカパッロの演出は初演時にも観たが、奇をてらわずに音楽と脚本が内包する楽しさを引き出しながら、パッパターチの場面でみなスパゲッティを食い散らかすなど、弾けるところは弾ける。つまり作品の潜在力が味わえる。そういう演出だと終演後も心地いい。


かはら・とし
音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。