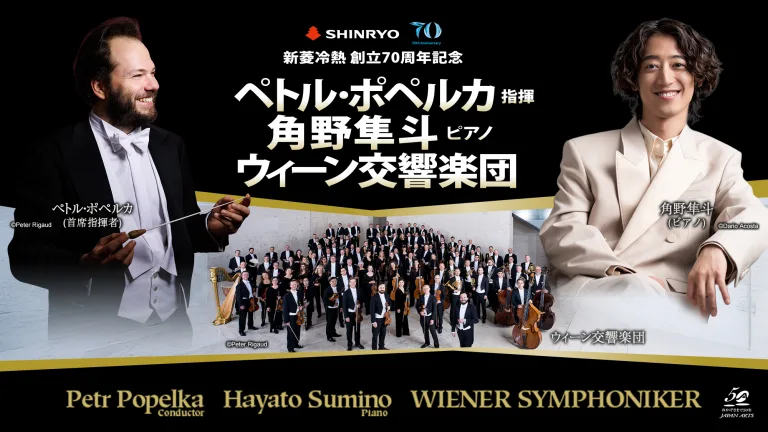大阪フィルの第591回定期演奏会(9月26、27日開催)には名指揮者トーマス・ダウスゴーを迎える。デンマークを代表する指揮者だ。
各地のオーケストラのポジションを歴任しているマエストロだが、日本ではBBCスコテッシュ響との関係が有名だろうか、それともやはり首席指揮者を務めたデンマーク国立放送響だろうか。レパートリーが広く古典から現代まで何でもこなす。それゆえにレコーディングも多い。ニールセンの交響曲は音楽監督を務めたシアトル響で全集を録っている。ナクソス・ミュージック・ライブラリーでも聴けるので、ぜひ予習も兼ねて聴いていただきたい。

さて、今回ダウスゴーにオファーした時からメインには「不滅」を据えるつもりでいた。アーティスト・イン・レジデンスのダニエル・オッテンザマーも来日出来る。ならばニールセンの協奏曲だ。ダウスゴーに伝えると、じゃあ「ヘリオス」序曲を最初にやろうよと返事が来た。自然にニールセン・プログラムが整う。
大阪フィルにはカール・ニールセンの作品はレパートリーに無いと言って過言ではない。魅力的な交響曲を6つも残しているのに、だ。手元の1990年以降の演奏記録では、交響曲第4番「不滅」を1996年9月の第301回定期演奏会で秋山和慶の指揮で取り上げている(ちなみにこの演奏会の前半はブラームスのピアノ協奏曲第2番、独奏はモーラ・リンパニーという素敵なプログラムだった)。あとは2007年に小組曲という弦楽のための作品を沼尻竜典が取り上げているだけだ。意識したわけではなかったがカール・ニールセンの生誕160周年の年に、大阪フィルにとっては歴史的なニールセン・プログラムが実現することになった。

序曲「ヘリオス」は曲目解説を読んでから鑑賞いただきたい。ニールセンがエーゲ海を旅した時の太陽の美しさを音楽で表した作品である。ヘリオスとはギリシャ神話の太陽神のことで、この作品は三部形式で日の出~真昼~日没を描いている。ホルンの美しさが印象に残るが、作曲者は太陽をホルンで表したともいわれている。
大阪フィルとの関係がさらに密度を増しているアーティスト・イン・レジデンスのダニエル・オッテンザマーは、今回演奏するクラリネット協奏曲をソロ、オーケストラともに難しい作品だと語る。ファゴット2、ホルン2、小太鼓、そして12型の弦5部という小ぶりな編成のオーケストラと親密なアンサンブルが展開されそうだ。オケ中の小太鼓が印象的なこともあらかじめ伝えておきたい。ダニエルは自身が所属するウィーン・フィル(指揮:アダム・フィッシャー)との録音もあるので、こちらもぜひ聴いていただきたい。
ニールセンの代表作の交響曲第4番は「不滅」というタイトルが印象的だ。デンマーク語でのタイトルは”Det Uudslukkelige” 。日本語に訳すと「消し去り難きもの」という意味だ。1914年の第1次世界大戦の勃発後に書かれ、戦争や混乱の中でも、生命そのものの力は決して滅びないという、ニールセンの強い意志を表している。ゆえにオーケストラに要求されるテンションは非常に高く、大阪フィルの高いポテンシャルが大いに発揮されるだろうと期待している。二群のティンパニが活躍するが、ニールセンは第2ティンパニを客席に近いところに置くように指示している。今回は上手側のヴィオラの後ろ側にセットする予定だ。この配置での第4部の2群のティンパニの掛け合いは壮絶に違いない。そして、この第2ティンパニが最後のフレーズを打つとき、聴衆は感動の渦に包まれるはずだ。この感動と興奮を、ぜひ客席で体験していただきたい。
山口 明洋(大阪フィルハーモニー交響楽団 演奏事業部長)
公演概要
大阪フィルハーモニー交響楽団第591回定期演奏会
9月26日(金)19:00、27日(土)15:00 フェスティバルホール(大阪)
指揮:トーマス・ダウスゴー
クラリネット:ダニエル・オッテンザマー
ニールセン:序曲「ヘリオス」Op.17
ニールセン:クラリネット協奏曲Op.57
ニールセン:交響曲 第4番「不滅」Op.29
主催者ホームページ 大阪フィルハーモニー