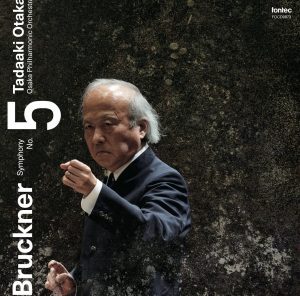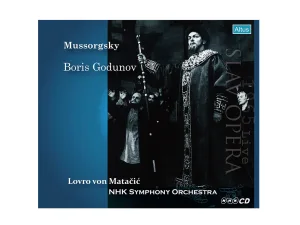東京・春・音楽祭の中心企画のひとつである「リッカルド・ムーティ イタリア・オペラ・アカデミー」が2日から15日の間、開催された。5回目となる今年はヴェルディ中期の傑作「シモン・ボッカネグラ」を題材に若手指揮者、歌手、東京春祭オーケストラのメンバーがムーティの指導を受けながら演奏会形式の公演を作り上げていった。15日に行われた国際的に活躍する歌手たちを招いてのムーティ指揮による「シモン・ボッカネグラ」の公演を中心にアカデミー全体を振り返る。
(宮嶋 極)
リッカルド・ムーティ指揮「シモン・ボッカネグラ」
取材したのは15日、東京音楽大学100周年記念ホールでの締めくくりの公演。
アカデミーの期間中、報道陣にも公開されたリハーサルでムーティは「(オペラは)歌手、合唱、オーケストラが一体となって演奏(上演)されなければいけない」と説いていたが、この日、彼は完璧な形でそれを実践してみせた。その言葉の通り独唱歌手、合唱、オケが混然一体となって創出した音楽空間は終始、高い集中度を維持しながら、起伏に富んだ表現が次々と繰り出され、圧巻のひと言に尽きた。演奏会形式にもかかわらず眼前で芝居が行われているかのような説得力に富んでいた。
オペラの世界でこうした状況を創り出すことができる指揮者は筆者が知る限り、イタリアもの、とりわけヴェルディにおいてはムーティ、そしてワーグナーではクリスティアン・ティーレマンくらいだと思う。

東京春祭オーケストラも大健闘していた。事実上の初リハーサルとなる2日の作品解説会では、いつもの春祭オケに比べてメンバーが若く、コンサートマスターの長原幸太(N響第1コンマス)を除くと常連ともいえる在京オケ首席クラスはほとんど参加しておらず、ムーティの指示や修正もいつにも増して細部にわたって行われており、少し不安を覚えたものだ。
ところが、解説会の約2時間でも、ムーティが指示を与えるたびに演奏はブラッシュアップされていった。さらにそこから2週間足らずしか経過していない最終公演では、名門オペラ劇場のオケのような質感の演奏を披露したのには驚きを禁じ得なかった。オーケストラ・ビルダーとしてのムーティの高い実力と情熱がなせる業であろう。


とにかく歌も含めて音の強弱、テンポの緩急の幅が広い。とりわけ弱音における微細なニュアンスを湛えた表現の数々は登場人物の心の内側を状況に応じて巧みに描き分ける多彩さであった。弱音の表現が冴えわたることに比例して強音の効果も大きくなり結果としてダイナミックさと繊細さを兼ね備えた演奏に仕上がった。
歌手の粒も揃っていた。題名役のジョルジュ・ペテアンは苦悩の心中をデリケートに表現。フィエスコ役は当初、イルダール・アブドラザコフと発表されていたが家族の事情で来日出来なくなり、ミケーレ・ペルトゥージに交代。これがかえって良い効果をもたらしていたように思う。何しろフィエスコは特に本編に入ってからは老人であり、ペルトゥージの渋さの中にも暗い怨念が伝わってくる歌唱は劇的なリアリティーに富んだものであったからだ。アメーリア役のイヴォナ・ソボトカ、アドルノ役のピエロ・プレッティも伸びのある豊かな声を駆使してムーティの要求に的確に応える表情豊かな歌唱を聴かせてくれた。すべての演者がムーティのタクトのもと、一体となって作品の本質に肉薄した滅多に聴くことのできない名演であった。

リッカルド・ムーティ presents 若い音楽家による「シモン・ボッカネグラ」
11日に行われた若い音楽家による「シモン・ボッカネグラ」ではアカデミーの期間中、ムーティの指導を受けた若手指揮者5人が交代で指揮し、シモン・ボッカネグラを栗原峻希、アメーリアを吉田珠代と日本の実力若手歌手がソリストを務めて演奏会形式で上演された。指揮の分担は公演データに記載したとおりたが、第1幕のフィナーレを担当した中国のウェイ・リンが筆者には最も強い印象を残した。彼にはオケからパワーを引き出す力が備わっており、幕切れに向けての高揚の築き方が上手かった。対する佐藤瑛吾(第2幕)、町田謙太郎(第3幕)の日本の2人は少し生まじめすぎるように感じた。リハーサルでもムーティは右手で丹念に拍子を刻む若手指揮者たちに「(指揮の)振りは自分が(拍子を)表現するのではなく、音楽をいかに表現するのかが重要。指揮法の本の著者はたいていの場合、指揮者として実績のある人はいない」「指揮者は拍子を振ることが大切なのではなく、楽曲をどう演奏すべきか伝える力、言葉が少なくても身振りでそれをオケにいかに伝えるのかが肝要なのです」と指導していたが、聞いていて納得させられた。日本の音楽大学指揮科のレッスンのようにピアノ相手にひたすら拍子を刻むことが果たして何の意味があるのか。いっそのこと、指揮科の学生に来年のアカデミーのリハーサルを聴講させ、出席した回数によって単位を与える、との取り組みをした方が有益ではないかとすら思った。何といってもイタリア・オペラの最高峰の巨匠が若手音楽家を指導しながらオペラを作り上げていく過程に立ち会うことは滅多にない貴重な機会にほかならないからである。
公演では栗原、吉田をはじめとする歌手たちもムーティの教えをしっかりと実践し高水準の歌唱を披露した。


公演終了後、受講者たちにムーティから修了証が伝達された。その際、ムーティはコンマスの長原に「君は立派な指揮者になれるよ」と彼の健闘を絶賛。若いメンバーを力強くリードし、水準を超える演奏にまとめ上げたのはムーティの意思を自身の熱演を通して全演者に伝えた彼のコンマスとしての手腕を高く評価したのであった。最後にムーティは「シモン・ボッカネグラは単なる政治劇ではなく、ヴェルディが愛、平和への思いを込めた作品なのです。だからこそ、多くの国の音楽家が集った今回のアカデミーで、取り上げた意義がある」との趣旨の言葉で締めくくった。

なお、来年の東京・春・音楽祭開催直後の4月26日、29日、5月1日に東京文化会館を会場にムーティ指揮でモーツァルトの「ドン・ジョヴァンニ」をフル・ステージ形式で上演することも発表された。
公演データ
リッカルド・ムーティ presents 若い音楽家による「シモン・ボッカネグラ」
9月11日(木)19:00 東京音楽大学100周年記念ホール(池袋キャンパスA館)
ヴェルディ:歌劇「シモン・ボッカネグラ」(演奏会形式、プロローグと全3幕 日本語字幕付き)
指揮:ジェイコブ・ニーマン(プロローグ)、ヒョンソプ・リム(第1幕No.2~5)、ウェイ・リン(第1幕No.6フィナーレ)、佐藤瑛吾(第2幕)、町田謙太郎(第3幕)
シモン・ボッカネグラ:栗原峻希
アメーリア(マリア):吉田珠代
ヤコポ・フィエスコ:湯浅貴斗
ガブリエーレ・アドルノ:石井基幾
パオロ・アルビアーニ:北川辰彦
ピエトロ:片山将司
隊長:大槻孝志
侍女:小林紗季子
合唱指揮:仲田淳也
東京オペラシンガーズ
東京春祭オーケストラ
コンサートマスター:長原幸太
リッカルド・ムーティ指揮「シモン・ボッカネグラ」
9月13日(土)15:00 、15日(月・祝)※取材日19:00 東京音楽大学100周年記念ホール(池袋キャンパスA館)
ヴェルディ:歌劇「シモン・ボッカネグラ」(演奏会形式、プロローグと全3幕 日本語字幕付き)
指揮:リッカルド・ムーティ
シモン・ボッカネグラ:ジョルジュ・ペテアン
アメーリア(マリア):イヴォナ・ソボトカ
ヤコポ・フィエスコ:ミケーレ・ペルトゥージ
ガブリエーレ・アドルノ:ピエロ・プレッティ
パオロ・アルビアーニ:北川辰彦
ピエトロ:片山将司
隊長:大槻孝志
侍女:小林紗季子
合唱指揮:仲田淳也
東京オペラシンガーズ
東京春祭オーケストラ
コンサートマスター:長原幸太
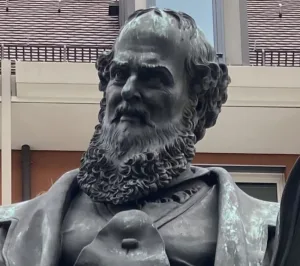
みやじま・きわみ
放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。