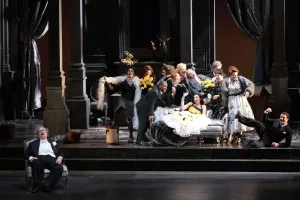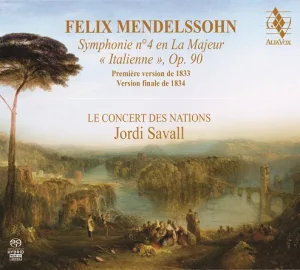ティーレマンのタクトで本気のウィーン・フィルが聴かせた白熱のブラームス
クリスティアン・ティーレマン指揮、ウィーン・フィルハーモニー ウィーク東京公演2日目について報告する。
1曲目、シューマンの交響曲第3番は前夜のブルックナー同様、音楽の自然な流れを重視したアプローチ。弦楽器は14型で管楽器は譜面の指定通り。冒頭に登場する変ホ長調の第1主題からオケ全体が豊かに鳴っており、ライン川のとうとうたる流れが脳裏に浮かぶような雰囲気を醸成する。最近流行のシューマン演奏のようにシンコペーションのリズムを強調することなく、音楽は悠然と進んでいった。第2、3楽章も少し遅めのテンポで明るく伸びやかに旋律が紡がれ、第4楽章では何度も繰り返されるコラール風の主題が荘重に強調された。終楽章は一転、明るく軽やかなフィナーレを作り上げた。

後半はブラームスの交響曲第4番。弦楽器を16型に増強、オケ全体の音量が増し、このオケならではの美しいサウンドと相まって圧巻の聴き応えとなった。第1楽章、転回の技法を使ったヴァイオリンによる第1主題から深く息を吸い込むようにアウフタクトのH(シ)をタップリ弾かせて、冒頭からロマンティックな曲想を濃密に表現していく。中庸なテンポで始まったが曲が進むにつれて演奏の燃焼度が高まっていき自然と加速。再現部後半からコーダにかけての白熱ぶりは〝本気のウィーン・フィル〟の凄さを目の当たりにする思いがした。初日公演の速リポ(クリスティアン・ティーレマン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン2025 東京公演1日目 ② | CLASSICNAVI)にも書いたがティーレマンは今、ウィーン・フィルが最も信頼を寄せているマエストロである。それだけに演奏の熱量が高くなることが多く、この日のブラームスもまさに息を飲むような凄演(せいえん)となった。

第2楽章、フリギア旋法を使ったホルン(1番はロナルド・ヤネシッツ)のメロディーもウィンナ・ホルンのサウンドによって哀愁が一層増して響き渡る。落ち着いた曲想の楽章ながら第1楽章の白熱ぶりが依然としてステージ上に漂っているようで聴き手をさらに引き付けていく。逆に第3楽章はお祭り騒ぎに終始することなく主題が変容して受け渡されていく過程の響きの変化が丁寧に表出されていた。
そして第4楽章は激しさすら覚える活発なアンサンブルが繰り広げられた。コンサートマスターはライナー・ホーネック。渾身の熱演でオケをリードする姿には30年以上にわたって重責を担ってきた音楽家の矜持(きょうじ)を感じさせるものがあった。また、第2主題のフルート(カール=ハインツ・シュッツ)のソロも太く豊かな音色がホールにこだました。コーダは第1楽章同様、白熱の展開となり圧倒的な熱量をもって全曲を締めくくった。

盛大な喝采に応えてヨハン・シュトラウスⅡ世の「美しく青きドナウ」をアンコール。ウィーン・フィルの演奏で、この曲、何も述べる必要はないだろう。なお、この日、来年のウィーン・フィル ウィークの指揮者はリッカルド・ムーティと発表された。
(宮嶋 極)
公演データ
クリスティアン・ティーレマン指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
ウィーン・フィルハーモニー ウィーク イン ジャパン2025 東京公演2日目
11月12日(火)19:00 サントリーホール 大ホール
指揮:クリスティアン・ティーレマン
管弦楽:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
コンサートマスター:ライナー・ホーネック
プログラム
シューマン:交響曲第3番 変ホ長調Op.97「ライン」
ブラームス:交響曲第4番 ホ短調Op.98
アンコール
ヨハン・シュトラウスⅡ世:ワルツ「美しく青きドナウ」Op.314
他日公演
11月15日(土)16:00、16日(日)16:00、いずれもサントリーホール
※プログラム等の詳細はサントリーホールの公式サイトをご参照ください。
https://www.suntory.co.jp/suntoryhall/feature/wphweek2025/
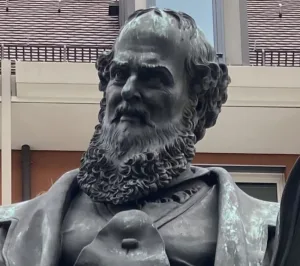
みやじま・きわみ
放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。