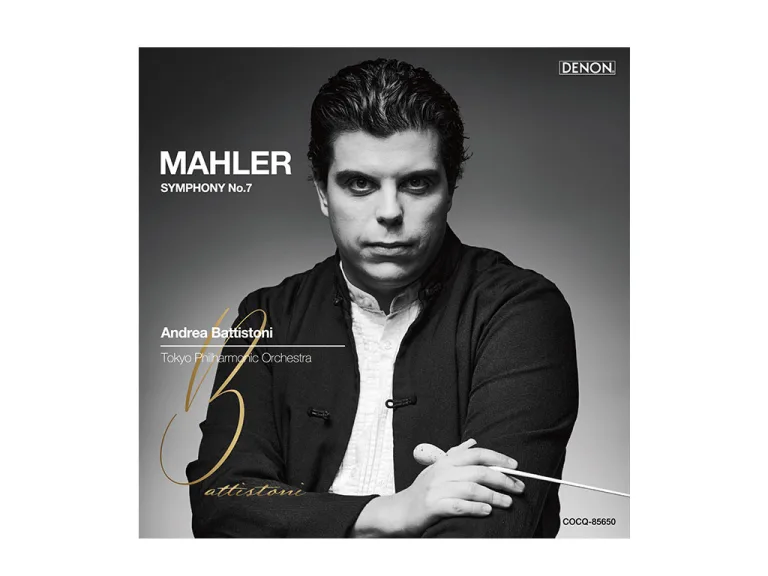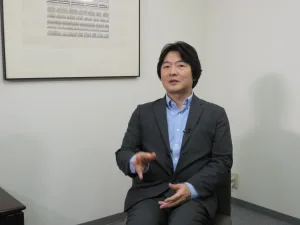ショパンの祖国のオーケストラが奏でる味わい深い響きに支えられてポゴレリッチの個性が全開となったピアノ協奏曲第2番
1984年にユーディ・メニューインによって設立されたポーランドのオーケストラ、シンフォニア・ヴァルソヴィアの日本ツアーから東京公演2日目を聴いた。指揮はクリスティアン・アルミンク、ソリストは人気ピアニスト、イーヴォ・ポゴレリッチ。

ヴァルソヴィアとはポーランド語で首都ワルシャワのこと。折しも同地では5年に1度のショパン国際ピアノ・コンクール(第19回)が開催中。これに合わせるかのようにポゴレリッチをはじめ、マルタ・アルゲリッチ、小林愛実、反田恭平といずれもショパン・コンクールで大きな存在感を示したピアニストが日替わりで登場する豪華ツアーである。
この日のメインはショパンのピアノ協奏曲第2番。ポゴレリッチは例によって開演前から普段着でステージに現れ、ピアノに向かってウオーミングアップを開演ギリギリまで続けていた。弾いていたのはF(ファ)から始まる半音階のスケール。♩=60くらいのゆっくりとしたテンポで左右のバランスを確認するかのようにニュアンスを少しずつ変えながら何度も繰り返していた。Fといえば協奏曲第2番の主調はヘ短調(F-moll)であり、彼は開演直前までFを根音(トニック)にした響きの可能性を探っていたのかもしれない。

実際の演奏は意外にも力強いタッチで強固な構造物を構築していくようなソロ。とはいっても乱暴に聴こえるわけではなく、とことん彫琢(ちょうたく)されたサウンドは透明感があり美しい。時折、一定の音にアクセントを付けて強調するなど随所にメリハリを付けていた。特に第3楽章、マズルカ風のリズムの箇所で少し遅めのテンポでフレーズの区切りを明確に表現し、躍動感を増幅させながらフィナーレに移行していった。ポゴレリッチは今年1月に上岡敏之指揮、読響との共演でも同じ曲を弾いているがこの時はもっと内省的でデリケートな演奏だったと記憶している。一方、この日は力強くゴージャスな雰囲気すら感じさせるなど、同じピアニストとはにわかに信じがたいほど異なるアプローチには大いに驚かされた。ポゴレリッチは常に変化と進化を標ぼうし、新たな境地を切り拓いていく稀有のピアニストであることが伝わってきた。


アルミンクが指揮するシンフォニア・ヴァルソヴィアは、ショパンの祖国のオケだけにこの作曲家ならではの寂寥(せきりょう)感を湛えた滋味深いサウンドでポゴレリッチの変化に富んだソロを支えた。また、前半のドヴォルザークの交響曲第8番は落ち着いた雰囲気の中にも木管楽器の内声部の表出も含めた能弁な演奏が印象に残った。
(宮嶋 極)
公演データ
クリスティアン・アルミンク 指揮 シンフォニア・ 日本ツアー2025 東京公演
10月6日(月)19:00 すみだトリフォニーホール
指揮:クリスティアン・アルミンク
ピアノ:イーヴォ・ポゴレッチ
管弦楽:シンフォニア・ヴァルソヴィア
ドヴォルザーク:交響曲第8番ト長調Op.88
ショパン:ピアノ協奏曲第2番ヘ短調Op.21
※他日公演等の詳細はこちらから
クリスティアン・アルミンク指揮 シンフォニア・ヴァルソヴィアJAPAN TOUR 2025 – KAJIMOTO
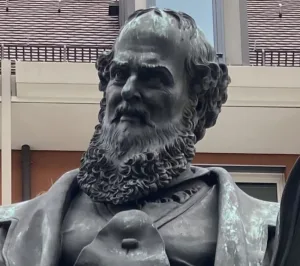
みやじま・きわみ
放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。