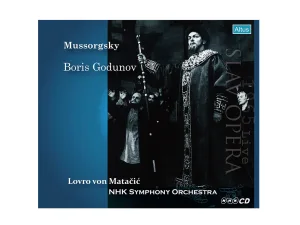ロシア音楽から引き出される透明で明晰なイタリア
以前、バッティストーニと話した際、イタリア人たる自分にとってロシア音楽のメロディーはとても相性がいいと強調するのが、強く印象に残った。プロコフィエフにしても、力強いリズムや斬新な和声、不協和音が目立つとはいえ、ロシア音楽の伝統に根差した叙情的なメロディーに支えられ、それが魅力なのだ——という話だった。
プロコフィエフにこだわる理由がもう一つある。バッティストーニの生まれ故郷である北伊ヴェローナが舞台の「ロメオとジュリエット」に基づくバレエ音楽を書いているからである。
したがって、プロコフィエフ・スペシャルであるこの日もバレエ音楽「ロメオとジュリエット」組曲がメインに据えられた。

演奏順を無視し、後半の「ロメオとジュリエット」から記すと、演奏されたのは第1組曲と第2組曲からバッティストーニが抜粋した7曲。この指揮者らしい特徴がいっそうの洗練を得て強調された。バッティストーニが指揮すると陰影にも色彩が添えられ、重厚な響きにも切れ味が生まれる。
たとえば、1曲目の「モンタギュー家とキャピュレット家」の威圧的な序奏にも、ヴェローナの空気感につながる輝きが加わる。2曲目の「少女ジュリエット」は、東京フィルの弱音を含む微細な表現も冴え、少女の軽快な足どりにアディジェ川の川面のきらめきが反映しているようだ。4曲目の「ロメオとジュリエット」は旋律の叙情美がイタリアそのもの。また、5曲目の「ティボルトの死」の劇的な躍動、7曲目の「ジュリエットの墓の前のロメオ」の慟哭(どうこく)は、巨大な響きも透明かつ明晰だった。強弱や緩急にも雑な動きがなく、7曲を通したドラマとしても均衡がとれていた。

実は、最初に演奏された「3つのオレンジの恋」組曲もイタリアに由来する。もとになったオペラは、18世紀イタリアの劇作家カルロ・ゴッツィの寓話劇が原作。だからだろう、バッティストーニは土の香りは無視して、太陽の輝きや流麗なキレを遠慮なく強調した。そこで発揮される鮮やかさは、この指揮者と東京フィルの相性のよさがあってこそのものと思われた。
そして、辻󠄀井伸行をソリストに迎えてのピアノ協奏曲第2番。辻󠄀井はスピード感ある演奏に独特の叙情性を滲(にじ)ませて快走する。少し抽象的な表現になるが、この人のピアノには、音になにか有機的な生命力のようなものが宿っていると感じられる。とくに第1楽章の長く激しいカデンツァは鮮やか。「有機的な明快さ」は全体として、バッティストーニ指揮の東京フィルとの相性がよかった。
(香原斗志)

公演データ
バッティストーニ×辻󠄀井伸行 プロコフィエフ・スペシャル
9月10日(水)19:00東京オペラシティ コンサートホール
指揮:アンドレア・バッティストーニ
ピアノ: 辻󠄀井伸行
管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団
プログラム
プロコフィエフ:「3つのオレンジへの恋」組曲より〝変わり者たち〟〝スケルツォ〟〝行進曲〟
プロコフィエフ:ピアノ協奏曲 第2番 ト短調 Op.16
プロコフィエフ:バレエ音楽「ロメオとジュリエット」組曲より〝モンタギュー家とキャピュレット家〟〝少女ジュリエット〟〝仮面〟〝ロメオとジュリエット〟〝ティボルトの死〟〝別れの前のロメオとジュリエット〟〝ジュリエットの墓の前のロメオ〟
ソリスト・アンコール
プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第7番 第3楽章

かはら・とし
音楽評論家、オペラ評論家。オペラなど声楽作品を中心に、クラシック音楽全般について執筆。歌唱の正確な分析に定評がある。著書に「イタリア・オペラを疑え!」「魅惑のオペラ歌手50:歌声のカタログ」(共にアルテスパブリッシング)など。「モーストリークラシック」誌に「知れば知るほどオペラの世界」を連載中。歴史評論家の顔も持ち、新刊に「教養としての日本の城」(平凡社新書)がある。