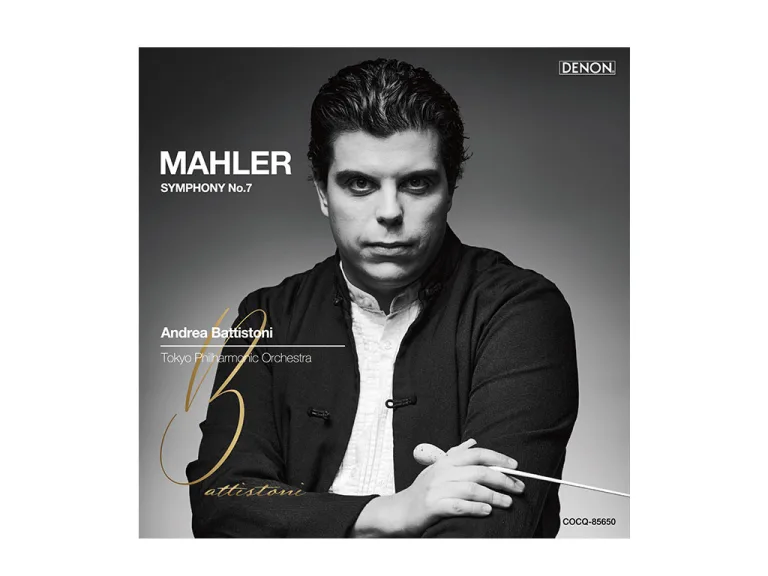ゆっくり、じっくりと聴き手の心におちる声楽と管弦楽
2014年から東京交響楽団第3代音楽監督を務めてきた英国人指揮者ジョナサン・ノット最後のシーズン、2025年は第二次世界大戦終結から80年の節目にも当たる。ノットは2014年12月のミューザ川崎シンフォニーホール10周年記念コンサートでマーラー「交響曲第8番(一千人の交響曲)」を指揮した際に東響コーラスの存在を知り、「アマチュア中心ながら厳しいオーディションと訓練を通じ、高い水準を保っている」と信頼を寄せてきた。節目の年の共同作業の総仕上げにブリテン「戦争レクイエム」、J.S.バッハ「マタイ受難曲」に挑むことを決めたのも同コーラスの存在あってだ。

「戦争レクイエム」は7月19日にミューザ川崎、21日にサントリーホールで演奏。筆者は後者を聴いた。来年で没後50周年を迎える20世紀英国を代表する作曲家ベンジャミン・ブリテンは第二次大戦中にドイツ軍の爆撃で破壊されたコヴェントリー大聖堂の再建(1962年)に際し、この曲を書いた。ラテン語によるミサ典礼文と第一次大戦にたおれた英国の詩人ウィルフレッド・オーウェンの戦争詩を融合させ、第二次大戦で敵対した旧ソ連(ロシア=ソプラノ)、英国(テノール)、ドイツ(バリトン)の独唱者3人を起用するアイデア自体がそもそも複数の時代をまたぎ、普遍の説得力を放つ。

ミサ側に寄り添うチェプラコワは今シーズン、ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場にデビューした中堅でやや年長、英独の戦死兵の思いを担うテノールのルイスとバリトンのウィンクラーは30歳前後とキャリアに多少の差はあるが、全員がリリックで透明度の高い声でそろい、テキストに込められたメッセージを曇りなく届けた。

プログラム冊子の対訳ではなく、日本語訳の字幕を用意した結果、ラテン語と英語の内容を雑音なしに細大漏らさず伝えることができた。様々なレクイエムを歌い込んできた東響コーラス(冨平恭平指揮)は隅々まで精妙に整い、明瞭な発音はもちろん、テキストの深い理解でも賞賛に値する。2階RC扉前の廊下に位置した東京少年少女合唱隊(長谷川久恵指揮)は大木麻理(オルガン兼)のハルモニウムともども、幽玄な響きを醸し出した。

東響はグレブ・ニキティンがリードする大編成、小林壱成がリードする小編成の2ブロックに分かれ、ホルン6人をはじめとする前者の迫力、小林やハープの渡辺沙羅らのソロが光った後者の繊細な美観それぞれがノットの強い統率の下、声楽チームと渾然一体の音楽に収斂していく。ノットは数週間前、スイス・ロマンド管弦楽団音楽監督として最後の日本ツアーを成功させたばかり。当たり前といえば当たり前だが、2つのオーケストラの持ち味をとことん把握し、全く違う感触の音楽を引き出す。スイス・ロマンドのカラフルに弾けたストラヴィンスキーに対し、東響とのブリテンには抑制の美意識、内面への深い沈潜でゆっくり、じっくりと聴き手の心に染み込んでいく美しさがあった。
(池田卓夫)

公演データ
東京交響楽団第732回定期演奏会
7月21日(月・祝)14:00サントリーホール 大ホール
指揮:ジョナサン・ノット(音楽監督)
ソプラノ:ガリーナ・チェプラコワ
テノール:ロバート・ルイス
バリトン:マティアス・ウィンクラー
合唱:東響コーラス
合唱指揮:冨平恭平
児童合唱:東京少年少女合唱隊
児童合唱指揮:長谷川久恵
管弦楽:東京交響楽団
コンサートマスター:グレブ・ニキティン
プログラム
ブリテン:戦争レクイエムOp.66(字幕付き)(78’)

いけだ・たくお
2018年10月、37年6カ月の新聞社勤務を終え「いけたく本舗」の登録商標でフリーランスの音楽ジャーナリストに。1986年の「音楽の友」誌を皮切りに寄稿、解説執筆&MCなどを手がけ、近年はプロデュース、コンクール審査も行っている。