名手たちの個性を際立たせるドゥダメルのタクトで、ベルリン・フィルの高いスペックが全開となった日本ツアー初日公演
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の日本ツアーが2日、大阪・フェスティバルホールでの特別公演で幕を開けた。

前半はクリスティーナ・ランツハマー(ソプラノ)をソリストにベートーヴェンの劇音楽「エグモント」。バリトンの宮本益光が物語のあらすじを紹介する語りを担当した。弦楽器の編成は14型で、ヴァイオリンは対抗配置。2,700人の客席を持つ大きなホールだが、筆者が座った1階24列目でも序曲の冒頭から弦楽器が重厚に響いてくるあたり、さすがベルリン・フィルと目を見張るものがあった。ホールの音響の特徴かもしれないが、全体の響きが柔らかく聴こえる。フレージングもレガート気味で、ピリオド奏法に寄せた演奏とは一線を画するスタイルであった。第7曲目「クレールヒェンの死」あたりから、強弱を細やかに変化させて、終曲「勝利のシンフォニア」に向かって高揚感を増幅させ、序曲と同じヘ長調のコーダへと勢いをもって回帰させ締めくくった。ランツハマーは透明感のある声で繊細に歌い上げた。


後半はチャイコフスキーの交響曲第5番。金管楽器が活躍するこの作品でも弦楽器の編成は14型。とはいえ金管が大音量で鳴り響く箇所でも弦楽器の重厚なサウンドがしっかりと聴こえ、全体の音量バランスが崩れる場面は皆無だったことで、ベルリン・フィルの合奏能力の高さを再確認する思いがした。
第1楽章冒頭、クラリネット(ヴェンツェル・フックス)のソロから木管楽器首席陣は自在かつ雄弁な演奏を聴かせた。この日はフルート(エマニュエル・パユ)、オーボエ(アルブレヒト・マイヤー)、ファゴット(シュテファン・シュヴァイゲルト)という百戦錬磨の名手が揃った。ソロの場面ではドゥダメルは彼らの裁量に任せている感じで、タップリと表情付けされた妙技が随所で披露された。そうした中、注目を集めたのが試用期間をクリアし正式に首席奏者に就任した中国出身の若きホルン奏者ユン・ゼンだ。第2楽章の長いソロを美しい弱音で吹き始め、途中少し音程が揺らぐ場面があったものの、全体としては歌心にあふれた聴かせるソロで終演後には盛大な喝采を集めていた。

終楽章はドゥダメルらしさが顕著に表れ、情熱がほとばしるような高揚感は彼ならではのもの。コーダの最後の5小節、フォルティッティッシモで演奏されるティンパニ(ヴィンセント・フォーゲル)のE(ミ)音のトレモロを弱音からクレッシェンドで最強音に至らせ最後の4音を強調したことも面白かった。熱気あふれるフィナーレに拍手は鳴り止まず、ドゥダメルはオケ退場後の舞台に再登場し歓呼に応えていた。
(宮嶋 極)

公演データ
グスターボ・ドゥダメル指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 特別公演
7月2日(水)19:00 フェスティバルホール(大阪)
指揮:グスターボ・ドゥダメル
ソプラノ:クリスティーナ・ランツハマー
語り:宮本 益光
管弦楽:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
コンサートマスター:樫本 大進
プログラム
ベートーヴェン:劇音楽「エグモント」Op.84
チャイコフスキー:交響曲第5番ホ短調Op.64
※他日公演
7月3日(木)18:45 愛知県芸術劇場コンサートホール
演目、出演者は2日と同じ
ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 ヴァルトビューネ河口湖2025
7月5日(土)17:30、6日(日)15:00 河口湖ステラシアター
指揮:グスターボ・ドゥダメル
管弦楽:ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団
プログラム
ガブリエラ・オルティス:カモシカ
デューク・エリントン:「スリー・ブラック・キングス」より〝マーティン・ルーサー・キング〟
アルトゥーロ・マルケス:ダンソン第2番
エヴェンシオ・カスティリャーノス:パカイリグアの聖なる十字架
ロベルト・シエラ:アレグリア
アルトゥーロ・マルケス:ダンソン第8番
レナード・バーンスタイン:「ウエスト・サイド・ストーリー」より〝シンフォニックダンス〟
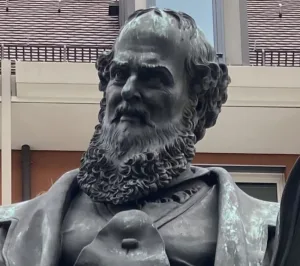
みやじま・きわみ
放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。


















