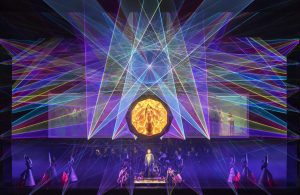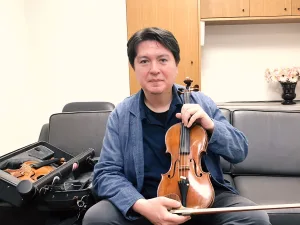天才ピアニストとして注目を集めるアレクサンドラ・ドヴガンの成長ぶりを示した来日公演
今年18歳となるピアニスト、アレクサンドラ・ドヴガンのリサイタルを聴いた。彼女の来日公演は2022年9月以来、2度目。筆者は前回もその公演を聴き、当時、毎日新聞のニュースサイト「毎日jp」の中で展開していたクラシックナビにレビューを書いている。(アンコール:マイスキー、カヴァコス、ドヴガン 秋のリサイタル一挙レポート | 毎日新聞)読み返してみると「演奏のスタイルは正攻法で(中略)何より驚いたのはその音色である。この若さにして彼女ならではのサウンドを持ち合わせていたからだ。(中略)怜悧(れいり)で凛(りん)としたたたずまいを持ったサウンドとでもいうのであろうか」との感想を記していた。
あれから約2年半、ドヴガンは目覚ましいまでの成長を遂げていた。プログラム前半は前回と同じくベートーヴェンとシューマンの作品、後半は前回オール・ショパンだったのに対して、今回はラフマニノフとプロコフィエフのロシアもの、それも同じニ短調の作品を選曲した。

1曲目、ベートーヴェンのソナタ第31番の冒頭から変化は明らかだった。音色の種類がより多彩になっていたからである。凛としたたたずまいは健在だった一方で、そこに柔らかさや奥行きを感じさせる響きも加わっていた。ベートーヴェンならではの構造感が十分表出されていたことに加えて、彼女の〝音のパレット〟に新たな色が加わったことで、表現の幅が広がったように感じた。
2曲目のシューマンのソナタでは、速いパッセージにおける見事に揃った粒立ちの流麗さが強く印象に残った。この2年半の間に彼女が磨き上げた新たな表現スタイルなのだろう。アンコール3曲目、ショパンのワルツでも細かな音符が連なる箇所で急激なアッチェレランド(次第に速くすること)をかけて、流麗な粒立ちを存分に披露してみせた。

後半のラフマニノフ「コレルリの主題による変奏曲」は、スリムな姿からは想像できないほどの力強いフォルティッシモと繊細なピアニッシモを巧みに使い分け、抒情あふれるロシア・ピアニズムの伝統を継承していこうとの意欲を感じさせる演奏。
プロコフィエフのソナタでは、スケールのような主旋律に対する低音域の和音の深遠さ、そこから醸成される不気味な雰囲気は彼女が曲の解釈を深めていこうとの意欲をもって作品に挑んでいることを窺わせるものだった。
アンコールで演奏したベートーヴェンのロンド・ア・カプリッチョの躍動感、ラフマニノフの音の絵における色彩感、そして前述のショパンの粒立ちの美しさは、正規のプログラムで示した彼女の成長ぶりを再確認させてくれるものでもあった。
(宮嶋 極)
公演データ
アレクサンドラ・ドヴガン ピアノ・リサイタル
2月12日(水)19:00 紀尾井ホール
ピアノ:アレクサンドラ・ドヴガン
プログラム
ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第31番変イ長調Op.110
シューマン:ピアノ・ソナタ第2番ト短調Op.22
ラフマニノフ:コレルリの主題による変奏曲ニ短調Op.42
プロコフィエフ:ピアノ・ソナタ第2番ニ短調Op.14
アンコール
ベートーヴェン:ロンド・ア・カプリッチョ ト長調Op.129「なくした小銭への怒り」
ラフマニノフ:音の絵Op.33-5
ショパン:ワルツ第7番嬰ハ短調Op.64-2
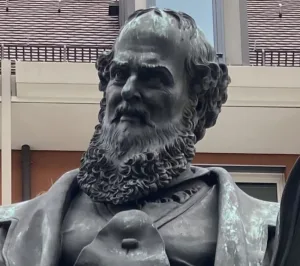
みやじま・きわみ
放送番組・映像制作会社である毎日映画社に勤務する傍ら音楽ジャーナリストとしても活動。オーケストラ、ドイツ・オペラの分野を重点に取材を展開。中でもワーグナー作品上演の総本山といわれるドイツ・バイロイト音楽祭には2000年代以降、ほぼ毎年訪れるなどして公演のみならずバックステージの情報収集にも力を入れている。